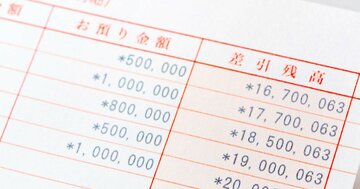【要注意】プロが作った遺言書が無効!? その超意外な理由とは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
プロが作った遺言書が無効!? その超意外な理由とは?
お盆の時期、ご家族で相続について話し合われたご家庭も多いかと思います。本日は、相続と遺言書についてお話しします。
一般的に活用されている遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。厳密には秘密証書遺言や危急時遺言などの遺言もありますが、特殊遺言として説明を割愛します。
自筆証書遺言とは、その名前の通り、遺言の内容を自筆して作成するものです。
公正証書遺言とは、公証役場という所で、公証人という法律のスペシャリストが本人の意向を確認して作成します。公証人の多くは元裁判官や検事です。
ただ、公正証書遺言であっても絶対に安全とは言い切れません。公正証書遺言が無効にされた裁判例はたくさんあります。
例えば「遺言者本人が認知症等と診断されていた」「施設の介護記録や家族の証言などから、正常な判断ができない状態で作成された遺言書と認定された」といったケースが挙げられます。
「おいおい。そもそもそんな状態で公正証書遺言なんて作れるの?」と思う方も多いでしょう。
公正証書遺言の立ち合いを数多くしてきた私の経験からお伝えすると、実は、公正証書遺言は意外と簡単に作れてしまいます。
公証人とひと言に言っても、遺言作成に取り組む姿勢は、結構バラバラです。遺言書の内容を読み上げて「この内容でいいですね? 問題がなければ、ここに名前を書いてください」と、ささっと済ませる公証人もいれば、「遺言書を読み上げる前に、まず、あなたがどのような内容の遺言書を作りたいのか、今この場で言ってみてください」と内容を慎重に確認する公証人もいます。
裁判で無効とされた公正証書遺言のほとんどは、前者のようなプロセスで公正証書を作成したケースです。
公正証書遺言の作り方
ここで、公正証書遺言を作る流れを簡単に説明します。
まず公証役場に連絡して、どのような内容の遺言書にするかを伝え、遺言書の原案を作ってもらいます。その原案の内容に問題がなければ、日程を調整し、証人2名を連れて公証役場に行きます。公証人が遺言書を読み上げ、内容に問題が無ければ、本人が遺言書に署名して完成です。遺言書の原案を作る段階では、遺言者以外の人(家族や弁護士等の専門家)が代理で行うことも可能です。
そのため本人は、公証役場に行き「問題ないです」とだけ言えれば、公正証書遺言は作れてしまうわけです。ちなみに、公証役場では遺言者本人が認知症の診断を受けていることなどは聞かれません。また身元確認も、実印と印鑑証明書だけあればよく、実際に、替え玉受験ならず替え玉遺言がされた事件も実在します。
遺言書の安全性を高めるには?
安全性をより高めるためにできることを紹介します。それが、第1章でもお伝えした通り、遺言書を作成してから早い時期(できれば1か月以内)に、かかりつけの主治医から「この人の意思能力は問題ない」と診断書をもらっておくことです。万全を期すのであれば、遺言書を作成する前と後に、2回診断書を取っておけばより安心ですね。
遺言書を巡る争いの多くは、「この内容は故人の本当の想いではない」という、立証が非常に難しく、水掛け論になりやすいことが争点になっています。「どこからが認知症か」という線引きは曖昧で難しいですが、「少なくとも遺言作成時点において意思能力がはっきりあった」ことを立証するのは比較的容易です。転ばぬ先の杖として、家族の絆を守るためにも念には念を入れて対策する姿勢が大切です。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)