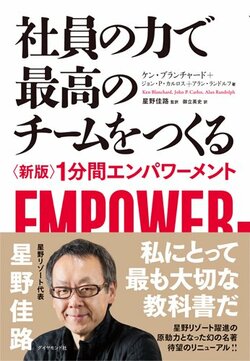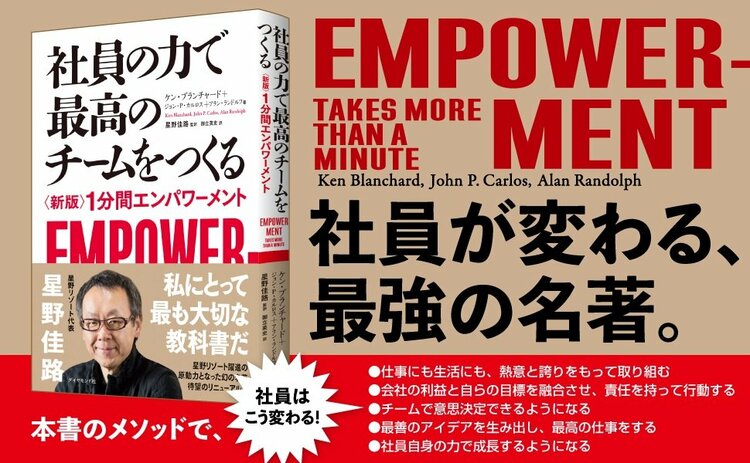低い社員モチベーション、高い離職率、採用難……。今や日本のリゾート業界を牽引する星野リゾートだが、1990年代にはそんな組織の課題に直面していたという。ここから会社を生まれ変わらせたのが、「エンパワーメント」だった。この本がなければ今の会社は存在しなかったと記す星野佳路代表が監訳者を務めるのが、『社員の力で最高のチームをつくる』(ケン・ブランチャード他著)。本書が説く「エンパワーメント」とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
いかにしてエンパワーメントは理解され、実現されたか
社員一人ひとりが高いモチベーションを保ち、自発的にさまざまな行動を起こし、大きな成果を目指そうとする。そんな組織を持つことは、リーダーにとって理想ではないか。
「エンパワーメント」は、自律した社員が自らの力で仕事を進めていける環境をつくろうとする取り組みだ。社員のなかで眠っている能力を引き出し、最大限に活用することを目指している。
エンパワーメントの企業文化が定着すればどうなるか。
本書で紹介されている米国高級食品小売チェーンのトレーダー・ジョーズ社では、従業員と多くの情報を共有し、彼らが自律的に行動できる業務範囲を広げ、責任を重くすることで、26パーセントを超える年間売上増加率を記録したという。
エンパワーメントに取り組んだ8年間で、1店舗当たりの売上を年率10パーセント、店舗数をほぼ100パーセント、総売上を500パーセント以上も引き上げることに成功した。
また、エンパワーメントを真に進めることに成功した意外な組織として、IRS(合衆国内国歳入庁)ロサンゼルス支庁の収税局があるという。役所にできたことが、あなたの会社でできないはずがない。本書はこう説く。
ただし、エンパワーメントを完全に理解することは難しく、実行はもっと困難だ、とも本書にはある。
だから本書では、ある会社の経営者が、エンパワーメントの導入に成功した会社の経営者<エンパワー・マネジャー>から学びを乞うという物語仕立てになっている。
いかにしてエンパワーメントは理解され、実現への第一歩が踏み出されたのか。
組織の階層を減らしても、変化は起こらない
物語の主人公は、中堅家庭用品メーカーの社長兼CEOのマイケル・ボブス。
MBAで学んでいた頃から、積極果敢で実行力があるという評判を持ち、会社がうまくいかない原因のほとんどはトップのリーダーシップ不足であるというのが持論だった。
1年前に社長に就任すると、それまでの自分のやり方を踏襲し、あらゆる意思決定を自分で行った。現場に介入し、部下任せにせずに自分で決めるべきことは決めた。ところが、会社はうまくいっていなかった。
デスクの上には、役員会が推薦したコンサルタントから送られた額が置かれていた。
「過去に成功をもたらした考え方が、将来も成功をもたらすとは限らない。」(P.16)
コンサルタントは会社が求めた報告書の結論部分で「まず、経営者が考え方を変えなくてはならない」という耳の痛い指摘があった。
会社を生き残らせるには、顧客と品質を最優先し、収益性とコスト効率を高め、市場変化に迅速かつ柔軟に対応し、イノベーションを継続しなくてはならない。それが、コンサルタントの提案だった。
そのためには、全社員を目標に向かわせる方法を見つけなくてはならないと何度も聞かされた。社員には、自分が会社のオーナーであるかのような自覚をもって、あるいは起業家の気概をもって、仕事に取り組んでもらうことが大切だという。
そう考えたとき、マイケルの中に「エンパワーメント」という言葉が浮かぶ。マイケルにはこれが必要だとアドバイスしてくれた人がいたのだ。しかし、マイケルはすでに試み、ほとんど成果が上がらないという結果も見ていた。
ところが、6カ月経っても、なにも変化していないように思えた。社員の行動は、階層を減らす前の官僚主義的な気分のままで、なんの変化も見られなかった。
社員に意思決定の権限さえ与えれば自然に変化が起こると思っていたが、そんな簡単な話ではなかったのだ。
そんなとき、「エンパワーメント」に成功した企業を紹介した記事に出会う。
テクノロジーはどんどん進化したのに
その記事は、社員の「エンパワーメント」に成功した企業として、ある通信機器メーカーを取り上げ、賞賛していた。
その会社の社員は意欲にあふれ、まるで自分が会社のオーナーであるかのように行動しているという。記事は、CEOのサンディ・フィッツウイリアムに<エンパワー・マネジャー>の称号を与えていた。
マイケルは、<エンパワー・マネジャー>に会って、話をすることを決意する。これまでに相談したコンサルタントは、誰も実際には自分で会社を経営したことがなかった。しかし、このCEOなら実務をふまえた話ができるかもしれない。
人の助けを必要としていることを認めるのが嫌いな性格のマイケルだったが、自分を励まし、思い切って電話をかけた。突然の電話に、<エンパワー・マネジャー>はいきなりいくつかの質問をマイケルに投げかける。
マイケルは「社員に意思決定の権限を与える」エンパワーメントがうまくいかなかったことを伝える。<エンパワー・マネジャー>はこう語った。
問題は、社員にベストを尽くす意思や能力がないことではなく、ベストを尽くすことを怖がっていることだと<エンパワー・マネジャー>は語る。
なのに、ほとんどの組織は、社員を励まして正しい行動を促すのではなく、間違いを見つけて懲らしめることばかりに意識が向いているのだ、と。
マイケルは、<エンパワー・マネジャー>に直接、会いに行く。エンパワーメントは実現までに時間がかかること。とても難しいこと。エンパワーメントを目指そうとするとき、古い自分の考えが邪魔になることを聞かされる。
一方でマイケルは、エンパワーメントの考え方に両手を挙げて賛成できないとも伝える。部下がエンパワーされてしまえば、上司は何をすればいいのかということになりかねないからだ。
必要なのは、上司が新しい役割を果たすことだった。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。