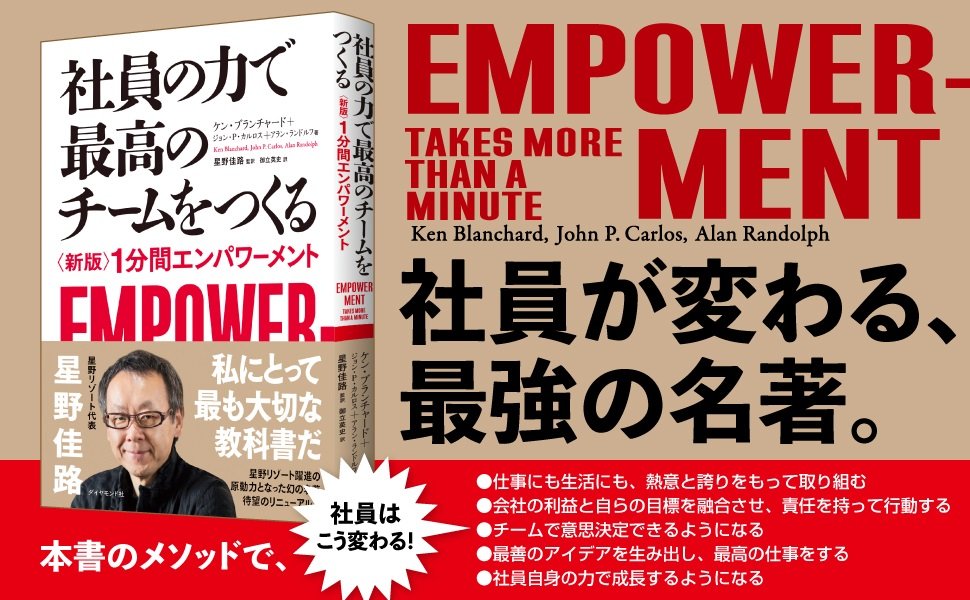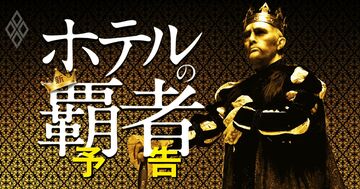「今の星野リゾートは、この本がなければ存在しなかった」。星野リゾート・星野佳路代表がこう語るのが『社員の力で最高のチームをつくる』だ。なぜ本書は、多くの読者に読み継がれているのか。それは、本書の内容をそのまま実行することで組織を劇的に変えることができるからだ。星野氏はこうも語っている。「書かれている内容を一言一句、そのまま実践することだ」。本連載では、星野氏が本書の内容を実践した際のエピソードを3回にわけてお伝えしていく。前編はこちら。
 界 箱根 大浴場
界 箱根 大浴場
さらなる問題に遭遇
さまざまなことが好転し始めた実感を得て、私たちは経営に自信を持つようになったが、まもなく大変困った事態が起きた。
各職場のスタッフが継続して改善に取り組む中で、多くの問題が解決され、残された課題は難度が高いものに絞られてしまったのだ。つまり、お金がかかる対策である。
客室のチームからは「布団など多くの備品を買い直さないと、これ以上満足度は上がらない」、食堂からは「食器を交換する必要がある」、フロントからは「増員して今できていないサービスを提供したい」、温泉大浴場担当からは「そろそろ露天風呂をつくる必要がある」などなど、コスト増になる提案がたくさん上がってきた。
社員たちの目は輝き始めているのに、私の目が曇り始めるという逆転現象が起こったのだ。
提案の多くは妥当性があり、星野温泉旅館がよくなっていくためにはいつか実施しなければいけない投資だ。
しかし、資金は限られていた上に、顧客満足に効果がある対策でも、それらが追加の収益につながるのか心配だった。
もしつながる場合でも、新たなキャッシュフローがいつ発生するのかがわからなかった。
リスクを感じた私が、いろいろな理由をつけて先延ばししていると、ある社員から「社長は顧客満足を本気で上げようとしていない」と指摘された。
焦った私は思わず「顧客満足は本当に重要なのか?」と言ってしまった。この一言で、ようやく社員の中に目覚め始めた価値観が崩壊していくのを感じた。
顧客満足はどのように利益と結びつくのか
マネジメントとしてこの表現は間違っていたが、その真意は一応こうだ。
企業活動の目的は利益を上げることであり、顧客満足はその手段であるはずだ。しかし、経営していた私の実感として、旅館の顧客満足を上げようとすると、利益は圧迫されるのである。
サービス産業の論文や書籍には、顧客満足は重要であるとは一様に書いてあるが、それが実際にどのようなメカニズムで利益に結びつくのかについては、誰も把握していないように感じた。
「顧客満足は善であるから、それをしっかりとやっていれば神様がどこかで見ていてくれて、いつか必ず利益というご褒美をくれるだろう」と信じているかのようなのだ。これで経営になるのだろうか。
同業にも学びを求めたが、驚いたことに、多くの経営者が「顧客満足の向上努力は必ずしも利益につながるとは限らない」「ある程度手を抜くことが収益の最大化につながる」と考えているようであった。
そうならば、どの程度手を抜くのが最適なのかを知りたくなるが、感覚としてはクレームが出る寸前まで手を抜くことが最適という感じだ。
クレームが発生すると新たなコストが発生し収益を下げるので避けるべきであるが、満足度が非常に高い状態を達成するにはコストがかかりすぎるので、それも収益を下げるという理屈だ。
確かに1990年代に日本国内でリゾート滞在を経験してみると「文句を言うほどではないが、大変満足したとも言えない」というモヤモヤしたサービスだった印象を受けたが、その背景が見えた気がした。
こんなことで日本観光は世界で勝てるのだろうか、というほど当時の私は高い意識を持っていなかったが、それでも、これでは仕事は面白くならないと思った。
この話をすると「口コミが重要だから顧客満足は大事だ」という説を発想する読者も多いだろう。これはSNSの発展で近年ますます重視されている。
しかし、それならば口コミするセグメントを特定し、そこだけに集中してコストをかけて、よいサービスを提供すべきとなる。
そもそも、悪く言われたくないから頑張る、ネット上で褒めてほしいからよいサービスを提供するということで、私たちの仕事はよいのだろうか。
私は今でもこの理屈に納得していない。口コミをする人であろうがなかろうが、いらしていただいた顧客に喜んでもらうことが収益増に結びつくというメカニズムがきっとどこかにあるはずで、そうでなければいけないと思っているのである。
後編は7/29公開です