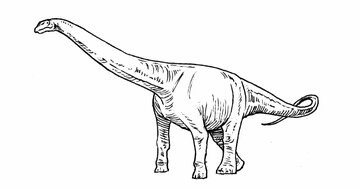人類の歴史は、地球規模の支配を築いた壮大な成功の物語のようにも見える。しかし、その成功の裏で、ホモ・サピエンスはずっと「借りものの時間」を生きてきた。何千年も続いた栄光は、今や終わりが近づいている。なぜそうなったのか? 『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』は、人類の繁栄の歴史を振り返りながら、絶滅の可能性、その理由と運命を避けるための希望についても語っている。竹内薫氏(サイエンス作家)「深刻なテーマを扱っているにもかかわらず、著者の筆致がユーモアとウィットに富んでおり、痛快な読後感になっている。魔法のような一冊だ」など、日本と世界の第一人者から推薦されている。本書の内容の一部を特別に公開する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
すべての種は必ず滅びる
ホモ・サピエンスは今、歴史上きわめて重要な時期にある。人類の波がこれまで絶えず膨らみ続けてきた中で、いよいよその頂点に達し、これからは引き始めるという、まさに転換点に立っているのだ。
今のように人口が多い時代ならではの、膨大な知の蓄積を活かすことができなければ、宇宙への進出は行き詰まり、やがて立ち消えてしまうだろう。すでに述べたように、偉大な発明を育てるには、何億人、場合によっては数十億人という規模の文明が必要だ。
二三〇〇年ごろには世界人口が一〇億人を下回るとする予測もある中で、資源は増えるどころかむしろ枯渇しつつある。
そうした未来を考えると、宇宙への進出は、人口が大きく減少して技術革新と創造力を支えきれなくなる前の、これから一世紀か二世紀のうちに、相当な段階まで進んでいなければならない。
だからこそ、私たちは今、このことについて真剣に考え始めなければならない。
まず私たちが認識すべきなのは、人類も例外ではなく、いずれは絶滅するという事実だ。長期的に見れば、すべての種は必ず滅びる。
古生物学者の故デイヴィッド・ラウプは、かつて皮肉を込めてこう語ったという。「おおざっぱに言えば、地球には生命など存在しない。なぜなら、これまで地球に現れた種の九九パーセントは、すでに絶滅してしまっているのだから」。
5回の大量絶滅とは?
種の絶滅は、いつの時代にも起きてきた。だが、地球の歴史には、ごく普通に起こる種の交代や舞台裏での静かな退場をはるかに上回る規模で、絶滅が怒濤のように押し寄せた時期がいくつか存在する。
過去五億四千万年のあいだに、こうした「大量絶滅」と呼ばれる出来事が少なくとも五回起きたことが知られている。
なかでも最も深刻だったのは、約二億五千万年前、ペルム紀の終わりに起きたものだ。連続的な超巨大火山噴火が有毒ガスを大気中に放出し、地球の平均気温を数度押し上げた結果、海ではおよそ九五パーセントの種が、陸では七〇パーセント以上の種が、数十万年という時間の中で姿を消した。
次に激しかったのは、六千六百万年前、白亜紀末の絶滅である。こちらのほうがよく知られているのは、そのきっかけが突発的かつ劇的だったからだ。
恐竜たちの絶滅と次の大量絶滅の可能性
小惑星の衝突が引き金となって、絶滅の波が一気に広がり、地球で最も有名な先史時代の生き物―恐竜たち―が、突然この世界からいなくなった。
そして今、人類が地球の生態系を支配する時代に入り、第六の大量絶滅がすでに始まっているのではないか、という懸念が広がっている。
現時点での科学的な見解では、ホモ・サピエンスが生物多様性にもたらしている影響は、過去の五大絶滅のレベルにまでは達していないとされている―少なくとも、まだそこまでには至っていない。
だが、もし人類が今の行動をあと五百年続けるようなことがあれば、そのレベルに達する可能性は高い。
(本原稿は、ヘンリー・ジー著『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』〈竹内薫訳〉からの抜粋です)