イギリスのウォーリック大学、ケンブリッジ大学、上海の復旦大学の共同研究チームは、1890人におよぶ14歳(14歳から飲酒可能な国において)の男女の脳活動を、機能的MRIにより調査しました。
それにより、アルコール依存症では、脳の前部にある内側眼窩前頭皮質(mOFC)と、脳の中心部にある背側中脳水道周囲灰白質(dPAG)という、2つの部位の相互作用が重要であることがわかりました。
mOFCは、不快な状況や緊急事態を感知すると、その情報をdPAGに送ります。dPAGは闘争や逃走、すくみ反応などの動物のさまざまな防御行動に関わるとされる脳領域です。そしてdPAGでは、その状況から逃げる必要があるかどうかを判断します。しかし、アルコール摂取によってdPAGの活動が抑制されると、脳は“危険から逃れる必要性”に反応できなくなります。これは、シラフ時に過剰になっていたdPAGの活動が、アルコールの摂取によって一時的に落ち着くための現象です。
その結果、アルコールを飲むことで得られるメリットだけを感じ、有害な副作用を感じなくなってしまうのです。そのため、現実逃避を求めてアルコールを大量に摂取する、強迫的な飲酒が発生すると考えられます。
また、アルコール依存症の人は、シラフ時にdPAGが過剰に活動しており、この過活動状態を補うために、アルコール摂取による一時的な抑制効果に依存する傾向があります。日常的にdPAGの過剰な活動が補われるよう、緊急にアルコールに頼ろうとするのです。これが衝動的飲酒の原因と考えられます。このような脳の反応は、決して心の弱さや根性不足のせいではなく、むしろ生存戦略として進化の過程で培われた必然的な適応反応です。
適切な治療や環境の変化が
脳に良い影響を与える
しかし、私たちの脳には「くじけない脳」として再構築される可能性が秘められています。
繰り返される失敗や依存の状態に直面しても、脳は状況に応じて変化する可塑性を活かし、適切な治療や環境の変化により、健全な機能を取り戻す力を持っているのです。アルコール依存症の根底にあるこの生物学的メカニズムを理解することは、弱さの証明ではなく、逆に脳が困難に立ち向かい、再び前進する「くじけない脳」を育むための重要な一歩となります。
【参考文献】
・Jia, T. et al. Neural network involving medial orbitofrontal cortex and dorsal periaqueductal gray regulation in human alcohol abuse. Sci. Adv., 7, eabd4074 (2021)
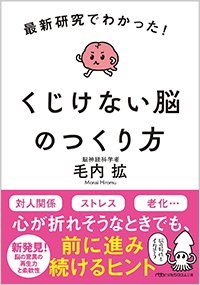 『最新研究でわかった! くじけない脳のつくり方』(毛内拡、日経ビジネス人文庫)
『最新研究でわかった! くじけない脳のつくり方』(毛内拡、日経ビジネス人文庫)







