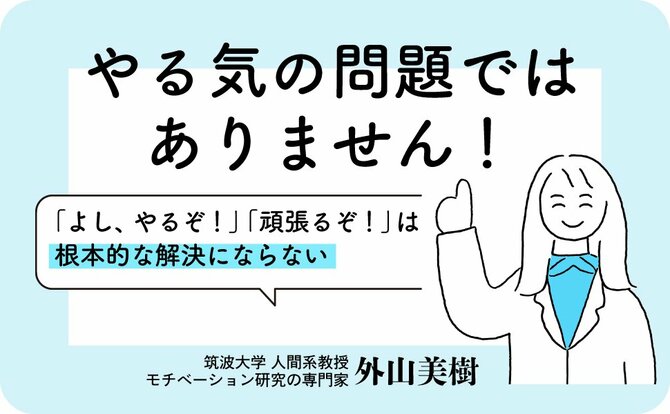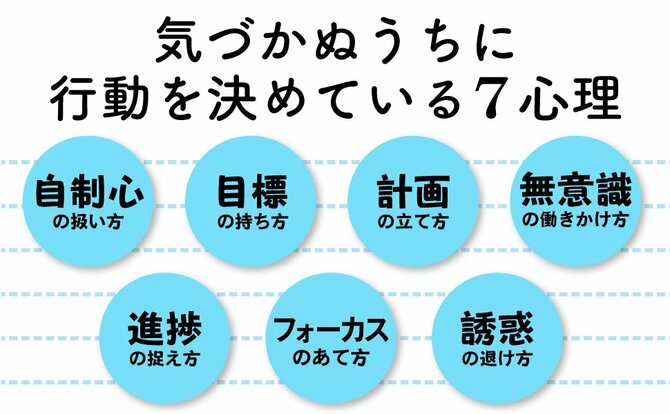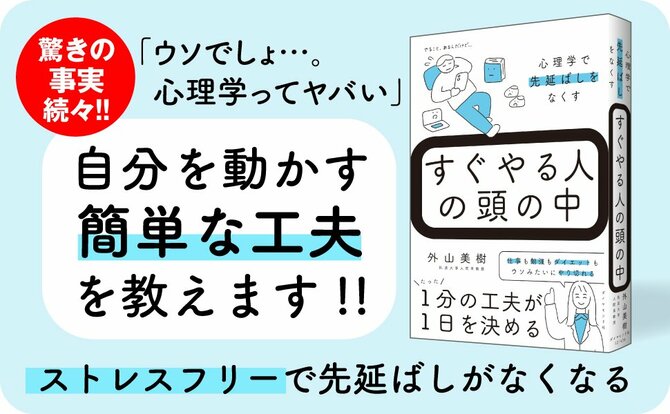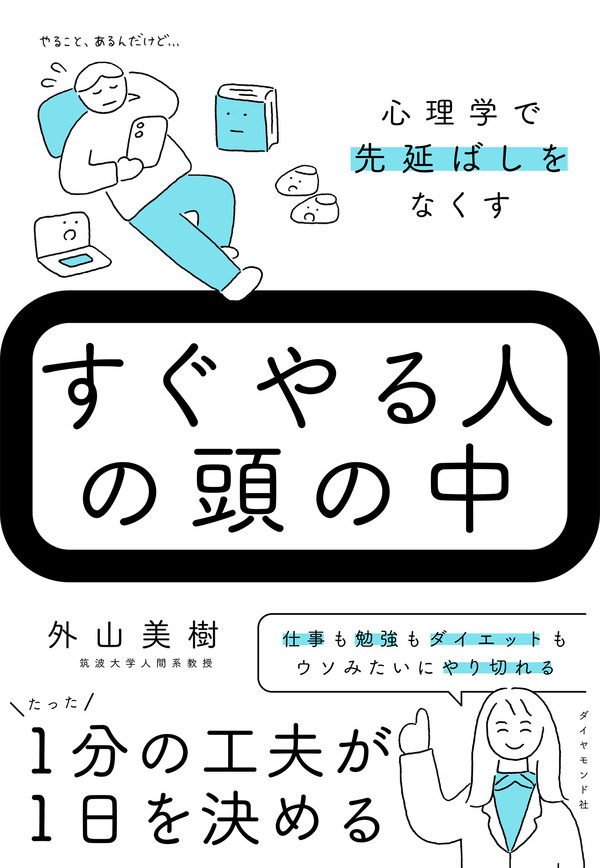新年や新学期、月の変わり目などのタイミングで、人は何かと目標を立てがちだ。しかし、その目標を毎回必ず達成できる人は少ないのではないだろうか。ダイエットにしろ、英語の勉強にしろ続かず、「なんて自分はダメな人間なんだ」と自分を責めてしまう人もいるだろう。しかし、モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏は「やるべきことを達成するための効果的な目標の立て方がある」と語る。本記事では外山氏の著書『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』をもとに、モチベーションが高まる目標の立て方を解説する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
目標の立て方次第で変わるモチベーション
目標を立てて達成できる人もいれば、どんな目標も三日坊主で終わってしまう人もいる。
筆者は後者で、ほとんど続かないことが多い。
であれば、いっそ目標など立てない方がいいのではないかとも思ってしまう。
しかし、外山氏は目標に関して次のように語る。
「人は絶えず目標を設定し、その目標に到達しようと試みる。人の勉強や仕事に対するモチベーションおよびそれらへの行動の違いは、目標の違いに由来する」
あまりモチベーションが湧かなくても、何らかの目標が設定されていれば、何とかその目標に到達しようと取り組むのが人間だというのです。(中略)
目標の立て方次第で、モチベーションは大きく変わるのです。(P.67)
ただし、外山氏は「目標を持つだけではうまくいかない」と指摘する。
当然だ。目標を持つだけでうまくいくなら筆者はとっくの昔に10キロのダイエットに成功して、英語も話せるようになっているはずなのだから。
いったいどのような立て方をすればモチベーションを高められるのだろうか。
目標が行動や努力の度合いを決める
具体的な目標の立て方の前に、そもそもなぜ目標を設定することが重要なのかを押さえておきたい。
外山氏は次のように語る。
そして、目標は目指すべき方向性を明確にするだけでなく、目標を達成するのに必要な努力の程度を調整することにもつながります。(P.69)
では、「努力の調整」とは具体的にどういうことだろうか。
その結果、目標が達成された時には、達成感や喜びを感じ、さらなる目標達成に向けて動き出すことになります。(P.69-70)
さらに外山氏は「目標を設定することで、行動の方向性が定まり、努力の調整がしやすくなり、継続もしやすくなります」と説明する。
こうした積み重ねが、最終的には成績や業績の向上につながるのだ。
では、どのような目標を立てることで、私たちはモチベーションを高めることができるのだろうか。
あいまいな目標では続かない
外山氏が推奨する目標の立て方は次のとおりだ。
第一に、具体的で明確な目標を立てることだ。
「たくさん勉強する」といったあいまいな目標ではなく、「毎日1時間勉強する」の方が有効であるというものだ。
「たくさん勉強する」というのは、明確な目標が定められていないために、「たくさん」からはほど遠い結果しか生み出しません。
また、あいまいな目標だと、それが達成できたのかどうかもわからないままです。(P.70-71)
だから、「毎日1時間勉強する」といった具体的で明確な目標の設定が重要になるのだ。
具体的で明確な目標を設定することは、目標に注意を集中させ、目標達成へのモチベーションを高めることになる。
また、具体的に目標を設定することで、その目標が達成されたのか、そうでないのかが一目瞭然になるというメリットもある。
簡単すぎず、難しすぎない目標を立てる
先ほどの「より具体的に目標を決めよう」という話は、一般的にもよく言われることなので、聞いたことがある人も多いのではないだろうか。
もう一つ、外山氏がすすめる目標がなかなか面白い。
それは、「自分の能力に合ったレベルで挑戦できる目標にする」というものだ。具体的に言うと「成功の確率が50%と感じるくらいの難易度」がいいという。
人は、主観的な成功確率が低い行動に対するやる気は低く、成功確率が高まるにつれてやる気も高まる。
しかし、「そのピークは成功確率が50%の行動であり、それ以上に成功率が高まると(課題が簡単になると)やる気は低下する」と外山氏は指摘する。
そこでポイントになるのが、「難しいが、可能な目標」を立てるということだ。
つまり、目標達成の確率を上げるには、今の自分には少し難しいかなと思う目標を、できるだけ具体的に立てるといいということだ。
プライベートな目標も、具体化して達成する
よく考えてみると、筆者は仕事の進捗管理に関しては具体的に「いつ、なにを、どこまで進めるか」を洗い出して、スケジュールに落とし込んでいる。
そこまでしてようやく、仕事の運用ができているのだから、個人的な目標も本来はそこまで具体化しなければ人はなかなか動かないのだろう。
漠然と「10キロ痩せるぞ!」と思っていても、その方法が決まっていなければ行動しようがない。道理で痩せないはずである。
本書によると、目標達成には他にもさまざまな目標達成のコツがあるようだが、まずは自分の目標が具体的なものになっているか、難易度が高すぎたり低すぎたりしていないかを確認したいものだ。
みなさんも、自分が長年抱えている目標や夢があれば、まずは具体的な行動に落とし込んでみてはいかがだろうか。