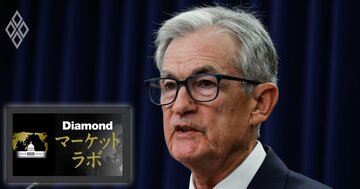Photo:Bloomberg/gettyimages
Photo:Bloomberg/gettyimages
米連邦準備制度理事会(FRB)は9月、雇用市場の停滞を打開するため、利下げを再開した。ただ、少なくとも短期的には、雇用低迷は利下げだけでは解決できない。
利下げは需要を押し上げることで景気を支え、特に住宅など金利の動きに敏感な取引に影響を及ぼす。だが多くの企業は需要ではなく、高コストや関税、信用収縮までさまざまなことが問題になっていると述べている。利下げは通常、経済を後押しする手段である株価上昇や住宅ローン金利低下につながるが、それもあまり期待できない状況にある。
ジェローム・パウエルFRB議長は、労働市場が「やや奇妙な均衡状態」にあると指摘している。レイオフは極めて低水準にとどまっており、この背景には企業の売り上げが持ちこたえていることがあるとみられる。一方で採用も極めて低水準にあり、結果として雇用の伸びはかろうじてプラスにとどまっている。
米デューク大学がアトランタ連銀、リッチモンド連銀と共に24日発表した四半期調査によれば、523社のうち約20%は、関税を理由に採用を減らしていると回答した。多くの企業は欠員補充を行わず、一部は従業員をレイオフしているとも述べた。調査は各企業の最高財務責任者(CFO)を対象に実施された。
こうした状況は、あらゆる規模の企業に及んでいる。米コーヒーチェーン大手 スターバックス は先週、人件費とコーヒー価格の上昇、既存店売上高の低迷を受けて、900人の人員削減を発表した。
関税などのコストに対処する選択肢が少ない中小企業は、特に採用に慎重になっている。企業への助言サービスなどを行うビステージ・ワールドワイドが最近調査した中小企業658社のうち、今後12カ月で従業員数を増やす見通しと回答したのは、半数強にとどまった。4月からは上昇したが、昨年12月の71%を下回る。