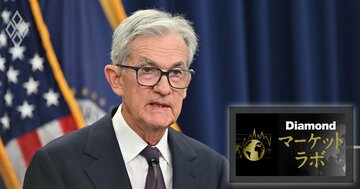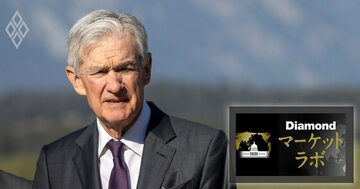FOMCの記者会見に臨むFRBのパウエル議長=9月17日 Photo:Anadolu/gettyimages
FOMCの記者会見に臨むFRBのパウエル議長=9月17日 Photo:Anadolu/gettyimages
9月FOMC予想通りの利下げ再開だが
名目は雇用悪化への「予防的緩和」
FRB(米連邦準備制度理事会)は、9月16~17日に開いたFOMC(米連邦公開市場委員会)で、政策金利(FF〈フェデラルファンド金利〉レートの誘導目標)を4~4.25%へと従来に比べて0.25%ポイント引き下げることを決めた。
利下げは昨年12月以来、6会合ぶりだ。トランプ大統領が再三にわたり圧力をかけてきた中で、トランプ政権になって初めての利下げになる。
利下げ再開は金融市場の事前予想に沿った結果だったが、ウォラー理事やバウマン理事が前回(7月)会合で利下げをすでに主張し、FRB内の意見が分かれていたことを考えると、今回は結果的に0.5%ポイントの利下げを主張したのは、トランプ大統領が新たに指名したブレーンであり、経済諮問委員会委員長も兼ねるミラン理事1人にとどまった。
その点では、パウエル議長によるコンセンサス形成が成功したと評価することができる。
だがそれでも、今回の利下げのロジックには分かりにくい点がある。
FRBの声明文やパウエル議長のFOMC後の会見では、非農業部門の雇用者数の増加ペースの急速な鈍化などで、「雇用の下方リスク」が高まったことを利下げ再開の理由としている。
しかし同時に公表されたFOMCメンバーの2025~27年の見通しでは、実質経済成長率は前回(6月)から上方修正され、経済は「堅調」との認識だ。消費者物価も26年は上方修正され、パウエル議長も会見でインフレ率が高止まりする懸念に触れている。
いわば雇用悪化のリスクに対応する「予防的緩和」の色合いが濃いが、トランプ大統領による露骨なFRB人事への介入など政権の利下げ圧力が目立っている中では、この利下げロジックは、トランプ政権に対してFRBが“暗黙の忖度(そんたく)”をしているとの疑念を抱かせる懸念がある。
FOMCメンバーの想定では、年内にあと2回、さらに来年に入り1回の利下げ継続がメインシナリオだが、市場の疑念を払拭するためには利下げロジックの修正を考えるべきだろう。