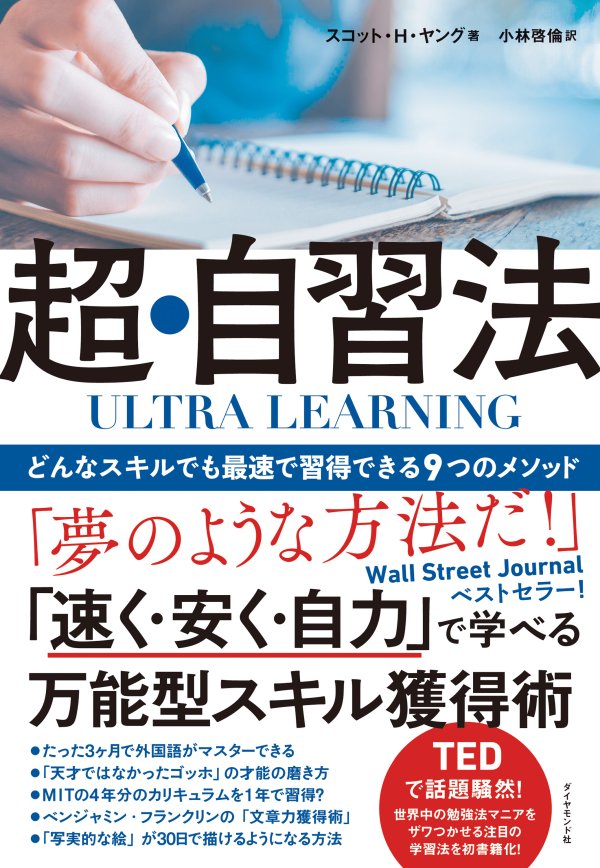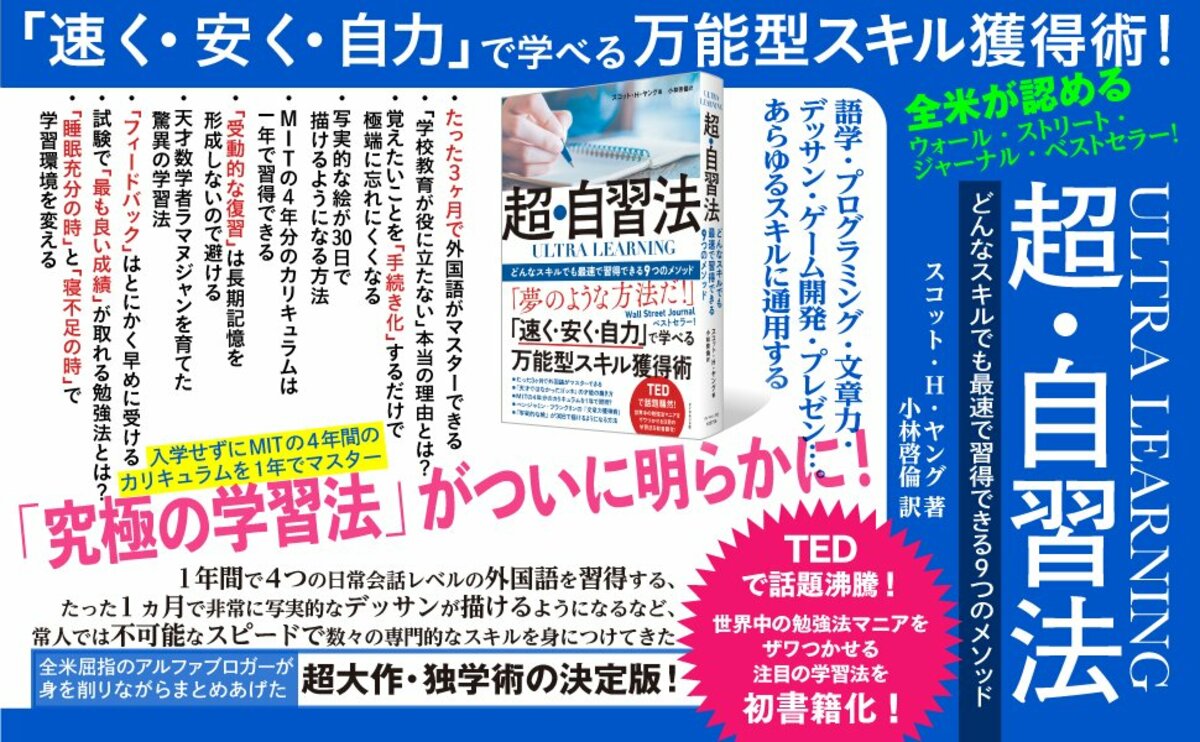新しいスキルを学ぶとき、教材が簡単すぎると退屈になり、難しすぎると挫折してしまう。効率よく成長するには「ちょうどよい難易度」を見つけることが不可欠だ。『ULTRALEARNING 超・自習法』では、この難易度調整を「フィードバックの戦略」と捉えて解説している。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。(構成:ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
自分に合った難易度で学んでいるか?
多くの人が学習でつまずく原因のひとつは、教材の難易度が自分のレベルに合っていないことだ。
「勉強を頑張っているのに成果が出ない人」は、教材選びを間違っていることが多い。
簡単すぎれば退屈で集中できないし、難しすぎれば挫折してしまう。学びの停滞は、この「難しさのズレ」から生まれることが多い。
本書では、効果的な学習には「挑戦的だが達成可能な課題」を設定することが大切だと説いている。
これは心理学で「フロー理論」と呼ばれる考え方にも通じる。フロー状態とは、ゲームに夢中になって気がつけば何時間も経っているような没頭状態のことだ。
フィードバックには、シグナル(活用できる有益な情報)とノイズが存在する。ノイズはランダムな要因によって発生するため、過剰に反応しないようにする必要がある。たとえば文章力を向上させるために、記事を書いてオンライン上で公開しているとしよう。その大部分は注目されず、また注目されたとしても、自分ではコントロールできないことが原因である場合がほとんどだ。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)
「少し難しい」ことに挑むとき、人は最も集中し、記憶や理解が定着しやすい。
簡単すぎたり、難しすぎたりすると、そのゾーンに入ることができない。学びの成果を最大化するには、自分にとって適切な「ちょうどいい難しさ」を意識する必要があるのだ。
教材の難しさを調整しよう
本書がユニークなのは、この難易度調整を「フィードバック」の一部として位置づけている点だ。
つまり、ただ問題を解いて結果を見るのではなく、課題のレベルを調整すること自体が「学びを修正するための情報」になるという考え方である。
たとえば、英語を学ぶ際に「ネイティブ同士の専門的な議論」をいきなり理解しようとすれば難しすぎて心が折れる。
しかし「子ども向けアニメ」だけを見続けていても進歩は遅い。必要なのは、自分が少し背伸びすれば届くレベルを選ぶことだ。
メタフィードバックを活用するもう1つの方法は、異なる学習法を比較してどちらが効果的かを確認するというものだ。MITチャレンジの間、私はよく試験を受ける前に、問題をいくつかのトピックに分け、異なるアプローチを並行して試すということをしていた。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)
学習の成果は、取り組む課題の設定によって大きく左右される。だからこそ、「教材の難しさを調整すること」自体が学習戦略になるという視点を持つと、独学はぐっと進めやすくなるだろう。
「自分に合った難しさ」の見つけ方
では実際に、どうすれば「ちょうどいい難しさ」を見つけられるのだろうか。本書が提案する方法は、まず小さく試してみることだ。
いきなり大きな目標を掲げるのではなく、現在のレベルに少しだけ上乗せした課題を設定し、結果を観察する。このプロセスを繰り返すことで、自分にとって最適な負荷を知ることができる。
たとえばプログラミング学習なら、基礎文法を覚えた後に「簡単な電卓アプリ」をつくってみる。その課題がすんなりできてしまうなら、次は「Webアプリ」でデータを保存する機能を追加する。
もし難しすぎてまったく前に進めないなら、もう少しシンプルな課題に戻る。この「少し背伸び」を繰り返す階段づくりこそ、学びの持続力を高める工夫である。
重要なのは、挫折の兆しを「自分に合わない教材のサイン」ととらえることだ。
やる気がなくなったから自分に向いていないのではなく、負荷のかけ方を間違えただけかもしれない。難易度を柔軟に調整すれば、学び続けるエネルギーを維持できるのである。
キャリア成長に効く「ちょうどよさ」
この難易度調整の発想は、単なる学習だけでなく、ビジネスやキャリアにも直結する。
社会人が「学び直し」をしようとすると、専門書の分厚さに怖気づいたり、逆に入門書ばかり繰り返して前に進まなかったりすることがあるだろう。
そこで役立つのが「今の自分にとって少しだけ難しい教材を選ぶ」という考え方だ。
たとえば仕事でプレゼン力を伸ばしたいなら、まず社内での小規模な発表を繰り返す。そのレベルに慣れてきたら、社外のセミナーに挑戦する。
いきなり大舞台に立てば緊張で固まるかもしれないが、小さなステップアップを重ねれば、自然とスキルは積み上がっていく。
キャリアにおいても「負荷の調整」は成長のカギである。
業務の中で少し背伸びする案件を引き受けたり、新しいツールを試してみたりすることは、学習と同じように適度な難易度の挑戦になる。
こうした実践を意識的に取り入れることで、独学や学び直しが確実に成果へとつながるだろう。
難しさのバランスをとる学習法は「筋トレのウェイトの重さを調整する」のに似ている。軽すぎれば効果がなく、重すぎればケガをする。
「ちょうどよい負荷」が筋肉をつけるのに最適であるように、知識やスキルも「ちょうどよい挑戦」で鍛えられるのだ。