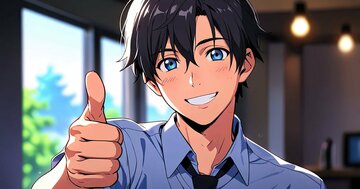勝率52%を“月次9割勝利”に変えるプロの統計学的アプローチとは?
ベストセラーとなっている『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』の著者・kenmoさんと、新刊『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略」』の著者・宇根尚秀さんによる特別対談をお送りする。新NISA(少額投資非課税制度)で、大人気の「オルカン(eMAXIS Slim全世界株式<オール・カントリー>)」や「S&P500(米国株式)」に連動する投資信託を始めた多くの個人投資家に、次の一手となる個別株投資を指南。個人投資家とファンドマネージャーによる「ここでしか語れない話」を繰り広げる。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
個人投資家が知るべき
銘柄選定のアプローチ
kenmo 宇根さんの著書『最後に勝つ投資術』の中で「トップダウン的アプローチ」と「ボトムアップ的アプローチ」について触れられていますが、まさにその通りだと感じました。
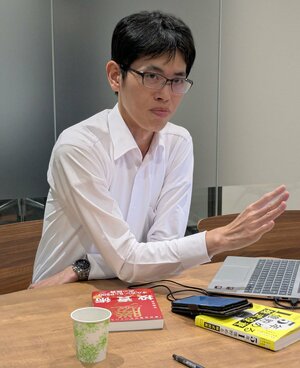 kenmo(湘南投資勉強会)
kenmo(湘南投資勉強会)1982年愛知県生まれ。大阪大学大学院情報科学研究科修了後、東証一部(現・東証プライム)上場のメーカーに研究員として就職。2011年に4年間で貯めた元手300万円から株式投資を始め、追加資金の投入なしに、会社員を続けながらわずか5年で資産1億円を達成。現在は、約3億円を運用している。2018年個人投資家同士の情報交換を目的とした「湘南投資勉強会」を設立。2023年に中小企業診断士の資格を取得。15年間勤めた会社を辞め、IR支援や企業コンサルティングを行うための法人を設立。現在は株式投資のかたわら、講演活動や、数多くの企業のIR説明会を主催している。『ダイヤモンドZAi』『日経マネー』『日経ヴェリタス』『日本経済新聞』などでの記事掲載多数。初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』(ダイヤモンド社)が17万部突破のベストセラーとなり話題に。X:kenmo@湘南投資勉強会3.1万フォロワーYouTube:湘南投資勉強会オンライン チャンネル登録者数1.85万人
私自身も両方のアプローチを試みていますが、宇根さん個人としては、どちらのアプローチがご自身に合っている、あるいは得意とされていますか? 個人投資家の方々も、銘柄の選び方という点に非常に関心があると思います。
結論は「両輪」
仮説検証のプロセスが肝
宇根尚秀(以下、宇根) 結果的には、トップダウンとボトムアップの両方を行っている、というのが答えになります。まず何らかの投資仮説を立て、それを検証するために発行体企業に直接話を聞きに行ったり、ネット情報などのデスクトップリサーチで深く掘り下げたりします。
投資仮説の立て方には様々な方法があります。私の著書にも書いたとおり、バリュー(割安性)・クオリティ(質)・モメンタム(勢い)といった条件でスクリーニングを行い、数十銘柄の候補を選ぶのが、安定的で始めやすいやり方でしょう。
多数の戦略で勝率を高める
統計学的アプローチ
宇根 ただし、知っていただきたいのは、例えばバリュー株投資やクオリティ株投資といった単一の投資スタイルだけに賭けていても、安定的に儲かるわけではないということです。
そこで私たちは、そういった投資戦術を10、20、30と数多く用意し、それらを組み合わせることでポートフォリオ(資産構成割合)全体で少しずつ利益を積み上げていく、という手法をとっています。
少し専門的になりますが、これは統計学に基づいた考え方です。例えば、一つ一つの勝率が52%の投資アイデアでも、それを400銘柄ほどポートフォリオに組み込むと、統計的にポートフォリオ全体での日々の勝率は約65%にまで高まります。日次で65%勝てると、月次のリターンでは9割以上の確率でプラスになる計算です。理論上は95%以上になりますが、実際はそこまでうまくいきません。
このように、私たちは統計学的な考え方に基づき、多様な戦略を分散させることで、安定的なリターンを目指しているのです。
【仮説事例1】
受注残と業績の「ズレ」に注目する
宇根 では、具体的な仮説はどのように立てるのか。ちょっと深掘りしてみましょう。
一例を挙げます。ある大手の消防車メーカーがありました。その会社はしばらく業績が悪かった。なぜなら、彼らは日野自動車のようなトラックメーカーから車体を仕入れて改造・販売するビジネスモデルなのですが、ご存じの通り、日野自動車が認証不正問題や半導体不足で、トラックの供給能力に制約を抱えていました。そのため、消防車を作りたくても作れず、売り上げも上がらなかったのです。
一方で、防災意識の高まりなどから消防車の需要はコンスタントにあり、受注はものすごく積み上がっていました。そして今年から供給が正常化し、溜まっていた受注分を生産・納品できるフェーズに入ったとします。そうなれば、当然ながら業績は上がりますよね。
受注残は、前受金などの形で財務諸表に少しずつ表れますが、まだ利益としては計上されていません。よく見ている投資家が気づけば株価は上がるはずですが、まだ市場がそれに気づかず、PBR(株価純資産倍率)が1倍を割っているような割安な状況は往々にして存在します。