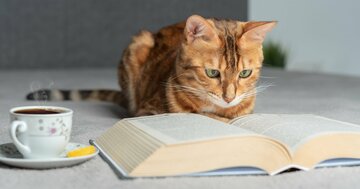ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されている。2025年のノーベル生理学・医学賞は、「制御性T細胞による免疫の過剰な働きを抑える仕組みの発見」に対して、大阪大学の坂口志文博士らに贈られた。この研究成果はどこが優れているのか、著者が緊急寄稿した。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
制御性T細胞の発見
2025年のノーベル生理学・医学賞は、「制御性T細胞による免疫の過剰な働きを抑える仕組みの発見」に対して、大阪大学の坂口志文博士、米国のバイオ企業ソノマ・バイオセラピューティクス社のフレッド・ラムズデル博士、米国システム生物学研究所のメアリー・E・ブランコウ博士の3人に贈られた。
免疫は、病原体などから私たちの体を守る大切な仕組みである。そのため、免疫の作用を強めることが医学の重要な課題とされてきた。ワクチンの開発は、その素晴らしい成果の一つといえる。
しかし、その一方で、免疫の作用は強ければ強いほどよい、というものではないこともわかってきた。免疫力の不足ではなく、免疫が過剰に反応することによって起きる病気も、かなりあるのだ。関節リウマチや一部の糖尿病などはその例で、免疫システムが私たち自身の細胞や組織を攻撃することによって発症するのである。
免疫とはどのような仕組みなのか?
そのため、私たちの体には、免疫の働きを抑える仕組みも存在する。たとえば、免疫システムにおいて重要なT細胞は、心臓の上にある胸腺で、私たち自身の細胞や組織と反応するものが除かれる。そして、私たち自身を攻撃しないものだけが、全身に送り出されていくのである。
しかし、私たち自身の細胞や組織のすべての情報が、胸腺に存在するわけではない。そのため、一部のT細胞は私たち自身を攻撃する可能性を秘めながら、全身へと送り出されてしまう。そこで、体のさまざまな部分でも、私たち自身を攻撃するT細胞を抑える仕組みが必要になる。それが、坂口博士が発見した制御性T細胞である。
あきらめず、根気よく続ける
坂口博士の素晴らしいところは、その業績の重要性もさることながら、免疫の働きを抑える仕組みの研究を途中で辞めずに、根気よく続けてきたことだろう。なぜなら多くの研究者が、この分野の研究には未来がないと見限って、やめていったからだ。
じつは20世紀の後半には、免疫の働きを抑える仕組みについて、活発に研究が行われていた。サプレッサーT細胞という細胞が存在すると仮定され、そのサプレッサーT細胞が免疫反応を適切なときに終了させると予想されていたのである。ところが、その細胞がなかなか見つからないうえに、サプレッサーT細胞についての矛盾点も指摘され、この分野の研究は下火になってしまった。
しかし、サプレッサーT細胞は存在しないとしても、ブレーキとして働く何らかのT細胞(これが後に制御性T細胞と名づけられた)が存在しないと、免疫反応を説明することができない。そう考えて、(本人いわく)細々と研究を続けていったのが坂口博士であった。
2つの発見
そして坂口博士は、1980年代に行った実験から、制御性T細胞の存在を確信した。正常なマウスからある種のT細胞(のグループ)を取り除くと、自己免疫病が発症したのである。自己免疫病というのは、本来は病原体などから自分を守る免疫システムが、自分の細胞や組織を攻撃することによって起きる病気だ。
この実験からは、二つのことがわかる。一つは自己免疫病を起こすT細胞が正常な体にもあるということ。そしてもう一つは、取り除いたT細胞のどれかが自己免疫病を起こすT細胞を抑えているということだ。この、抑える方のT細胞が制御性T細胞であるはずで、その後の研究により、坂口博士はこの制御性T細胞の存在を実証したのである。
偉大な業績の背景にあるもの
免疫は重要だが、強ければ強いほどよいわけではない。ものごとを諦めない意志の強さも重要だが、何の根拠もなく闇雲に突進するだけでは不幸な結末になりかねない。しかし、坂口博士の場合は、制御性T細胞があるはずだという確かなデータがあったうえで、その実証に向けて諦めなかったからこそ、偉大な業績を挙げることができたのだろう。先見性があったからこそ、逆風のなかでも研究を続けることができたのだと思う。心からお祝い申し上げたい。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』に関連した書き下ろしです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。