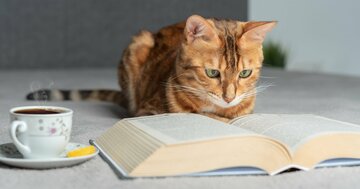ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
「絶滅」と進化の関係
ダーウィンは、自然淘汰が働きやすい条件をまとめている。
その一つ目は、個体数が多い(集団が大きい)ことだ。有益な変異が生じることはまれである。
しかし、個体数が多ければ、そのどれかの個体に有益な変異が生じる確率は高くなる。したがって、その集団に有益な変異が起きる確率は高くなるのである。
「農薬が効かない昆虫」のしくみ
自然淘汰が働きやすい条件の二つ目は、限定された交雑だ。逆に言えば、自由な交雑は自然淘汰の効果を弱めるのである。
これについては、有名な例が知られている。
畑で同じ農薬を何年も使っていると、その農薬が効かない昆虫(抵抗性の昆虫)が現れて、大きな被害をもたらすことがある。それを避けるために、農薬を使わない畑を少し残しておく戦略を取る農家もある。
農薬を使っている畑では、農薬が効く昆虫(感受性の昆虫)より、抵抗性の昆虫の方が有利である。一方、農薬を使っていない畑では、抵抗性の昆虫より、感受性の昆虫の方が有利である。
農薬を使っていないのだから、抵抗性の昆虫も感受性の昆虫も生きていけるし、どちらが有利とか不利とかいうことはなさそうだけれど、じつはそうではないのだ。
抵抗性の昆虫は、農薬に抵抗するための余分な仕組みを持っているので、かならずその他のどこかが犠牲になっている(たとえば、感受性の昆虫より飛ぶのが遅いとか)。
そのため、農薬を使っていない畑では、感受性の昆虫の方が有利なのである。
あえて農薬を使わない畑を残す
昆虫は空を飛んで、農薬を使っている畑と使っていない畑のあいだを行き来する。その結果、感受性の昆虫と抵抗性の昆虫が自由に交雑して、どちらの畑にも両方の昆虫がいるようになる。
そのため、農薬を使わない畑を残しておくことで、抵抗性の昆虫の数を低いレベルに抑えることができるのだ。この戦略は、自由な交雑によって(抵抗性の昆虫、あるいは感受性の昆虫を増やそうとする)自然淘汰の効果を弱めた例と言えるだろう。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を抜粋、編集したものです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。