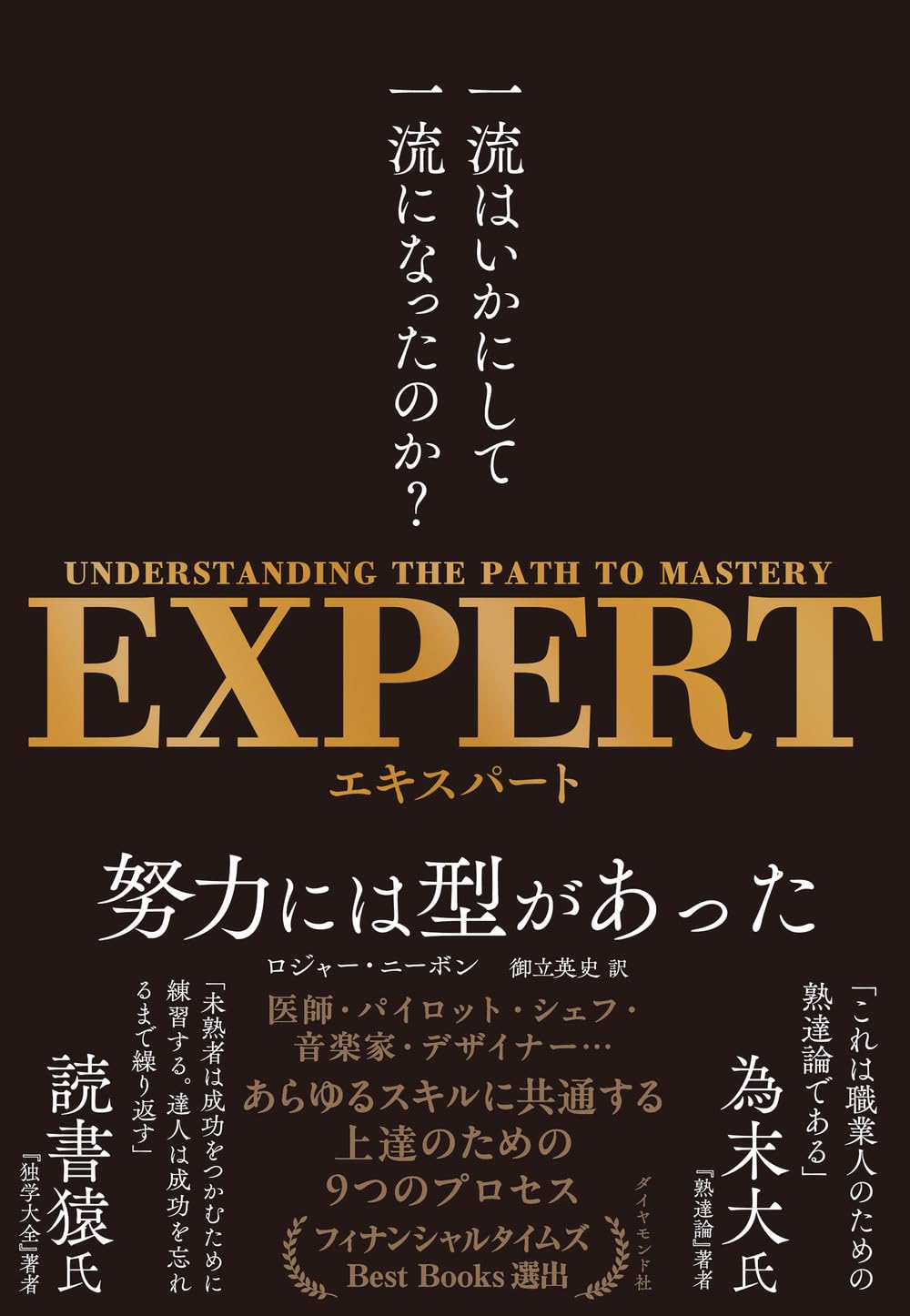『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回はなぜか上手くいく人の考え方について『EXPERT』の本文から抜粋・一部変更してお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
なぜか上手くいく人の思考法
ドレイファス兄弟─数学者のスチュアートと哲学者のヒューバート─は、成人がスキルを習得する過程をモデル化したことで知られている。二人は1986年に出版した『純粋人工知能批判』〔邦訳・アスキー出版局〕という本で、そのモデルを発表した。
それによると、スキル習得の過程には初心者、中級初心者、有能、熟練、熟達の五段階があるとされる。最終段階の熟達について、彼らはこう述べている。「物事が普通に進行しているとき、達人は問題解決も意思決定も行わない。ただ、いつもうまくいっていることをするだけだ」
10年後、医学教育に関して共同研究を行ったH・G・シュミット、G・R・ノーマン、H・P・ボシュイゼンの三人はこう論じている。「思考には分離可能な二つのレベルがある。すなわち、多くの問題に迅速に対応できる非分析的思考と、少数の難解な問題をゆっくり取り扱う分析的思考である。どちらかがすぐれているというわけではなく、どちらも問題を解決する可能性がある」
ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは、2001年に出版した『ファスト&スロー』〔邦訳・ハヤカワ文庫NF〕で同様の考えを述べ、「システム1」、「システム2」と命名した思考方法を説明している。「システム1は、努力も意識もしなくても自動的かつ迅速に働く思考で、システム2は、努力と注意力が必要な負荷の高い認知活動において働く思考である」
私はかつて、患者の治療経過を上級専門医に報告するとき、彼らが思考モードを切り替えながら推論していることに気づいた。情報を順序立てて確認し、見落としがないかチェックすることもあったが、多くの場合、そういう考え方はしていなかった。
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)