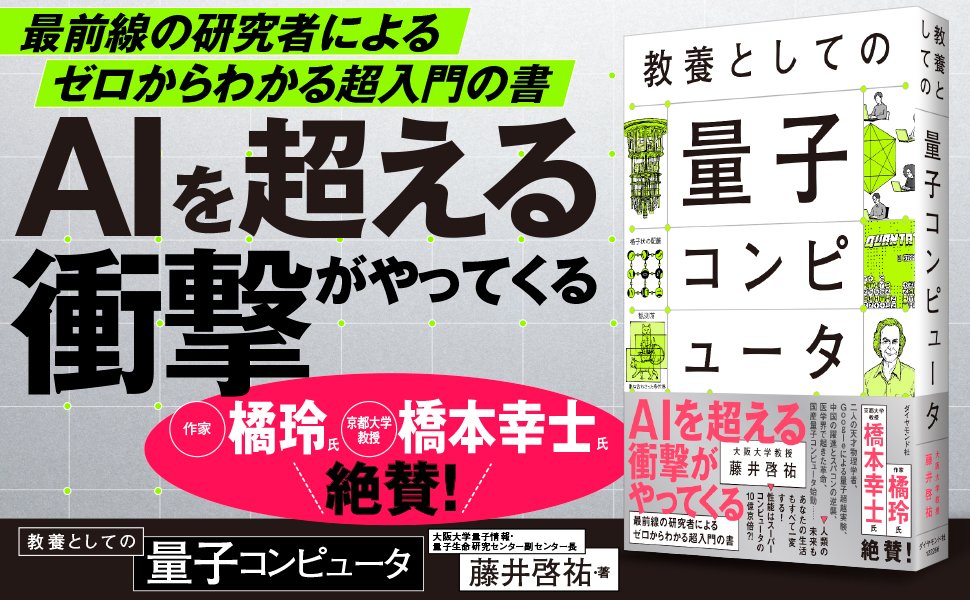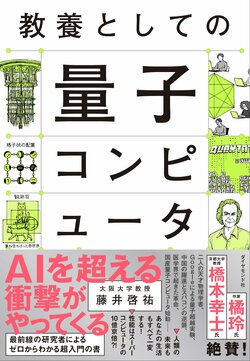量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。
そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。
近日発売の『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回はアインシュタインと量子力学についてを抜粋してお届けする。
 Photo: PhotoSpirit/Adobe Stock
Photo: PhotoSpirit/Adobe Stock
アインシュタイン VS. ボーア
量子力学が発表された当初は、量子論の創造者であるボーアとアインシュタインが量子力学の解釈において論争を繰り広げていた。
アインシュタインは、
「完全な物理学の理論とは、すべての物理量に対して『実在の要素』が備わっている。
私たちが観測しようとしまいと物理量の値はその実在の要素を知ることができれば予測できる」
と主張した。
観測をしたときにはじめて物理量の値がランダムに定まるのはおかしいと量子力学の解釈に異を唱えたのだ。アインシュタインの「神はサイコロを振らない」という言葉はあまりに有名である。
不思議な「量子もつれ」とは?
アインシュタインが量子力学の欠陥として持ち出したものが「量子もつれ」だ。
量子もつれとは、二つの異なる粒子がまるで双子のように連動し、まったく同じように振る舞う状態である。
一方が上に動いていれば他方も上に、一方が回っていれば他方も回るといった感じだ。
どれほど二つの粒子が離れていても、そのような連動が実現される(ただし、実際には遠く離れた地点で量子もつれを共有することは技術的には簡単ではない)。
アインシュタインが指摘した「欠陥」
もし、東京と大阪で量子もつれにある二つの粒子をそれぞれ同時に観測するとどうなるだろうか?
量子力学では観測するまで位置や運動量といった物理量は定まらない。
しかし、量子もつれによると、東京と大阪で同じ物理量を測った場合には、観測結果は必ず一致しなければならない。
両者で同時に観測するので、一方の物理量の結果を知ってから他方にメッセージを送り、辻褄合わせをすることはできないようになっている。
このことは、局所性と実在性という古典物理学が持っている、アインシュタインが完全な物理の理論が持つべきだと考えた性質が、量子力学においては満たされていないことを示している。
(本稿は『教養としての量子コンピュータ』から一部抜粋・編集したものです。)