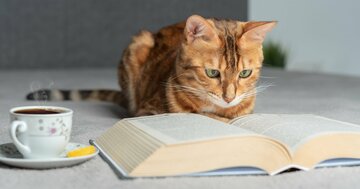ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。本記事では、著者であり、生物学の専門家である更科功氏にインタビューを実施。現代において『種の起源』を読む意味から、更科氏の読書法まで伺った。(取材・構成:小川晶子)。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
「読んだふり」をする理由
――『『種の起源』を読んだふりができる本』というタイトルがすでに面白いと思いました。『種の起源』を「知る」、「読み解く」ではなく「読んだふりができる」としたのはなぜですか?
更科功氏(以下、更科):『種の起源』は、チャールズ・ダーウィンが自らの進化理論を解説した名著です。生物学の「圧倒的に重要な本」なので、現代においてもよく売れているようです。
ただ、最初から最後まで読み通した人は少ないのではないかと思うんです。「不真面目な読者のためのまえがき」に書いたことですが、本国イギリスでも『種の起源』は買っても読まれることのない本として有名であるようです。
日本でもそうでしょう。なぜなら、読み通すにはなかなかの労力が要るんですね。現代の科学からすれば間違っていることもたくさん書いてありますし、同じことが何度も出てきたり一文が長かったりするので、はっきり言って読みにくいのです。
そこで、『種の起源』を読んだときと同じ記憶を頭の中に作ることができるような本を書こうと思いました。このタイトルが吉と出るか凶と出るかわかりませんが、良いほうに転ぶことを願っています(笑)
『種の起源』を読む意味
――現代の私たちが『種の起源』を読む意味はどういうところにあると思われますか?
更科:読まなくても生きてはいけます。でも、読むこと自体が喜びだと思うんです。ちょっと話はズレますが、「生きる意味」っていう表現があるでしょう?
私はヘンな言い方だなと思っているんです。意味を問うということは、生きる以上に大切なことがありそうじゃないですか。でも、生物にとって生きる以上に大切なことはありません。
意味があってもなくても、生きること自体が一番大切です。『種の起源』のような古典を読む意味というのも、それと似たようなことです。読むこと自体が最上の目的で、喜びです。
「人生を豊かにする」と言ったらありきたりかもしれませんが、そういうことです。
『種の起源』が古典となっているのは、生物学がこの本から始まったからです。たとえば目の前にキリンがいて、それを「神様が作ったものだ」と思っていれば、生物というものがよくわからないと思うんですよ。
「進化したのだ」という目で見て初めてわかるんです。ですから「ダーウィンの前に生物学はなかった」と言っていいと思います。
ダーウィンの進化論がわかる、おすすめ本
――『種の起源』と併せて読むべき、おすすめの本は何かありますか?
更科:一番のおすすめは『「種の起源」を読んだふりができる本』ですが(笑)、他にも良い本があるので紹介しましょう。
まず、私の大学院の先輩でもある千葉聡さんが書かれた『ダーウィンの呪い』(講談社現代新書)。それから、東北大学の教授でいらっしゃった河田雅圭さんの『ダーウィンの進化論はどこまで正しいか』(光文社新書)。どちらも新書で読みやすいと思います。
それぞれちょっと見方が違うところがあるので、併せて読むと面白いのではないでしょうか。
著者の読書法
――さきほど「『種の起源』を読んだのと同じ記憶を作る」とおっしゃっていて興味深く感じたのですが、更科先生流の読書法があれば教えてください。
更科:特別な読書術があるわけではないですね。電子は頭に残りにくいので紙の本を、重要な箇所に赤線を引きながら読んでいます。
線を引くのには大変なことがあって、それは「恥ずかしい」ということです。私は電車で本を読むので、赤ペンを持って線を引きながら読んでいる姿を見られるのが、若い時は恥ずかしかったんですよ。
いい大人が何を勉強しているんだろうって思われていないだろうかと……。いまは慣れちゃったので平気ですけど。
――線を引いたあとはどうされるんですか?
更科:それを元に、メモをパソコンで作って検索できるようにしています。どこに何が書いてあるかわかるようにしておくんです。
作家の森鴎外はドイツ語で書かれた本を読んで、要約メモをよく作っていたそうです。私は若い頃、森鴎外が大好きだったので、真似をして全部漢字で日記を書いてみたりなどやっていました。
メモを作るのも森鴎外の影響です。「本は読み直さないと意味がない」と考えているのは一つのポイントかもしれないですね。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』に関連した書き下ろしです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。