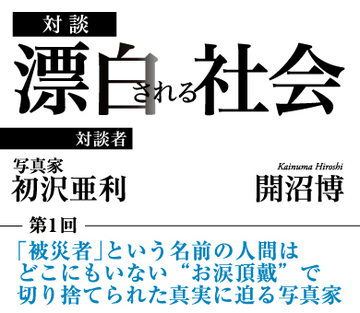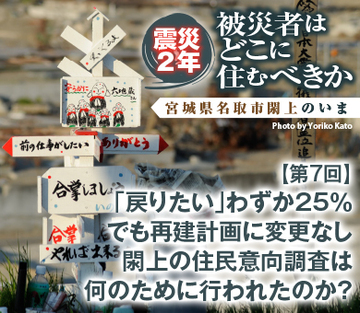「まずは日本人が先だから」――祖国に帰ることも、第二の故郷に戻ることもできない被災したフィリピン人女性の日常から見えてきた「現実」とは。いわきの「昼と夜」に迫った(取材・文・撮影/ジャーナリスト 菅原聖司〈すがはら・せいじ〉)
中傷でも、美談でもなく
「居場所がないの、どこにも。この店にいるフィリピン人は、行く場所がないからここで我慢してるだけ。地震が起きてから、国に戻ることも、町を出ていくこともできないから」
いわき市駅前の繁華街、雑居ビルの2階に佇むフィリピンパブ。ホステスとして働くエステーラさんは、大きな瞳を少し曇らせ、ぽつりとつぶやいた。
「日本にいると、時々自分の人生がわかんなくなることがあるの。やっぱり『普通の人生』がいい。あれから、特にそう思うようになったわね」
 会話中に煙草をくゆらせるエステーラさん
会話中に煙草をくゆらせるエステーラさん
薄暗い店内では、常連客の中年男性がカラオケで演歌を熱唱していた。接客中のホステスたちはマラカスを振ったり、額から光を放つ「ハゲヅラ」をかぶりながら、甲高い声で合いの手を入れていた。
「みんな、こう見えて結構大変なのよ」
ソファーで騒ぐ客から少し離れて、僕たちはカウンターで3時間以上も話し込んでいた。
東日本大震災後、外国人は日本から「脱出した」と非難めいた論調で語られることもあれば、「外国人にもかかわらず」日本に残って復興に尽力しているという美談も伝えられた。
しかし、そうした報道の陰で「被災した外国人の日常」は、ほとんど描かれずじまいだったのではないだろうか。偶然訪れたパブで出会った彼女と話しながら、そんな思いが頭をよぎっていた。