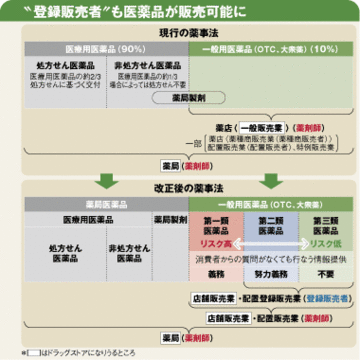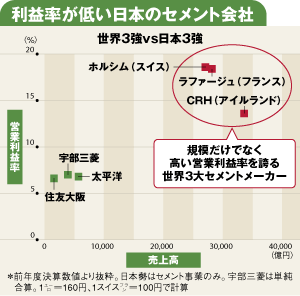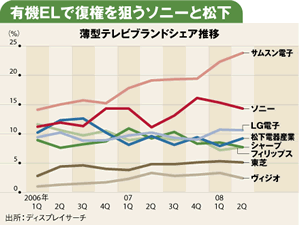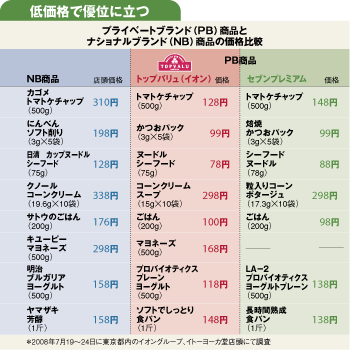医薬品市場の成長が鈍化するなか、近年、30~40%の急成長を続ける抗体医薬。日本で先頭を走ってきた協和発酵工業、キリンファーマが経営統合を決める一方、後れを取ってきた日本の製薬大手4社もアライアンスと買収で体制を整えつつある。がぜん注目度を増してきた、抗体医薬ビジネスのうまみと課題を探った。
「両社の抗体医薬事業を統合し、創薬力を向上させる」――。
2007年10月22日、協和発酵工業がキリンファーマと合併し、キリンホールディングスの傘下に入ることを発表した記者会見の席上、協和発酵の松田譲社長は合併の意義をこう強調した。
「サイズを狙った統合ではない」(松田社長)というように、協和発酵とキリンファーマの医薬品事業は合算しても1987億円(2006年度)と中堅レベル。しかし、世界で過去5年間に4倍を超える規模に成長し、2兆円市場となった“抗体医薬”に限れば、話は別だ。
じつは両社は、抗体医薬の老舗。日本で初めての抗体医薬「アクテムラ」の製品化に成功した中外製薬と合わせて「抗体御三家」と呼ばれ、同分野が最初に注目された1980年代から研究を続けてきた。先頭を走る2社の合併とあって、新会社「協和発酵キリン」は業界の注目の的となったのである。
抗体医薬とは、バイオテクノロジーを用いて生産されるバイオ医薬品の一種である。病原体が体内に入ると、免疫の働きでタンパク質の「抗体」が作られ病気を防ぐが、抗体医薬はこれを医薬品に応用したものだ。ルーツは、100年以上前に北里柴三郎らが開発し、破傷風治療などに使われた“血清療法”にまでさかのぼる。その後、バイオテクノロジーの進化とともに、副作用を抑えたり、効果を高める改良が続けられ、現在は、ある特定の病原体(抗原)だけに結合(抗原抗体反応)する“モノクローナル抗体”を使った抗体医薬が中心になっている。
急成長には訳がある。
80年代から世界の大手製薬会社は、生活習慣病など患者数の多い疾患をターゲットに年間1000億円以上を売り上げる「ブロックバスター」医薬品の開発にしのぎを削ってきた。その結果、脂質異常症(高脂血症)や痛風などの疾患は、クスリでコントロールできる時代を迎えている。