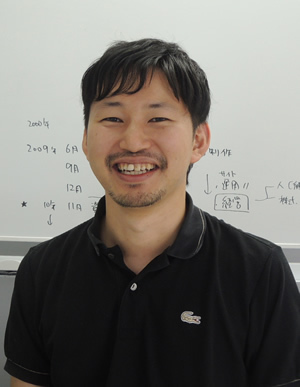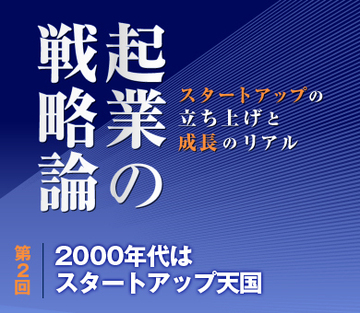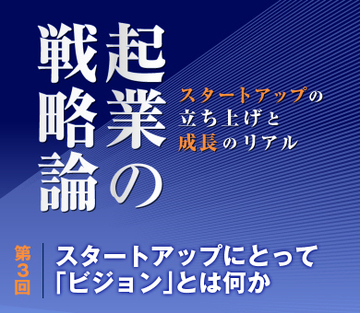小澤隆生・YJキャピタルCOO。nanapiやスターフェスティバルのメンターとして、事業創造に大きな役割を果たした。根っからの”起業家”である Photo by Kazutoshi Sumitomo
小澤隆生・YJキャピタルCOO。nanapiやスターフェスティバルのメンターとして、事業創造に大きな役割を果たした。根っからの”起業家”である Photo by Kazutoshi Sumitomo前回は、個人投資家でありメンターである小澤隆生氏がインキュベートした2社の事例について紹介した。今回は、直接その小澤氏に、事業のつくり方、つくらせ方について、話をうかがった。
小澤氏は、自ら創業したビズシークを楽天に売却し、楽天でオークション事業を担当した後、楽天イーグルスの取締役として球団立ち上げを陣頭指揮。2007年に独立し、個人投資家として活動。共同創業したクロコスが12年にヤフージャパンに買収されたタイミングでヤフーグループ入りし、YJキャピタルCOOに就任。現在は、ショッピングカンパニー担当執行役員、CFO室を兼務する。
何をやるか、どうやるか
HOWがスカスカな事業案が多い
――スタートアップの事業案をみていて、感じることは?
事業を始めるにあたり、何をやるか、どのようにやるかの、両方の課題がある。まず、何をやるかは、普遍的に正しいことでなければダメだ。例えば、砂漠で水は売れるが砂は売れない。WHAT=何をやるかを間違うと全くダメ。
だが、WHAT がいいようにみえても、HOWの中身がスカスカなビジネスプランが多い。例えば、東京で一番おいしいフレンチレストランをつくるというようなもの。それが実現できれば、必ず儲かるというアイデアは、誰でも思いつく。
もし、そのアイデアに投資するなら、三ツ星のレストランで15年間修業したとか、丸ビル1階で5年間格安で使える権利があるとか、フレンチ好きで金持ちの顧客リストを持っているとか、年商2億円の店をつくった実績があるとか、そういった自分がそのアイデアを実現できる理由が必要だ。
HOWの見極めは大変だがとても重要。やり方で成功の確度や利益が変わるからだ。