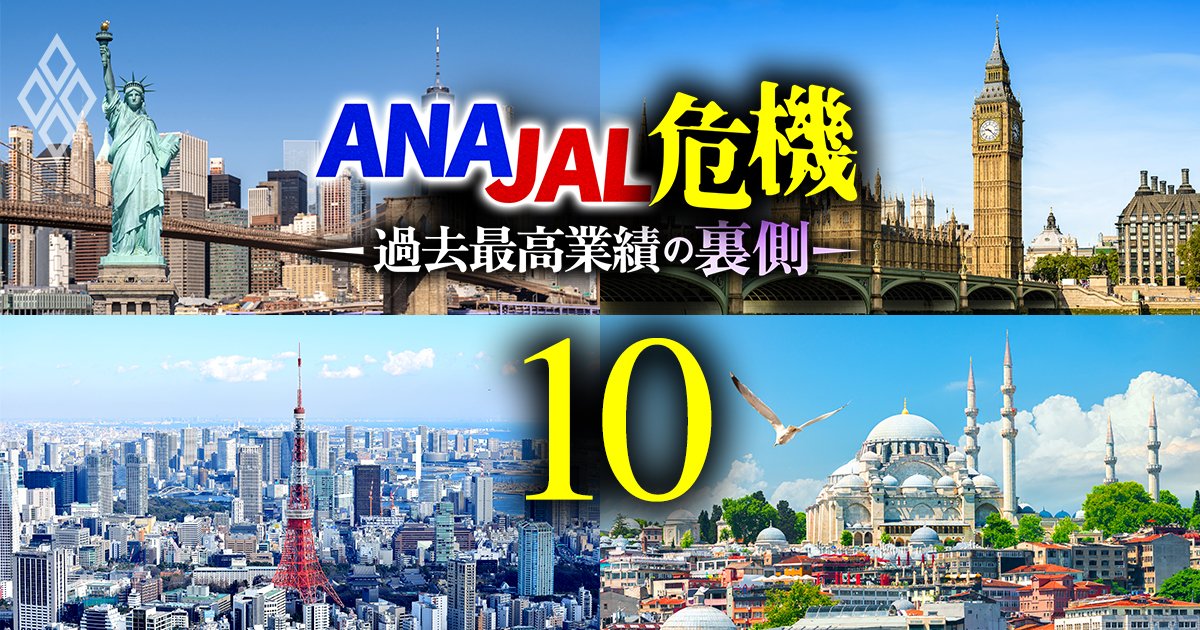 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
移動需要の回復により、世界の空に再び活気が戻っている。だが、その追い風をどれだけ成長につなげられたかは、航空会社によって大きな差がある。為替や収益構造の違いが、業績の明暗をくっきりと分けたのだ。特集『ANA JAL危機 過去最高業績の裏側』の#10では、コロナ前後の世界の航空会社の売上高ランキングを作成。国内2強は順位を下げていることが分かった。(ダイヤモンド編集部 田中唯翔)
エアライン売上高ランキング
ANAとJALは順位を落とす
国際線が好調なのは日本だけではない。移動需要の回復に伴い世界中の航空会社に追い風が吹いている。
国際航空運送協会(IATA)の発表によると、2024年の世界全体の旅客輸送量は47.7億人で、19年の45.6億人をすでに上回っている。25年は49.8億人に達する見込みで、世界の空に再び活気が戻りつつある。
しかし、この追い風をどれだけ自社の成長につなげられたかは、航空会社ごとに明確な差がある。移動需要が戻っても、全ての企業が等しく潤ったわけではない。為替や収益構造の違いが、各社の明暗を分けている。
航空ビジネスは、為替変動の影響を強く受ける産業だ。自国通貨の価値が下がれば、同じ業績でもドル換算では減収になる場合がある。一方で、インバウンドを多く呼び込み、外貨建て収入を多く取り込むことができる収益構造であれば、通貨安の状態でも成長は見込める。むしろ自国の人件費などのコストが下がることで、収益的にはプラスの貢献をする可能性もある。
こうした構造の違いが、世界の航空業界で「勝者と敗者」をくっきりと分け始めている。
24年度と18年度の各社業績を比較すると、米ドル換算の売上高が75%も伸びた企業がある一方で、20%減少した企業も存在した。表面上は同じ“回復”に見えても、実際の成果はまったく異なるのだ。
では、世界的な需要回復の波を最も巧みに乗りこなしているのはどこの会社か。ANAホールディングス(HD)と日本航空(JAL)は、コロナ禍前と比べて順位を落とす結果となったが、一体何位になったのか。







