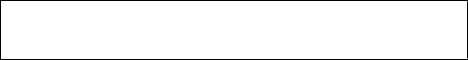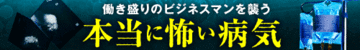先日、米ハーバード大学の研究グループによる調査結果が、がん専門誌(オンライン版)に載った。配偶者の有無によって、死亡率や治療に差が生じるか? という興味深いもの。果たしてその結果は……。
調査は全米がん登録システムのデータベースのデータを用いて行われた。2004~08年の間にがんに罹患した73万4899人について、配偶者の有無と初診時のステージ(病期)、診断後の治療法、そして最終的な死亡率との関連を調べたのである。
対象のがん種は、大腸、乳房、膵臓、前立腺、卵巣、食道の各臓器がんと、肝臓/管内胆管がん、非ホジキンリンパ腫、頭頸部がんなどだった。
その結果、配偶者がいる場合、死別や離婚、別居などで配偶者を失ったがん患者よりも、早期にがんが発見されることが多く、根治的な治療を受けるチャンスが1.53倍高かったのである。
また、仮に進行がんであっても、がんに関連した死亡は、配偶者を持つ人が有意に少なかった。しかも、大腸がん、乳がん、前立腺がん、食道がんおよび頭頸部がんでは、「配偶者」による延命効果が、抗がん剤治療のそれよりも大きかったのである。
ちなみに、調査対象としたすべてのがんで「配偶者効果」は女性よりも男性──夫側で大きかったことも付け加えておく。
研究者は「この調査のハイライトは社会的なサポートが、がんの早期発見、がん治療、そして生存率に大きなインパクトを与える可能性がある点だ」としている。
もちろん、医療制度が異なる米国の結果をそのままうのみにはできない。病院へのアクセスは日本ほど容易ではないし、早期発見しても高額な医療費に治療を断念するケースも少なくはないからだ。それでも、日本の男性の間で増加中の大腸がんや前立腺がん、食道がんで「配偶者効果」が大きい点は無視できない。
ということで、何かと「病院で診てもらったら?」と心配する妻の言葉を軽んじてはいけません。相手はがんにも勝る最強の“ソーシャル・サポーター”なのである。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)