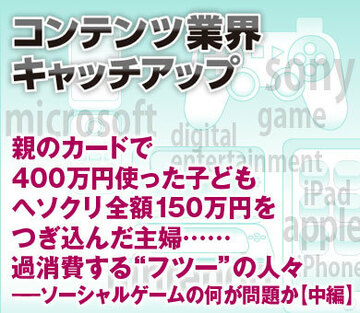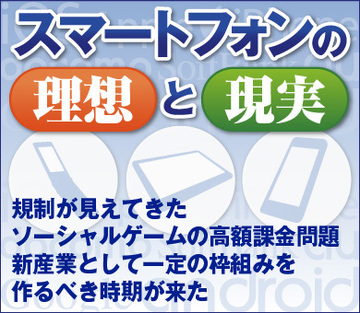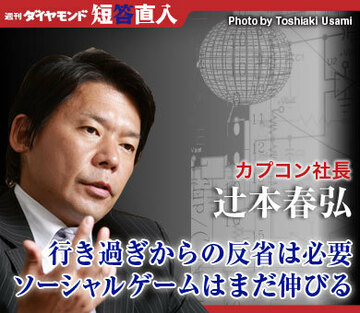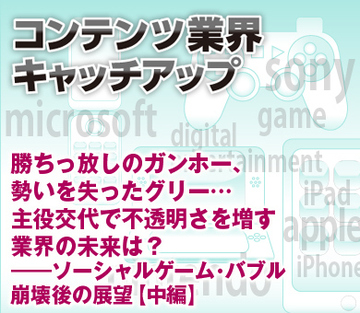基本無料で遊べるがアイテム課金システムが組み込まれたゲームサービスで、企業側が客からのクレームに対して事実上返金に応じるという事態が発生した。原因はアイテム課金システムのひとつ、「ガチャ」と呼ばれる有料くじ引きのシーンで、イラストでは箱の中にあたかも当たりがたくさん入っているかのように描かれていたにもかかわらず、なかなか当たらなかったことがきっかけだったという。こうした基本無料のゲームは、アイテム課金システムに慣れていて高額支払いを厭わないユーザーに支えられていると言われていたが、そうではなかったのだろうか。
安心安全の「ドラクエ」ブランドで
高額ガチャは受け入れがたい!?
問題が発生したゲームは、国民的ゲームとして名高い「ドラゴンクエスト」(スクウェア・エニックス、以下スク・エニ)シリーズのスマートフォン用ゲーム「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」。運営は、スク・エニとサイゲームス(CyGames)の共同によるものだという。
サイゲームスはサイバーエージェントの関連企業で、主要株主としてディー・エヌ・エー(DeNA)が名前を連ねる。主な実績としては、ディー・エヌ・エーが運営している人気ゲームコンテンツ「神撃のバハムート」や、高額課金者が多いことで知られるバンダイナムコゲームスの人気アイドルゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」の開発運営などがある。つまり、サイゲームスはアイテム課金型ゲームビジネス運営では大変実績がある企業だということだ。
今回の問題に関して、家庭用ゲーム系経営幹部は次のように話す。
「やはり、家庭用とソーシャルゲームのお客さんは違うということがはっきりした。ドラクエクラスの有名家庭用ゲームはアイテム課金システムを安易に組み込めませんね。まあ、子どもからお年寄りまで遊べる、安心安全がドラクエの売りですしね。そもそも、日本で一番面白いとされていて、ユーザーをあらゆる意味で裏切らないゲームの代名詞がドラクエです。『ドラクエ』のお客さんは、日本の家庭用ゲームのお客様そのもので、アイテム課金にそもそもなじみがないでしょうし、ドラクエのガチャでアイテム1個に対する課金が5000円越えは許しがたい設定なんでしょうね」
「ただし、今回のようにゴネれば返金(公式サイトでは「プレゼント」とされている)された実績をスク・エニが作った事は、メーカーサイドからするとゆゆしき問題です。他のアプリにも波及しかねない。できれば、ちょっとこれはやめてほしかった。まあ、ドラクエだから仕方がないんだろうけど」