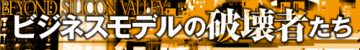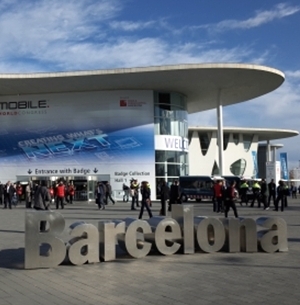スペイン・バルセロナで開催された、世界最大のモバイル分野の展示会「モバイルワールドコングレス」(以下MWC、今年の展示会を指す場合はMWC2014)のレポートを、前回に引き続いてお送りする…といいつつ、すでに東京では桜が散ってしまった。またしても更新が遅れたことをお詫びします。
さて、前回の文末で「MWC2014で日本勢はダメダメだった」と触れた。一方、すでに多くのMWC2014レポートがある中で、日本勢の健闘を伝える記事も少なからず見かける。そうした記事を読みながら、皮肉や反語ではなく純粋に、いろいろな見方ができるものだと思ったし、実際にも日本勢に対する評価は分かれているのが実態なのかもしれない。
今回の日本の端末メーカーや通信事業者の展示について、私なりに結論づけると、「部品や通信インフラのサプライヤーとしては優れている面もあるが、最終製品のメーカーやサービスプロバイダーとしては色あせており、全体的にはポジション不在に逆戻り」というものだ。
ソニーはバルセロナへ何をしに来たのか?
たとえばソニー。昨年はXperiaが世界的にも好調で、日本勢の中でも唯一気を吐くメーカーと目されていたが、今年のMWCでは率直に言って影が薄かった。新製品の発表もなく、ブースの展示も、テーマが定まっておらず混乱した印象を受けた。
まず、大きな通路からブースに入って最初に目にするのは、スマートフォンやタブレットではなく、なぜかBRAVIA。CESではなく「モバイル」ワールドコングレスの会場で4Kテレビのアピールでは、正直「?」という第一印象を拭えない。
 ソニーのCore Photo by Tatsuya Kurosaka
ソニーのCore Photo by Tatsuya Kurosakaめげずに奥へと進むと、ようやくモバイル端末にたどり着く。ただ、整然と並んではいるが、コンセプトがよくわからない並べ方だし、華やかさもない。今年は新製品の発表もないのだから、仕方ないのかもしれないが、その片隅にあるヘッドフォンなどの周辺機器の方が、目立っているくらいである。
そして一番奥にウェアラブルデバイス「Core」があるものの、実際に手で触れてみるには、説明員に声を掛けないと見せてもらえない。そうして実際に触ってみたものの、もはや新鮮さはなく、手触りもガジェットとしてのギミックも、特筆すべきものは見られなかった。
と書いた矢先、ジャーナリストの方から「Xperia Z2等が新製品として発表されていたのでは」とご指摘をいただいた。BRAVIAもその4K出力の演出のため配置されていたという位置づけである。図らずも48時間の強行軍ではMWCを見て回れないことを露呈してしまった格好でお恥ずかしい限り。いずれもご指摘の通りで、お詫びして訂正します。
言い訳がましいが、とはいえ正直、ソニーブースへの印象は大きく変わらなかった。MWC2014で発表されたXperia Z2や同M2の印象は、会場内ではあまり大きいものとは私には思えなかった。BRAVIAも「あれは一体?」という声を、海外の通信事業者やアナリストとの雑談で多く聞いた。また、M2は欧州向けと発表されているものの、日本市場を強く意識しているという同社関係者の声も、事実である。