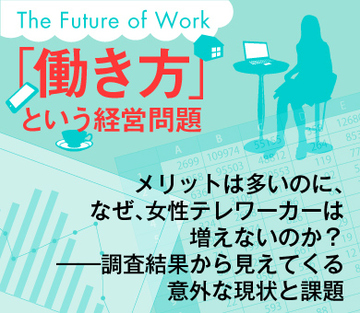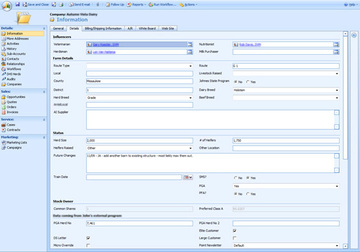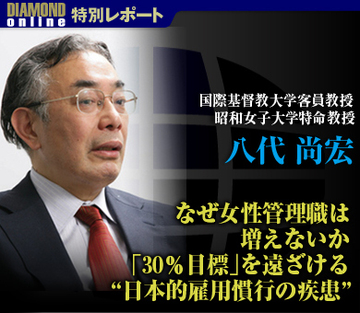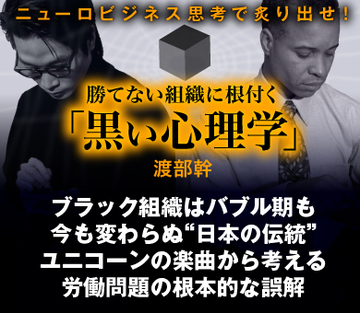企業活動のグローバル化やサービス産業化、ITによるモバイルワーク/テレワークの浸透など、働き方が変わるなかで、企業が自社の職場環境や人事制度はいいのか悪いのか、客観的に知る尺度は存在しなかった。人材コンサルティング企業のエーオンヒューイットはこの問題に着目し、2001年から世界各地で優れた雇用主(企業)を選び出すための調査「ベスト・エンプロイヤー調査」を実施してきた。そして今年、はじめて日本国内の企業に対してもこの調査を実施中である。調査の背景と、これから何がわかるのか、企業経営にとっての示唆はあるのかなどについて、日本法人であるエーオンヒューイットジャパンの楠見スティブン代表取締役社長に聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン編集部 指田昌夫)
職場環境が社員に好まれると
企業の業績が改善する結果に
 エーオンヒューイットジャパンの楠見スティブン代表取締役社長 Photo:DOL
エーオンヒューイットジャパンの楠見スティブン代表取締役社長 Photo:DOL
――まず、この調査を行っている理由についてお聞かせください。
楠見 エーオンヒューイットは、アジア・パシフィック地域では2001年からこの調査を実施しています。そもそも、なぜ始めたかというと、人材を通じて企業の優位性が判断できるのか、データとして明らかにしたいという思いがありました。そして、実際にいいスコアが出ている企業は成功しているのかを知りたかったということが動機です。
調査の結果、ベスト・エンプロイヤー企業と、その業績にはいい相関があることが明らかになってきました。
アジア・パシフィック地域の企業について過去に実施した調査では、ベスト・エンプロイヤーに認定された企業は、他社より40%以上高い利益成長率を達成しています。また離職率は、ベスト・エンプロイヤー企業ではそうでない企業に比べて25%も低いという結果が出ています。さらに、ある部署で人員が不足したときに、それを社内の人材で補える率も、ベスト・エンプロイヤー企業は約40%高くなっています。
――業種別に違いはあるのですか?
楠見 基本的にはあらゆる業種で同じ傾向が出ていますが、たとえばあるホテルでは、もともとスコアが高かったのですが、調査をもとに社員の働きやすさを改善した結果、リピーターの顧客が増えることによってさらに売上が伸びました。
また、サービス業だけでなく、製造業などあらゆる業種で「人」が業績に直結する時代です。たとえば掃除機のメーカーでも、単に製品を売るだけでなく、サービス窓口の印象や対応がその企業の評価を左右します。そしてその好印象は、サービス担当者の職場の環境から育まれるものです。こうした背景もあり、業種を問わずベスト・エンプロイヤー企業の業績にはいい結果が出ていると言えます。