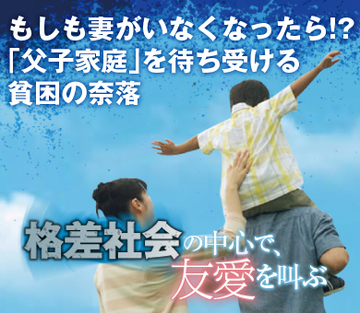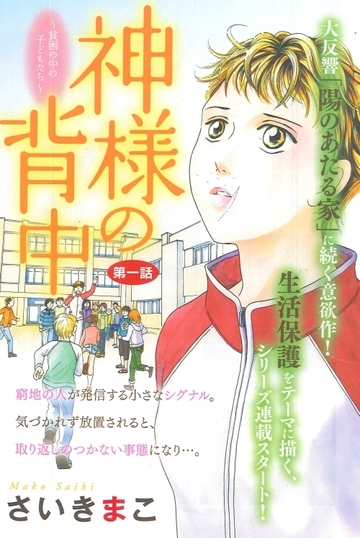2015年2月21日、大阪子どもの貧困アクショングループ(CPAO)が、シングルマザー100人を対象としたインタビュー調査の結果を報告した。シングルマザーたちの多くは、劣悪な家庭環境で暴力を受けて生育し、結婚しても暴力被害から自由になれず、離婚すれば「自己責任で子どもを作ってシングルマザーになった」という非難に囲まれながら、必死で自らと子どもたちを支えている。「子どもの貧困」は、シングルマザーと子どもたちにこそ、最も端的かつ深刻に現れているといえる。
この大きすぎる課題に対して、一市民にできることは何もないのだろうか?
シングルマザーの「しんどい」実態
周りは誰も何もできない?
 シングルマザーの状況について語る、徳丸ゆき子氏。2015年2月21日、報告会会場にて
シングルマザーの状況について語る、徳丸ゆき子氏。2015年2月21日、報告会会場にてPhoto by Yoshiko Miwa
「シングルマザーたちの人生って、もう、暴力、暴力、暴力……の連続なんです。そして、大変なことが起こり続けて、ジリジリと落ちていく方が少なからずいるんです」
こう語るのは、徳丸ゆき子氏(大阪子どもの貧困アクショングループ(CPAO)代表)だ。
2015年2月21日夜、新大阪駅近くの公共施設において、2013年から2014年にかけて、CPAOがシングルマザー100人を対象として行った調査の報告会「シングルマザー100人がしんどい状況について話しました」が開催された。
調査対象となった100人のシングルマザーたちは、主に京阪神地域に在住(一部は、東日本大震災の被災地に在住)。調査方法は、主にインタビューであったが、データ収集も行われた。
 熱心に撮影を行う放送局のTVクルー。この報告会の様子は、既にTV・新聞等でも報道されている
熱心に撮影を行う放送局のTVクルー。この報告会の様子は、既にTV・新聞等でも報道されているPhoto by Y.M.
土曜日の夕刻という好条件もあり、会場は100名の参加者の熱気であふれていた。参加者は女性が多かったけれども、20~30%程度は男性であるように見受けられた。また、TV・新聞など5社程度が取材に訪れていた。
徳丸氏がシングルマザーたちの置かれている状況について語ったり、当事者の物語を紹介したりするたびに、会場からは深い溜め息が漏れ、参加者たちは深刻な表情を浮かべていた。同時に、取材陣は厳粛な表情になりつつカメラを回し、写真撮影を行っていた。取材陣の一部は、もしかすると子どもの貧困にもシングルマザーの状況にも深い関心はなく、ただ業務として指示されて取材に訪れただけだったのかもしれない。しかし人間には、「知るだけで変わる」「より深く知ることで変わる」ということがありうる。これは、大きな希望ではないだろうか? そんなことを考えながら、私もメモを取りつつ撮影を行っていた。
「この調査を始める時、暴力の調査をするつもりはなかったんです。でも、シングルマザーたち自身の人生が、とにかくもう、暴力の連続で。暴力をふるうのは、親だったり、きょうだいだったり、付き合った男であったり子どもの父親であったりするんですが、その人々もまた、幸せな子ども時代を送っておらず、暴力や虐待の犠牲者であることが珍しくないんです」(徳丸氏)