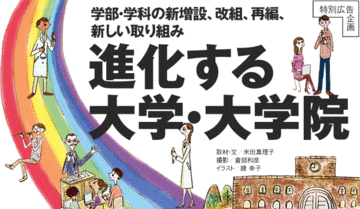ダイヤモンド・オンラインplus
スマートフォンやタブレット端末は、いつでも、どこでもビジネスに必要な情報やアプリを使える利便性の一方、端末の紛失・盗難や悪用の危険性もある。こうしたリスクを解消するのがAXSEEDのスマートフォン統合管理システム「SPPM」だ。

スマートフォンやタブレット端末は、いつでも、どこでもビジネスに必要な情報やアプリを使える利便性の一方、端末の紛失・盗難や悪用の危険性もある。こうしたリスクを解消するのがAXSEEDのスマートフォン統合管理システム「SPPM」だ。

豊田通商は2011年、経営ビジョン「GLOBAL 2020 VISION」を策定。 今期の好業績にも支えられ、三つの事業領域のシナジー効果を追求する経営方針にブレはない。 目標年度である2020年に向け視界は良好で、新卒採用にも意欲的だ。 そこで、加留部淳・取締役社長に、ダイヤモンド社が組織する現役の大学生記者クラブである 「メンター・ダイヤモンド」の学生記者が、同社の現状と経営への思いについて聞いた。

業界を問わず日本メーカーは、今なお特許や意匠登録など知財戦略を強化し続けている。中国をはじめとする新興国の隆盛に対抗し、グローバル市場で揺るぎない競争優位を確保するために知財が競争戦略の核となっているのだ。それは各種の調査結果などからも明らかだ。
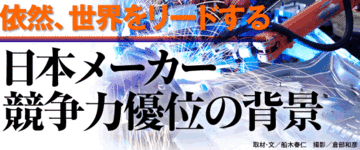
いつまで続くとも知れない低金利や企業の業績悪化による雇用不安、収入減に加え、2013年4月からは厚生年金の支給開始年齢も段階的に65歳へと引き上げられる。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦氏に対応策を聞いた。
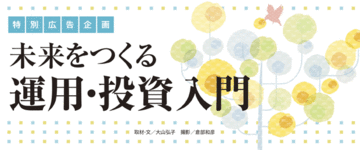
今、ビジネスパーソンの間で「学ぶ」ことが見直されている。仕事を通じて培った経験に、最新の理論と知見を加えて、さらなるキャリアアップを目指す動きだ。これをサポートするのが、ビジネススクールである。学位取得はもとより、教員や共に学ぶ学生との交流も生涯の宝となるビジネススクールの最新事情を追った。

“教育付加価値日本一”を目指す金沢工業大学のフラッグシップとして、2004年に開設された「K.I.T.虎ノ門大学院」(K.I.T.=Kanazawa Institute of Technology)。実務実践を重視する社会人向けの大学院として、着実に評価を高めている。「知的創造システム専攻」「ビジネスアーキテクト専攻」の二つの専攻を擁し、専門的知識やスキルの修得と人的ネットワーク作りに真価を発揮。そのK.I.T.虎ノ門大学院の修了生である松井正寛氏と在学生の青山大蔵氏は、現在共にメディア・コンテンツ業界に身を置いている。また今回はファシリテーターに、元「広告批評」編集長の河尻亨一氏を迎えし、お二人のK.I.T.での学びの実際と、社会人大学院へ進学する意味と価値を聞いた。

今、日本の企業に求められているのは、経営活動のすべての側面において、戦略的に思考できる人材だという。多様な知識と分析能力を備え、グローバルな視点で全体を把握できるリーダー。中央大学ビジネススクール(CBS)では、実務と理論のカリキュラムをバランスよく用意し、それらの能力を備えた「戦略経営リーダー」の育成に力を入れている。

2012年、慶應義塾大学ビジネス・スクールは創立50年を迎えた。その教育の核となるのが、ケースメソッド。具体的なケースと理論との往復の中で、経営に欠かせない実践的な知が育まれている。また、“T字型人材”の育成、グローバルを見据えた各種プログラムもKBSの大きな特長。国際単位交換プログラムによる海外トップスクールとの交流、「アジアビジネス・フィールドスタディ」など、学生がグローバルに目を向けるための土壌がKBSにはある。

日本でもようやくDSPやRTBの活用がスタートしたが、「アドテック東京2012」では、徳久昭彦氏(プラットフォーム・ワン 代表取締役社長CEO)をモデレータに、業界のトップランナーらがDSP/RTBの活用について将来の展望を語った。
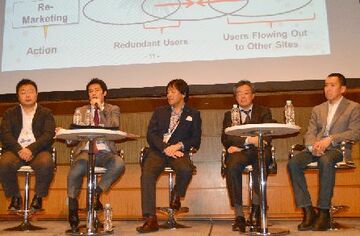
「アドテック東京 2012」では、「アトリビューション」に関するセッションが実施され、デジタル広告をより効果的誘導導線とする手法が話し合われた。また、解析テクノロジーが進化する時代だからこそ、消費者インサイトの見極め力が問われているというセッションも実施され、今後のマーケティングを考える一つの方向性が示された。

商業化が進む空港での過ごし方も変化してきた。時代に追い付き、利便性を最大限に利用する出張術を、観光ジャーナリスト・千葉千枝子氏に聞いた。

発行開始以来、さまざまな企業の海外業務をサポートしてきた「MoneyT Global」カード。法人口座から個人利用プランへの入金ができるようになり、利便性はさらに高まっている。現在では、海外ビジネスに不可欠なカードとして認識されつつある。

圧倒的な流通量を誇る米国の中古住宅市場。それを支えているのが、スピーディで透明性のある取引を可能にする、MLSという不動産情報システムだ。いったいどのようなシステムなのか、米国の不動産市場はどこまで進んでいるのか。オウチーノの井端純一社長が、全米リアルター協会の日本大使を務めるジェイスン渡部氏に聞いた。

ビッグデータ活用のためには、情報システムの基盤(プラットフォーム)を刷新しておく必要がある。インターシステムズは、独自性の高いデータベース「Caché(キャシェ)」を中心に、ビッグデータ時代に向けた「情報システムの土台づくり」を強力に支援する。

「ビッグデータ」というキーワードが注目されている。ビッグデータ活用で新たな気付き・洞察、あるいは迅速な判断を実現することで、経営やマーケティングを大きく革新していく道が開けたのである。

人間の体は、さまざまな病気を退治する力を備えている。それが、「免疫力」。たとえば、免疫力がガン細胞に勝るほど強ければ、生命を脅かされることなく健康を維持することができる。順天堂大学医学部特任教授の奥村康氏に、ガンを予防するほどの力を持つ免疫力とそのメカニズムについて聞いた。
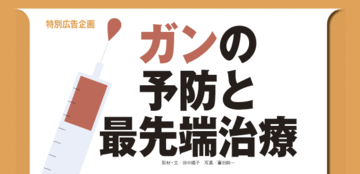
2014年に設立50周年の節目を迎える学習院大学法学部。少数精鋭のFTコースをはじめ、ユニークなカリキュラムで、これからの世界をデザインする人材を輩出している。

グローバル化に対応する人材育成を目指したり、現代社会の課題とリンクした高度な専門性を養うコースを新設する大学・大学院が目立つ。大学・大学院の最新動向について、大学通信の安田賢治・常務取締役に聞いた。