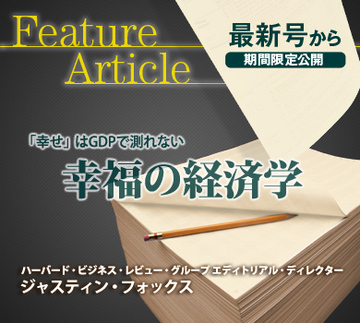記事検索
「数学」の検索結果:2621-2640/2845件
第2回
「数字に強い人」と一目おかれる2ケタ×2ケタの暗算テクニック!
『この1冊で一気におさらい! 小中学校9年分の算数・数学がわかる本』の著者・小杉拓也さんの連載2回目は、「数字に強い」と一目おかれること間違いなしの暗算方法を紹介します。お子さんにも教えてあげたい簡単テクニック。ぜひ活用ください。
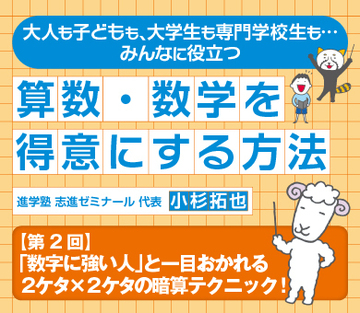
第10回
ドタバタしたイメージの「ギャグ」に対して、知的な雰囲気漂うのが「ウィット」。我々ダージャリストが標榜するダジャレは、ウィットに富んだものを目指しているのです。

第1回
落ちこぼれの私が、数学を得意になったわけ
我が子を算数・数学好きにするにはどうしたらいいか。数字に弱いビジネス・パーソンが数字に強くなる方法とは? 『この1冊で一気におさらい! 小中学校9年分の算数・数学がわかる本』の著者・小杉拓也さんの新連載「算数・数学を得意にする方法」では、そんな悩みを解決するヒントを紹介します。

第237回
バートン・マルキールの『ウォール街のランダム・ウォーカー』(井出正介訳、日本経済新聞出版社)は、内容の一部に重大な間違いを含む(と筆者は思う)が、投資家が繰り返し読むに値する名著だ。

第88回
中古品は新品の市場価値を支える方向に作用するのではないか、という仮説を想定してみた。今回はこの仮説を検証してみたい。新車(日産自動車)と中古車(ガリバーインターナショナル)に置き換えて話を進める。
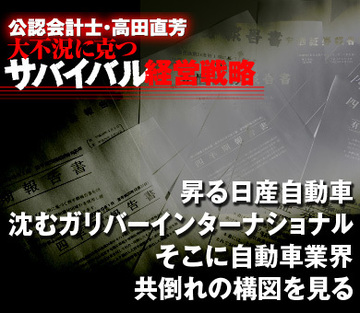
第43回
ヒッグス粒子の発見は偉業だと言われる。だが、すぐ何かの社会の役に立つかと言われれば、役には立たない。そうした基礎研究にお金を出す意味は何か。今回はいつもと趣を変えて、その問題について考えてみよう。

第87回
筆者はときどき「円高が進めば → 日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)は値を下げる」と錯覚を起こすことがある。しかしメディアは強く関連づけて報道する。いったい、この関係は成り立つのだろうか。検証してみることにした。
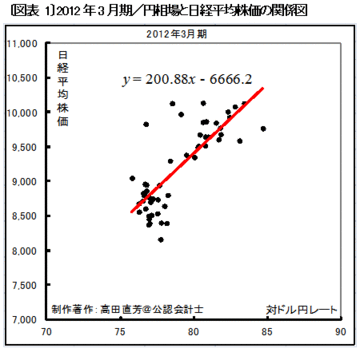
第3回
地球上の20億人が触れたマインドマップシンプルだからこそ最も効果的なツール
約40年前に発明されたマインドマップ。コンピュータで使うためのソフトウェアの開発が試みられてきたが、手がきに匹敵する使用感のものはなかなか生まれなかった。初めての公認ソフトiMindMapの開発者クリス・グリフィス氏に、開発プロセスと将来ビジョンを聞いた。
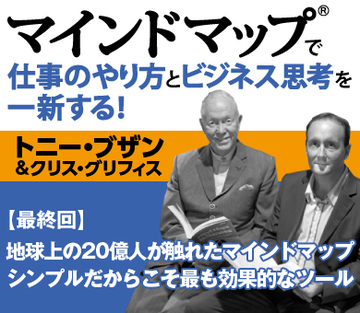
第86回
本コラムを掲載している『ダイヤモンド・オンライン』編集者との会話で「化学業界や非鉄金属業界は『読者受け』がよくないので、本連載では避けたほうがいい」という話をしたことがあった。しかし、今回はへそ曲がりを全開にして、その化学業界を扱う。
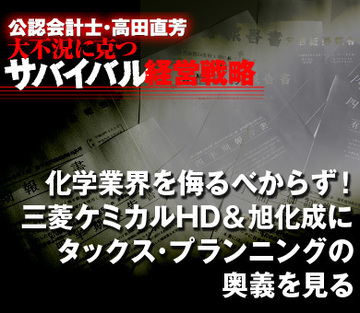
第52回
私たちの未来であるわが国の子ども・若者は、現在、どのような状況に置かれているのだろうか。今回は、内閣府が6月6日に公表した、2011年度「子ども・若者白書」を紐解いてみたい。
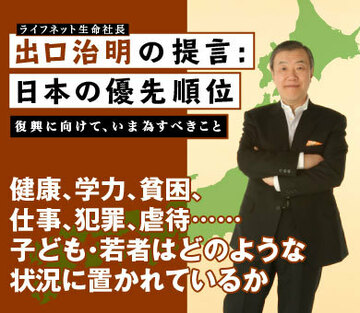
第85回
通常、将来の企業の業績は、インカム-ゲインが増大するかどうかにかかっている。資産を切り売りしたキャピタル-ゲインによって、業績回復を目指すという経営戦略はあまり見かけない。ところが、筆者が常時ウォッチングしている上場企業400社の中で珍しいケースがあった。
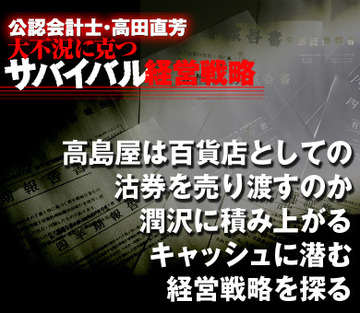
第84回
米グーグルや米フェイスブックといった少数の企業(または経営者)に、なぜ巨額のキャッシュが集まるのだろうか。それは、いまの時代で実現できる最強のビジネスモデルを確立しているからに他ならない。
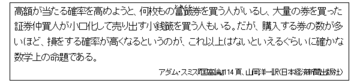
12/5/19号
志望の大学に合格できる学力が身につく中高一貫校や高校はどこか。受験生を抱える親にとっては、一大関心事だ。そこで、国公立大学や難関大学、医学部への合格実績を基に全国の学校を精査し、ランキングしてみた。上位の学校に共通する「強み」とは?

第83回
企業が成長する為に「現金回収の早さ」が重要だと、アップルを例に語られることが多い。しかし、現金回収を早めようとする経営戦略は、必ずしも企業の成長性を保証するものではない。そうした点を、スタートトゥデイなどのデータで検証してみよう。
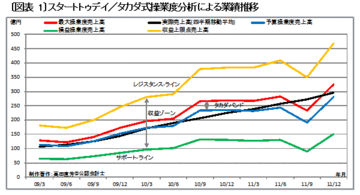
第368回
日本で今、子どもの「学力格差」が拡大しているという。国にとっては子どもの学力低下を助長する頭の痛い問題だ。足もとでは、文科省も本腰を入れて調査に乗り出した。明らかになってきたのは、「家庭の所得による学力格差」が歴然と見て取れることだ。

第82回
コンビニエンスストア業界やドラッグストア業界を取り上げる。その理由は、両業界の決算データを眺めていると、世に普及している原価計算や管理会計などの情報システムのすべてに重大な欠陥があることを、「見た目」で容易に証明できるからだ。
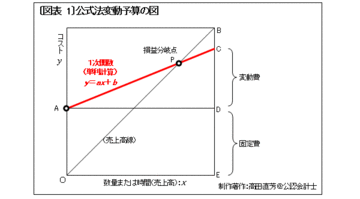
第2回
エンジニアはこれからどのように生きるべきか?
沈みゆく日本のメーカーから逃げだそうとしないエンジニアたち。対してサムスンなどの海外メーカーの技術者は自分の将来設計をどう立てているのか。フラッシュメモリ、次世代メモリで世界をリードする竹内健教授と、ちきりんさんの対談・第2回は「エンジニアは何でメシを食うべきか?」についてです。
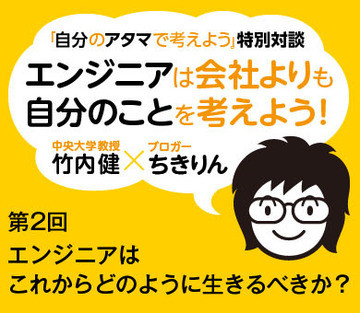
第78回
ある日本のベンチャー企業が自社の米国特許を武器に米国IT企業を果敢に攻めている。グーグル、ヤフーなど13社を特許侵害で訴え、アップルまで標的に定める。しかも勝てそうであるから驚きだ。

第81回
「需要が蒸発した」とは大手メディアでよく出る言葉だ。これを具体的に業績数字を基に調べてみた。題材としたのは、東京会場HDとT&Dホールディングス、エルピーダメモリだ。すると、多くの企業の経営戦略が必ず失敗する理由が見えてきた。
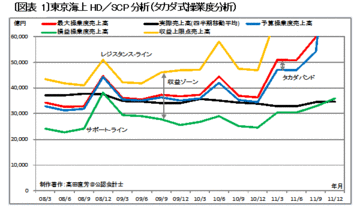
「幸せ」はGDPで測れない幸福の経済学
GDPは攻撃の的になっている。1)GDPはそれ自体欠陥のある指標である、2)持続可能性や持続性を考慮に入れていない、3)進歩と開発の測定には別の指標のほうが優れている場合がある、というものである。GDPの代替案について各界で真剣な議論が高まっており、経済政策に実際的な影響を与えるようになるかもしれない。