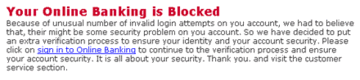藤澤俊雄
最終回
米国最大の投資サギを働いたバーナード・マドフに、先日禁固150年の判決が下された。ヘッジファンドの情報開示は今なお徹底されていない。最終回では、投資サギに騙されないためのリスク回避法を詳しく公開する。
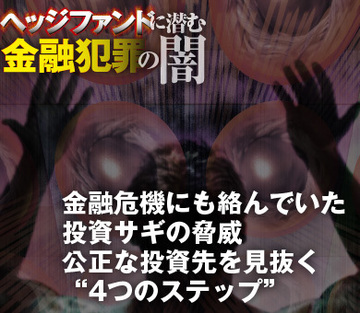
第3回
一見合理的な組織形態のヘッジファンドでも、出資するにはよくよく吟味が必要だ。実は「違法スレスレ」の投資手法をとっているケースもあり、場合によっては投資家自身も莫大な損害を被りかねないからである。特に、ようやくマーケットに「底打ち感」が漂い始めた現在、「再び動き出しつつある」と言われるヘッジファンド。そんな彼らへ投資するにあたって、投資家が注意すべきポイントは、とても多いのである。
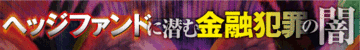
第2回
「歴史上最大の架空投資サギ」とも呼ばれる「マドフ事件」。一般投資家だけではなく、金融のプロである機関投資家までが被害を受けた。今回は、投資家が金融犯罪に巻き込まれて大損を被らないための「リスク分析の要諦」を伝授しよう。たとえプロ中のプロであっても、決して油断してはならない。
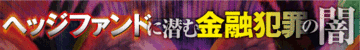
第1回
投資家から莫大な資金を集めて運用するヘッジファンド。その実態は謎のベールに包まれているため、実は金融犯罪のターゲットになり易い。米国で起きた史上最大の投資サギ「マドフ事件」がその例だ。しかし、実際に彼らが行なっている手法とは「サギの中では最も古典的な手法の1つ」だった!それにも関わらず、なぜ機関投資家たちでさえも騙されてしまったのか。「マドフ事件」の検証を通じて、ヘッジファンド投資へのリスクに迫る。
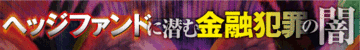
最終回
これまで、仮想世界で起きる金融犯罪の代表例として、電子マネーを媒介したマネーロンダリングを分析して来た。最終回では、有効なマーケティングにも応用できる「企業の犯罪対策」の真価について、紹介しよう。
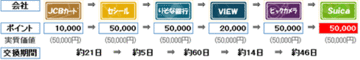
第3回
急拡大する電子マネー市場には、マネロンのリスクが溢れている。だが、それを規制する法律は事実上ないに等しい。企業に大きなビジネスリスクを負わせる金融犯罪について、現状の課題を徹底分析してみよう。
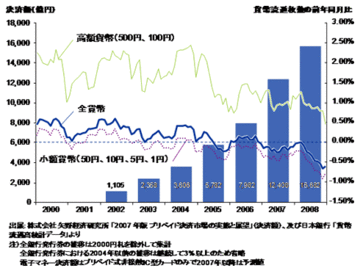
第2回
日本国民のおよそ3人に1人が参加していると言われる「オンラインゲーム」にも、金融犯罪のリスクは忍び寄っている。麻薬や銃器売買に伴う資金のマネーローンダリングが、ゲーム内で密かに行なわれるケースもあるのだ。

第1回
近年、金融犯罪は国内外問わず大きな社会問題となっているが、それがついに仮想世界にまで及んでいることをご存知だろうか。仮想世界とは、インターネットなどの情報技術を利用して作り上げられた“擬似的な世界”のこと。そこには世界中の人々が集まることから、多くの企業が商機を求めて群がっている。しかし、仮想世界における各国の法的管轄が不明確なため、そこで横行する金融犯罪を取り締まるのは困難を極めており、企業は金融犯罪というリスクに晒されているのが実情だ。