
野口悠紀雄
第11回
前回は、労働力の観点から介護の問題をマクロ的に考えた。今回は、サービスの市場価値の観点から考える。介護サービスの総額は、GDPの4%強となり、これはかなり高い比率である。しかも、この比率は将来さらに高まることが確実である。
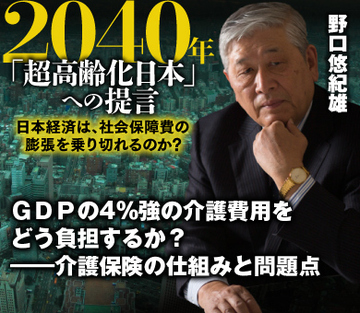
第10回
人口構造の変化により、介護に対する需要は今後ますます増える。75歳以上の人口は今後も増加し、要介護者は急増する見通しだ。今回は、そうした需要に応えられるか否かを検討する。
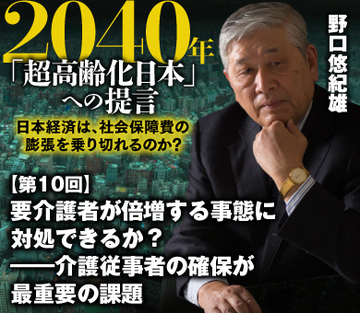
第9回
介護は、日本人のほとんどすべてが、一生の間に何らかの形でかかわらざるをえない深刻な問題である。今後高齢化がさらに進めば、その深刻さはさらに増す。日本はこの問題を乗り越えられるか。今回は、費用の面から検討する。
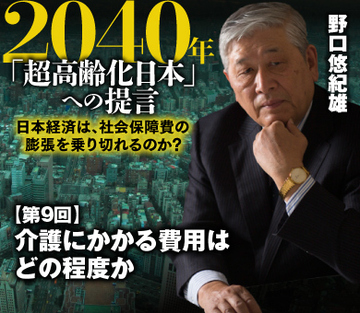
第8回
年金支給総額を削減する方法としては、前回述べたマクロ経済スライドのほかに、支給開始年齢の引き上げがある。今回は、この2つの方法の比較をすることとしよう。
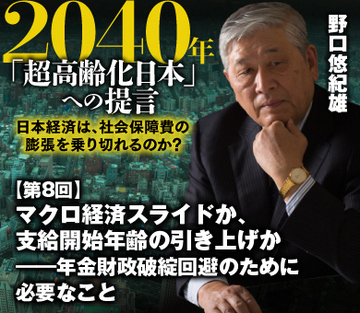
第7回
今回は、年金財政の政策措置について分析する。保険料率や国庫負担率を所与とすれば、政策は給付にかかわるものだ。これには、マクロ経済スライドと年金支給開始年齢の引き上げがある。今回は、前者について分析する。
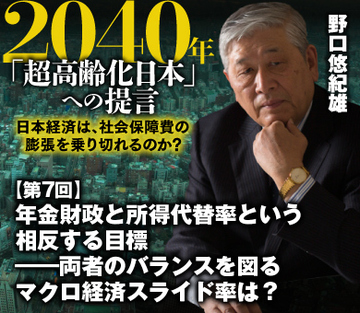
第6回
今回は、運用利回り、実質賃金上昇率、物価上昇率などのさまざまなパラメータが、将来の厚生年金財政にどのように影響するかを、前回示したシミュレーションモデルを用いて検討することとしよう。
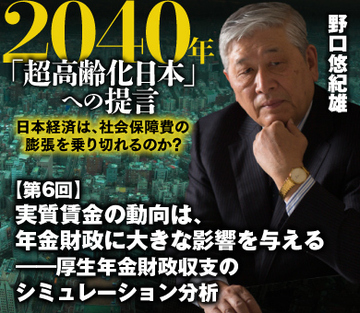
第5回
前回「厚生年金の財政破たんまで40年間程度」と述べた。しかし、これは、赤字額が一定に留まる場合である。実際には、赤字額が年々拡大し、40年後より前に年金財政が破たんする可能性が高い。シミュレーション分析によって確かめる。
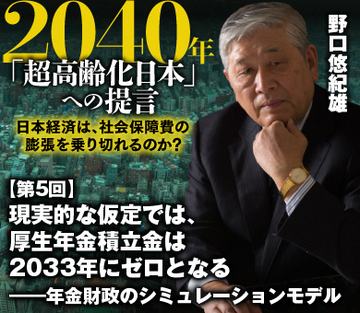
第4回
年金財政には人口構造の変化が最も重大な影響を与える。若年層が減少することがはっきりする中、2014年の財政検証における年金の利回りは著しく高い。政府の見通しは甘すぎると言わざるを得ない。
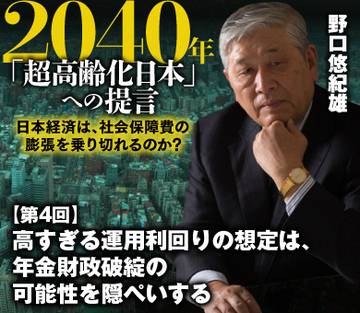
第3回
日本の公的年金には「マクロ経済スライド制度」が導入されている。これは、加入者が減少し受給者が増加することの影響を、年金額を減額することによって調整するものだ。では、これを完全に実行できれば、年金の問題はすべて解決できるのだろうか?
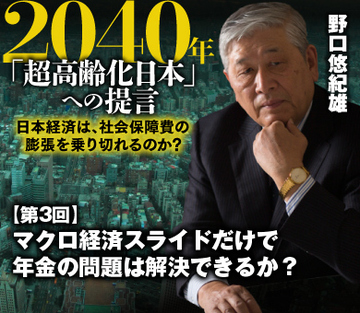
第2回
今回の2014年財政検証における収支見通しは、09年財政検証に比べて好転している。しかし、その原因は、加入者について楽観的な見通しが追加されたことによるものだ。こうした楽観的見通しを排除すると、年金財政は破綻する。

第1回
日本社会は、世界でも稀に見る人口高齢化に直面しており、経済の深刻な長期的問題を抱えている。とりわけ深刻なのは社会保障で、現在の制度は早晩破綻することが避けられない。この連載では、人口高齢化と日本経済が長期的に直面する問題について検討し、いかなる対策が必要であるかを示す。
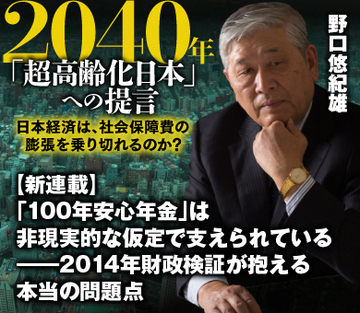
第15回(最終回)
日本における財政ファイナンスが行き着く先はインフレである。これまでは、その救済手段はなかったが、ビットコインがそれを提供する。ビットコインでなくても、ライトコインでも、リップルでもよい。円に対する信頼が失われたときに、最後のよりどころとなる手段だ。
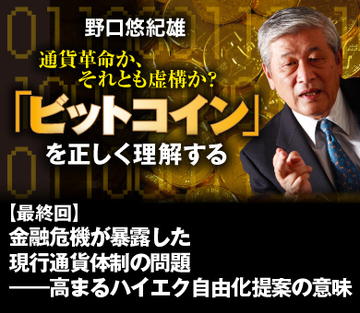
第14回
フリードリッヒ・フォン・ハイエクは、1976年に刊行された『貨幣の非国有化』において、貨幣発行の自由化を主張した。ビットコインをはじめとした仮想通貨は、ハイエクの考えを現実化するものとして注目されるが、一部には違いもある。
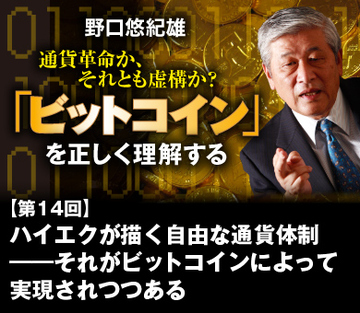
第13回
ビットコインの基礎にあるブロックチェーンの技術は、信頼性確立のために重要な役割を果たしうる。個人の存在証明、アイデンティティの確立にこの技術を使うことができれば、国家に囚われない、国境を超えた「世界政府」の実現が可能になる。

第12回
ビットコインとその拡張技術によって、新しいビジネスモデルが続々と生まれている。なかでも「分散市場」と「自動化企業」がもたらすインパクトは大きい。既存のネット企業が自動化企業に駆逐される可能性も秘めている。
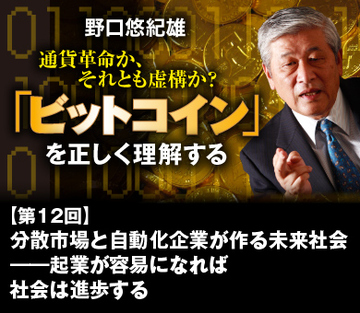
第11回
ビットコインについてはさまざまな評価があり、その中には否定的なものもある。ただ、「ブロックチェーン」という仕組みの革新性と発展可能性は、多くの人が認める。そこで、これを拡張する試みが数多く行なわれている。「次世代ビットコイン」の構想を紹介する。
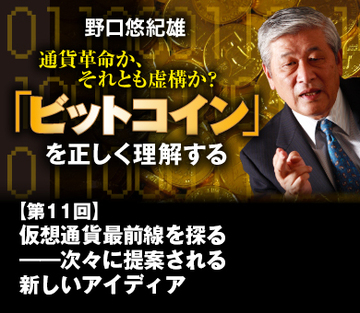
第10回
ビットコインが大きな役割を果たし得る1つの分野は、海外送金だが、送金コストの仕組みは不透明な場合が多い。そこで今回は国際送金がどのような仕組みで行なわれており、そこにどのような問題があるかを説明する。
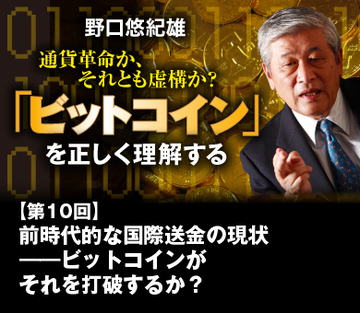
第9回
ケニアでは、携帯電話を使った送金サービスが広く普及している。なかでも最大手の「エムペサ」は、ケニアの成人人口の3分の2以上にあたる1700万人が利用している。エムペサの普及から、ビットコインが学ぶべきことは多い。
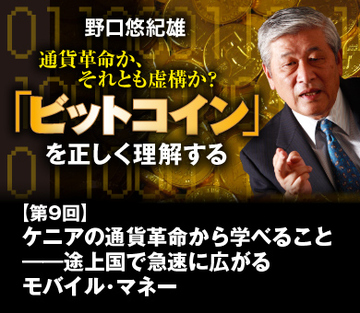
第8回
しばらく前まで、ビットコインの利用は、ウェブ店舗での違法な薬物購入、キプロスや中国などからの資本逃避、そして投機などのイメージがあった。しかしこの状況は急速に変わり始めている。実際の生活やビジネスにも影響を与え始めたのだ。ただし、日本はその動きから完全に取り残されていると言わざるを得ない。
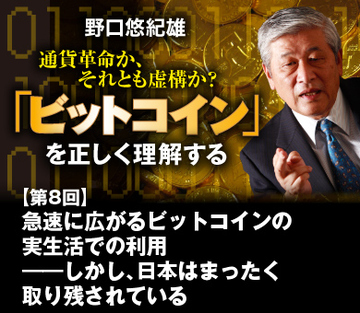
第7回
ビットコインの成功は、コンピューター・サイエンスに関わる人々に大きな刺激を与えた。インターネット上で機能する送金手段が続々と登場しているのである。昨年の11月頃にすでに80種類程度のものが存在すると言われていたが、現在ではすでに200近くのものが存在している。
