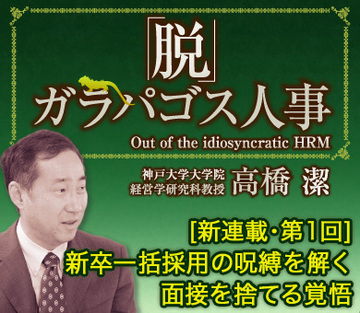高橋 潔
第8回
現代では、多くの創造的活動は、一握りの天才のものではなく、多くの普通の人々の、小さな創造性の積み重ねでできている。では、創造性を高める組織・人事制度とはどのようなものか。最終回はそのことを考えてみよう。
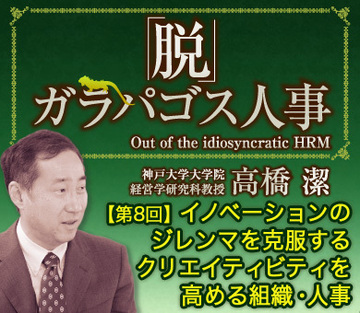
第7回
時間とは不思議なものだ。時間は主観によって伸び縮みするが、時間に対する指向性は6つに分類することができる。時間に対する展望というのは、あくまで個人の特徴だが、組織そして人事評価にも当てはまるかもしれない。
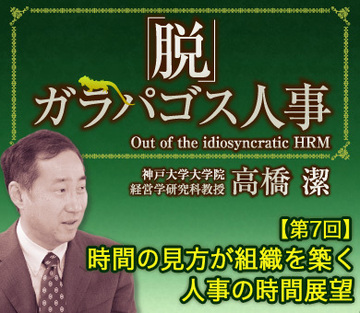
第6回
モチベーションに3つの次元があることを理解し、その上で、自分の内面を見つめ直して、その強さと方向と持続性にかかわる要素を正直に知れば、モチベーションをよりよくマネジメントできるようになる。
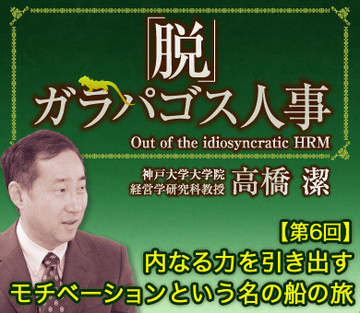
第5回
小学生に「あったらいいもの」のアイデアを問うと、その答えはほとんど『ドラえもん』化している。ドラえもんのような便利な執事役が、リーダーシップに与える影響はどれほどなのか? リーダーシップとは何かについて、脳科学の成果も踏まえながら考えてみよう。
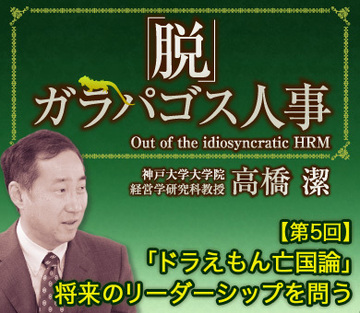
第4回
企業のための「自分を映す鏡」。それが人事評価である。だが、評価にはいつも不満が渦巻いている。グローバル化が進む中、分析的、論理的な左脳的評価と全体的、感覚的な右脳評価を連携させる必要がある。

第3回
政府が「若者雇用戦略」として、大学内にハローワークを設置する案が示された。だが、これで解決できるのは短期的な雇用のミスマッチだろう。今や大学から小学校まで、キャリア教育が盛んだが、それで本当に幸せなキャリアは実現できるのか、そのことを考えてみよう。
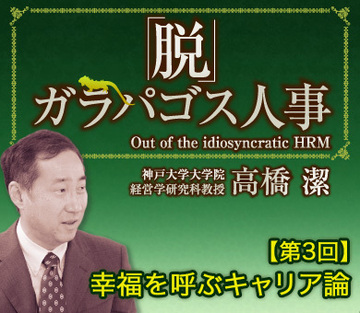
第2回
日本で人材教育といえば、OJT神話が続いている。だが、グローバル化に対応できる人材は育っておらず、OJT神話も崩れ去った。カオスとなった現代ビジネスに求められているのは、自律的に動ける人材だ。そうした人材を育成するには、対話による学習=ダイアローグが有効である。
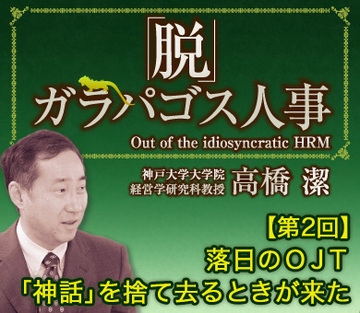
第1回
就活が最盛期を迎えている。この新卒一括という採用方法も日本独自ものだ。しかもウェブを活用するようになってからというもの、大量に募集し、面接で上澄みを採用するという手法が主流となった。が、仕事ができる人間を採用するには、「募集重視から選考重視へ」のパラダイム転換が必要である。