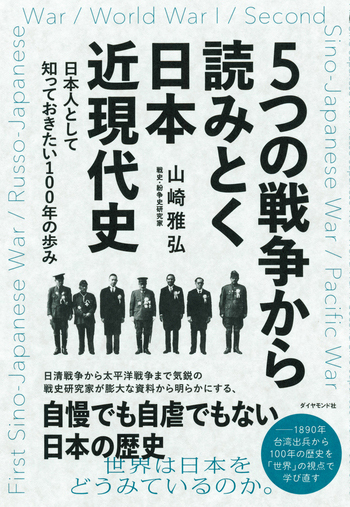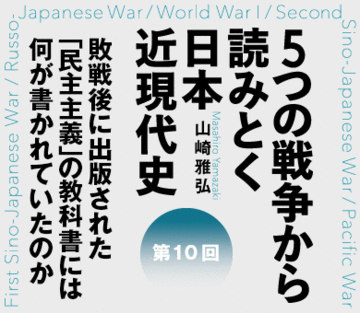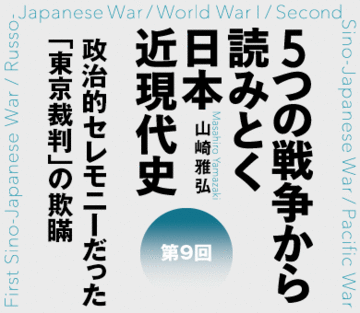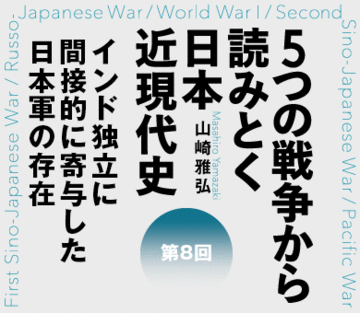近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売半月でたちまち3刷・5万5000部突破の気鋭の戦史・紛争史研究の山崎雅弘による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第11回は日米安保を中心とした戦後の対米関係、および中国・台湾との関係を解説します。

日米安保改定と
日米地位協定に残された問題
朝鮮戦争の終結(北朝鮮と韓国の間では正式な講和は結ばれず、現在に至るまで「休戦」状態)から2年後の1955年10月13日、講和条約への対応をめぐり左右二つの勢力に分裂していた日本社会党が、再び統一を果たし、日本の政治における革新勢力(いわゆる左派)の中核となりました。一方、GHQの統治下で導入された日本国憲法に不満を抱く保守勢力(いわゆる右派)の政党は、何度かの再編と統合を経た後、11月15日には日本民主党と自由党の保守合同で「自由民主党(自民党)」が誕生しました。
この保守(右派の自民党)と革新(左派の社会党)の二大政党が、それぞれ与党と野党の第一党として国会で対峙する状況は、やがて「55年体制」と呼ばれるようになり、以後38年間にわたって日本の政治状況の基本的な構図であり続けました。
二大政党による55年体制で政治が安定する中、日本は本格的な経済成長の時代へと移行しましたが、それと共に、政界では日米安保条約と行政協定の改定を求める声が、主に自民党議員の間から湧き起こりました。その理由は、内容がアメリカ側に有利なものばかりで、日本はアメリカのために義務を負う一方、アメリカは義務から免除されている、というものでした。
最初に締結された日米安保条約とは、アメリカは「好きな時に、好きな場所に、好きなだけの米軍部隊を日本国内に配備でき」、日本は「アメリカの承認なしに第三国の軍隊を国内に駐留させてはならない」一方で、米軍部隊には「日本を守る義務は特にない」という、明らかな不平等条約だったのです。
1957年2月25日、それまで自民党の石橋湛山内閣で外務大臣だった岸信介が、石橋首相の病気による退陣を受けて、新たな首相に就任しました。岸は、自民党内での安保条約改正派の急先鋒とも言える人物で、首相に就任するとすぐに、日米安保条約と行政協定の改定の実現に向けて動き出しました。同年6月、アメリカを訪問してアイゼンハワー米大統領と会談を行った岸は、6月21日に日米首脳の共同声明を発表しましたが、その内容は次のようなものでした。
「1951年に調印された日米安保条約は、暫定的な性格のものであり、その内容を改めて見直し、改定を相談するための日米両国政府による委員会を設置する」
岸はこの時、まず安保条約の内容を改定してから、次に行政協定を改定するという、二段構えの手続きを想定していたといわれています。一方、アメリカ政府は最初、岸の申し出を軽くあしらっていましたが、世界規模での東西冷戦の激化に伴い、日本を東アジアにおける自国の前線基地として強化する方針へと切り替え、1958年9月から本格的に改定交渉が始まります。
そして、1960年1月19日、ワシントンDCのホワイトハウスで「日本とアメリカの相互協力および安全保障条約(通称『新日米安保条約』)」が調印されました。新条約の主な内容は、「国連憲章の武力不行使の原則に基づき、純粋に防衛的性格の条約とする」「日米は各自の防衛能力を維持発展させる」「日本の施政下にある領域で、日米いずれか一方に対する攻撃が自国を危うくすると判断されたなら、憲法の手続きに従い共通の危険に対処するよう行動する」「在日米軍が日本以外の極東地域に出動する際には事前協議を行う」「期間は10年間とする」というものでした。
これに対し、日本国内では激しい反対運動が湧き起こり、1959年に設立された「安保改定阻止国民会議」が中心となって、全国で大勢の市民が参加する抗議デモが行われました。反対派の主張の一つは「新安保条約を締結すれば、日本はアメリカの戦争に巻き込まれる」というものでした。
1960年5月19日夜、衆議院本会議で政府・自民党は警察官を国会に導入し、単独強行採決を行いました。これにより、1ヵ後の6月19日には新安保条約が自然成立(参議院に対する衆議院の優越という制度のため)することになりますが、自民党の強行採決は市民の安保反対運動の火に油を注ぐ結果となり、国会議事堂は学生や主婦を含むデモ参加者に包囲されて、騒乱状態となりました。6月15日には、一人の女子大学生がデモ参加中に圧死する事件が発生しました。6月23日、日米両政府間での批准書の交換で、新安保条約は発効しますが、岸首相は国内混乱の責任をとって退陣を表明、7月15日には内閣が総辞職しました。
在日米軍の駐留条件や裁判権などを定めた日米行政協定は、新安保条約発効と共に、一部が改定されて名前が「日米地位協定」に変更されましたが、「公務中のアメリカ軍人・軍属が犯した犯罪の裁判権は日本にはない」との条文は、そのまま引き継がれました。そして、実際には公務外の米軍人が起こした犯罪であっても、米国務省や国防総省の意向で「公務」中の事件にされる(1974年の伊江島住民狙撃事件)などの出来事が、その後も起こりました。
親米路線と中国・台湾との関係
以上のように、日本は講和条約で主権を回復した後、東アジアにおける東西冷戦構造の中で、アメリカの傘下に属する「西側」の一国としての役割を担い続けました。では、冷戦の「東側」に位置する中国との関係はどうだったのでしょうか。
先に述べた通り、1951年のサンフランシスコ講和会議には、中国の代表が招かれていませんでしたが、その理由は、第二次大戦当時の中国政府であった国民党(台湾に逃れた蒋介石)と、その後の国共内戦に勝利した共産党(毛沢東)の、どちらを「正統な中国政府」と見なすかで、アメリカと他の戦勝国の間で意見が分かれてしまったからでした。
この時、日本政府は蒋介石の国民党を「講和する相手」だと見なし、1952年4月28日に台湾の台北で「日華平和条約」に調印しました。これにより、日本と中国の戦争は終了したことになり、台湾に対する日本の領土権放棄と、中華民国(国民党)の日本に対する一切の賠償権の放棄という合意が成立しました。
当然のことながら、中国の毛沢東はこうした日本の動きを快く思わず、日中の外交関係は1970年代まで途絶えたままでした。しかし、1972年2月にニクソン米大統領が中国を訪問し、東アジアの冷戦構造が多少和らぐと、同年7月7日に首相となった田中角栄は「日中国交正常化を急ぐ」と述べ、水面下で中国との接触を開始しました。
そして、就任から2ヵ月後の1972年9月25日、田中は中国の北京に降り立ち、周恩来首相らと会談した後、9月29日に「日中共同声明」を発表しました。その内容は、日中の国交正常化と、日本政府が中国(共産党)を合法的な唯一の中国政府と認めること、台湾が中国領の一部であると見なす中華人民共和国政府の立場を日本政府が理解・尊重すること、戦争賠償の放棄、相互の領土不可侵などでした。
この日中共同声明の成立により、先に日本政府が蒋介石と結んでいた日華平和条約は事実上「無効」となりました。この事実を知った台湾の蒋介石は激怒して、日本との外交関係を破棄すると日本側に通告しました。これ以降、台湾は日本と非公式な外交関係を維持していますが、正式な大使館を互いに持たない状況が、現在まで続いています。