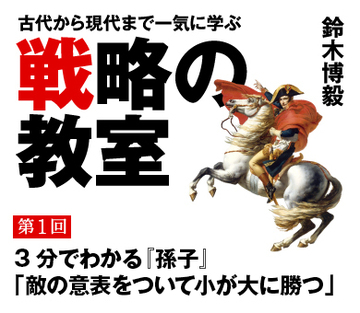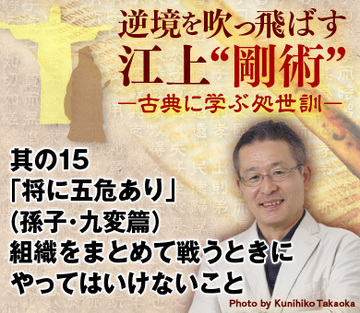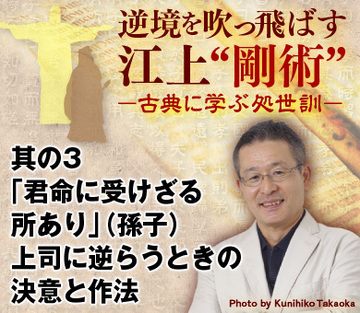『週刊ダイヤモンド』9月10日号の第1特集は「孫子~現代に通じる『不敗』の戦略」です。ここ数年、日本で『孫子』ブームが起こっています。2500年前の中国・春秋戦国時代に書かれた兵法書が、なぜはるか時代が下った現代まで読み継がれているのでしょうか。孫子の魅力と人気の秘密に迫りました。
2500年前の兵法書『孫子』が
いまブームになっている理由
 史上最強の兵法書を著した孫武の生涯は、今も謎だらけである Photo:Bridgemen Images/Aflo
史上最強の兵法書を著した孫武の生涯は、今も謎だらけである Photo:Bridgemen Images/Aflo
『三国志』の曹操、戦国時代の武将・武田信玄、米マイクロソフトの創業者・ビル・ゲイツ氏、ソフトバンクグループの孫正義社長──。
時代も国籍も違うこれらの人物に共通していることがある。2500年前に書かれた『孫子』に影響を受けている(いた)ことだ。
曹操は自ら孫子の注釈本を書くほど孫子を使い倒し、戦いでは8割の勝率を誇った。武田信玄が孫子の一節「風林火山」を戦術に取り入れ、旗指し物にしていたことは有名である。ゲイツ氏は自著の中で何度も孫子を引用しており、孫社長に至っては、孫子をアレンジした独自の兵法を編み出すほどの傾倒ぶりだ。
時を超え、国境も超えて読み継がれてきた孫子が、いま日本でブームとなっている。中国の春秋戦国時代という戦乱の世に書かれた兵法書が、なぜ現代の日本で脚光を浴びているのか。
「個人も企業も激しい競争にさらされているということがある」。中国古典研究家で孫子関連の著作も多い守屋淳氏は、ブームの社会的背景をそう分析する。戦乱の世で生き残るための原理原則を説いた孫子の教えが、グローバルな競争が激化しているいま、必要とされているのではないかというのだ。
ただ、競争が激しい時代に孫子が読まれているのは、「勝つ」ためのノウハウが詰まっているからではない。孫子は兵法書でありながら、最上の策は「非戦」だと言い切る。いったん戦えば、多かれ少なかれ人も組織も疲弊する。それ故にまず、戦うべきかどうかを考えよと説いているのだ。
一般的な戦略論はいかに勝つべきかが主眼となるが、孫子は「不敗」の戦略で貫かれている。勝てない戦いはするな。もし戦うなら犠牲は最小限にせよ。当たり前だがなかなかできないことを、孫子はずばり指摘するのである。