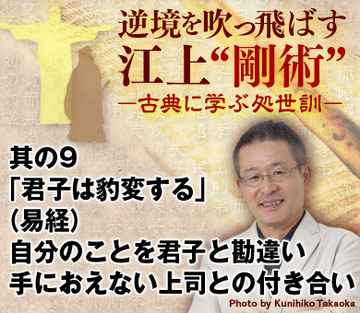ビジネスパーソンの多くが1日の大半を過ごす「会社」について、改めて考える機会はさほどないかもしれません。ただ、会社という人の集まりが持つ多義性とフィクション性を知り、向き合う視座を培うことが、“独立して”生き続けるために必要だ、と10月7日発売『論語と算盤と私 ――これからの経営と悔いを残さない個人の生き方について』の著者、朝倉祐介さんは言います。同書の発売を記念し、全体のエッセンスがギュッと凝縮された「はじめに」の後半を昨日の前半に続いてご紹介します。
もっとも、私のように経験の浅い人間が大上段で「経営」を語るというのは、なんともおこがましいことだとも感じます。読者諸賢のなかには、「経験といっても、社会人経験も乏しい小僧じゃないか」とお叱りの向きもあるでしょう。浅学非才の身であることは、ほかならぬ自分自身が一番よく理解しています。とりたてて確信めいた理論を、自分自身のなかで構築できているわけでもありません。
とはいえ、考えてみれば現在の自分の年までは、坂本龍馬も吉田松陰も高杉晋作も生きながらえてはいませんでした。ミクシィ代表に就いた際も年齢のことを散々言われたものですが、約140年前、渋沢栄一は30代前半で第一国立銀行を設立しています。
先人の偉業を思うと、いつまでも経験不足を口実に口ごもるのもまた浅薄な気がしますし、何かにつけて年齢や経験を取り沙汰するメンタリティが、日本全体の潜在的な競争力を阻害しているようにも感じます。拙いなりにも自分の考えを棚卸しして、読者のみなさんにご披露することにも、幾ばくかの意味を見出すことができるのではないかと思う次第です。
読み進めていただくとお気づきになるかと思いますが、私の言動は必ずしも首尾一貫しておりません。多分にいい加減な性格であるのもさることながら、従業員・経営者、コンサルティングファーム・事業会社、スタートアップ・上場企業、売却側・買収側、調達側・投資側と、異なる立ち位置を経たこともあって、企業を取り巻く事象について語るべき切り口が定まらないことが大いに影響しているように感じます。基本的には経営者としての視点を軸にして考えを述べるよう試みてはおりますが、ところどころ、「誰の目線で物を言っているのだ」とお感じになる点もあることでしょう。なんだか随分といい加減な物言いにお感じになるかもしれませんが、そんなものだと思って話半分にお付き合いください。
一方で立ち位置の定まらない異邦人であったことは、私が仕事に携わるなかで大いにプラスに働いたとも感じています。それぞれの世界では当たり前に受け止められている出来事であっても、アウトサイダーである私には風変わりな奇習に映り、批判的に観察することができたからです。
 “生身”の人間が携わることの難しさと面白さ
“生身”の人間が携わることの難しさと面白さ
また『論語と算盤と私』では、事業の成否を決する要素について、外部要因のみならず内部要因の側面に触れることを意識して執筆にあたりました。その時々の需給関係、競争環境、技術革新といった業界動向に関する描写は、主に外部要因について説明したものであり、当事者ではない外部の人間からでもある程度は客観的に観察可能な対象です。事実と論理によって記述できるという意味において、語りやすい企業活動の側面であると言えるでしょう。
一方で、会社には生身の人間が携わっています。自身の会社での活動を改めて振り返ってみると、外部要因以上に内部要因の調整や解決に、より心血を注いできたように感じます。必要とされたのは、時に論理以上に情理であり、経済合理性では説明できない、心理面にまで踏み込んだ洞察が求められる局面が多々ありました。この類の話はなかなか外部からは窺い知ることができませんし、どうしても主観的な内容になってしまいます。また、それぞれの会社が置かれた特殊な状況によって採るべき打ち手も変わってくるため、普遍化して体系立てた説明がしにくい領域であるとも思います。
しかしながら、外部の人間から見ると打ち手が明確で、「この会社はこうすればいいのに」と感じられる焦れったい状況であっても、内部にはそうした打ち手を実現できないことにはできないなりの理由があるものです。理屈で「あらまほしき世界」を考えたうえで、それが実現できない内部的な理由を一つひとつつぶしていき、現実を可能な限り理想に近づけていくこと。これが、事業をうまく回す勘所ではないかと思うのです。これが同書であえて、主観的な内部要因にまつわる話をできるだけ盛り込みたかった理由です。
多くの会社に当てはまるものかは甚だ心許ないところではありますが、なるべく私自身が経営の現場で見えた景色を一般化してお伝えするよう、心がけたつもりです。
本書は言うなれば、私なりに培っていくべき「経営観」に関する中間レポートという位置づけです。まだまだ生煮えの考察ではありますが、読者のみなさんが個々人の「経営観」を築かれるうえで、多少なりとも参考、あるいは叩き台、踏み石になるのであれば、私にとってこれに勝る喜びはありません。(続きはぜひ書籍『論語と算盤と私』でお楽しみください!)