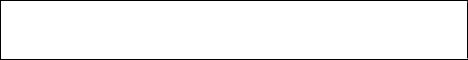日立製作所が、TOB(株式公開買い付け)による上場5子会社の完全子会社化を発表した。グループ構造改革の号砲となるのか。
この構想が具体化し始めたのは、今年3月。古川一夫前社長(現特別顧問)の時代だ。もっとも、親子上場はもちろんのこと、課題自体は積年のものだった。
今回TOBの対象となる5社のうち3社は、情報システム部門の企業群である。具体的には、日立情報システムズ、日立ソフトウェアエンジニアリング、日立システムアンドサービスだ。同部門は、日立の連結売上高の2割以上を占め、電力・産業システム部門と並ぶ主力事業である。この3社の統合問題は、古川前社長時代にも、年に1回は経営会議の俎上に上った。日立コンサルティングに構造改革案を提案させたこともある。
背景には、日立の苦境があった。情報システム業界で近年進んできた2つの潮流──「ハードからソフト」「グローバル化」に完全に乗り遅れてしまったのだ。売上高の8割を依存する国内市場で、地盤だった金融業界は統合で顧客が減り、一方、日産自動車などグローバル化を求める顧客には十分なサービスが提供できない状況だった。
競合する富士通は一歩先に海外に活路を求め(海外売上高比率は約35%)、NTTデータは官公庁をがっちり押さえた。日立は足場を失っただけでなく、苦境にあってなお、グループ内で顧客を取り合ったり、作業を分け合ったり、ムダがまかり通っていた。
TOB対象の他の2社(電力・産業システム部門の日立プラントテクノロジーと、デジタルメディア部門で民生電池を手がける日立マクセル)も同様に、グループ内で事業が重複して、非効率だった。
なにより、日立が中核事業に据える「社会イノベーション事業」──電力や交通などのインフラをシステムごと請け負うBtoBビジネス──の需要が世界的に拡大するなか、リソースの集約と適正配置が、喫緊の課題だった。
古川時代には結局、その時々に当該子会社のトップが合併や子会社化に猛反発し、解決には至らなかった。だが、「前期の7800億円超の大赤字が背中を押した」(関係者)。今回の完全子会社化は、対象5社の、日立以外の少数株主持ち分の利益が、連結決算から流出するのを防ぐ狙いもある。
構造改革が動き始めた意義は大きい。ただし、始まりにすぎない。海外市場を攻め収益力を強化するには、取り込んだ事業でさらなる構造改革が必要だ。海外プレーヤーの買収など前向きな投資も必要で、財務の立て直しが急務だ。
今回のTOBにかかる費用2790億円は、借り入れで賄う。自己資本比率は11%まで悪化しており、増資も視野にある模様だ。中核以外の事業売却も急ぐ必要がある。有利子負債8900億円を抱える日立キャピタルや本体とシナジーの薄い日立物流などの優良資産だ。過去に、各社の抵抗やOBの横やりで棚上げされてきた。
景気低迷で来期の最終黒字化が確実視できないなか、改革を託された川村隆会長兼社長と五副社長の実行力が引き続き問われている。
(『週刊ダイヤモンド』編集部 柴田むつみ)