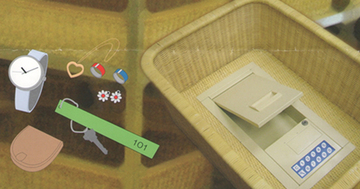人生のなかで、思い出すのが辛い時期というものがある。野村良子さん(仮名)の場合、入社1年目がそれにあたる。
「1日10回くらいは辞めたいと思っていました」
「……わかります」
「キャップが怖くて」
「それもよーくわかります」
「生理だって、止まっちゃいましたからね」
「ああ、あります、あります」
なんだか、いつもと調子が違う。それもそのはず、野村さんは全国紙の記者なのである。
優雅なランチなど夢のまた夢
猛スピードが基本の新聞記者の食事
新聞記者という職業について書くのは、かなり気が重い作業である。自分自身の恥ずかしくもなさけない体験と、どうしても向き合わなければならなくなるからだ。
筆者が某経済新聞社に入社したのは1993年のこと。すでにバブルははじけていたとはいえ、今と比べれば景気も良く、牧歌的な時代だった。
政治・経済の中枢に触れることもなく、もっぱら家庭面や夕刊、日曜版に載る記事ばかりを書いてきた。スクープとは無縁で、これといって胸を張れるような記事を書いた記憶はなく、むしろ、怒られた思い出ばかりが鮮明に残っている。
なかでも、1年目は悲惨であった。
「おい、今日はなにか書けるネタはないのか?」
夕方になると、翌日の朝刊に向けた出稿予定をデスクに知らせるため、キャップが聞いてくる。
「ありません……」
「お前は今日1日、なにを取材していたんだ?」
「……すみません」
締切が迫るといつも憂鬱になり、逃げ出してしまいたいような気分になった。
「もっと勉強して来い!」
あまりにモノを知らなくて、取材先にまで怒鳴られたり、あきれられたりしたことも、1度や2度ではなかったと思う。