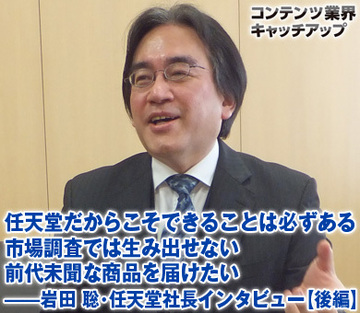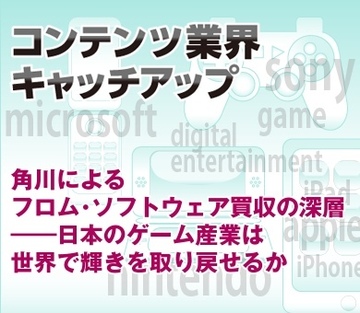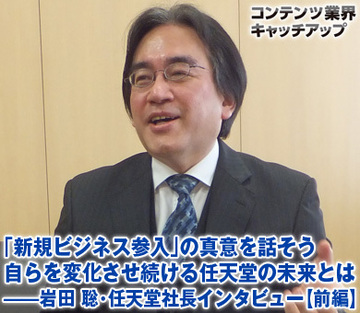昨年まで不調に喘いでいた大手ソフトメーカーを、復調させたソーシャルゲーム。そのソーシャルゲームを、ゲーム業界の雄である任天堂はなぜやらないのか。前編に引き続き、後編ではソーシャルゲームと任天堂のゲームのユーザーの違いから、その理由を検証する。
ソーシャルゲームに定額制はあり得ない
「料金をどれだけ払わせるか」が勝負に
ソーシャルゲームが儲かっていることは、ディー・エヌ・エーやグリーの決算を見ればわかるが、基本的に一律同額である家庭用ゲームと違って、ユーザー1人あたりの支払額に差があるという。
大手ソフトメーカーの経営幹部は、「お金を払っている人は2割弱で、タダでずっと遊んでいる人が8割。お金を払ってくれる人の中には、総額で200万円を超える人も珍しくない」と話す。
それでは、ユーザーも納得づくで料金を払っているのかと思いきや、思いのほか料金を巡るトラブルが絶えない。たとえば、1ヵ月で8万円弱の利用料を請求されたユーザーが「子どもが勝手に使った」と訴えて、交渉の末利用料を取り戻したという話もある。
そんなにモメるなら、定額にしてしまえばよいのではないかとも思うが、あるソフトメーカー経営幹部から、「そんなことはあり得ない」と一蹴された。
しかも、「ソーシャルゲームの場合は、アイテム1個に5000円払うことも一種のゲームになっているんだから、パッケージビジネスのように定額化することはあり得ない。もしそんなことをしたら、誰もやらなくなるよ。業界歴が長いのに、そんなこともわからないの?」という説教までされてしまった。
しかし、不況だと世間では騒がれているのに、なぜこんなにお金を払ってもらえるのであろうか。たとえば、ソーシャルゲームの課金方法の1つに「ガチャ」というものがある。
この「ガチャ」とは、駄菓子屋やスーパーなどにある、お金を入れてレバーを回してアイテムを得る「ガチャガチャ」のデジタル版だと考えていただければいい。