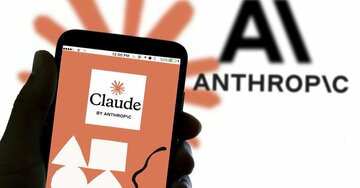2005年9月、郵政民営化を旗印にして、国民から圧倒的な支持を受けた小泉政権による改革が始まってからわずか4年――。今や国民の郵政民営化に対するスタンスは大きく変化した。
今年8月の衆院選挙で、国民は「小泉改革の巻き戻し」を訴えた民主党を圧倒的に支持した。それを受けて鳩山政権は、郵政民営化の見直しに着手し、民営化に反対の姿勢を取ってきた亀井氏を民営化担当大臣のポジションにつけた。
亀井氏は、予想通り、一種の怨念さえ感じられる手法で民営化のプロセスを見直し、日本郵政の西川社長を事実上更迭して、元財務次官の斎藤氏をトップに据える人事を行なった。
それと同時に鳩山政権は、郵政事業の4社体制の見直しや、株式売却の凍結を閣議決定した。こうした一連の動きに関しては、一部の専門家から“危険な官業回帰”との批判も上がっている。
郵政事業の民営化は、わが国の金融システムの根幹に関わる、極めて複雑な問題と認識すべきだ。簡単に答えが出るものではない。
したがって、この問題を「小泉改革とその反動」という単純な構図で見ることは、適切ではない。
この問題を判断する最も重要な基準は、「国民がどれだけのコストを負担して、どれだけのベネフィットを受けるか」という、“費用対効果”であるべきだ。
郵便や郵貯、簡易保険の拠点を、過疎地を含む全国に展開し、一律のサービスを提供するには大きな費用がかかる。つまり、それを国の事業として続けるならば、税金を使って補填せざるを得ない。
そのため小泉政権は、そうした事業を民営化して、「どれだけのコストを払っているか」を明らかにしようとした。そして、株式を公開することによって、市場の機能を通して事業を効率化することを選択した。
ところがそれ以降、景気の低迷が続いたこともあり、地方を中心に民営化に反対する声が予想以上に盛り上がった。その流れに乗ったのが、今回の民主党政権だ。