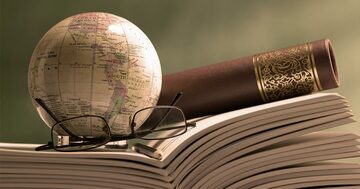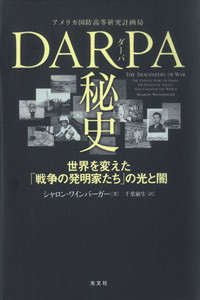 『DARPA(ダーパ)秘史 世界を変えた「戦争の発明家たち」の光と闇』
『DARPA(ダーパ)秘史 世界を変えた「戦争の発明家たち」の光と闇』シャロン・ワインバーガー著
(光文社/3200円)
科学に基づく新たな技術が国家の安全を左右する。1957年、最初の人工衛星スプートニクの打ち上げで旧ソ連(現ロシア)に先んじられた米国は、改(あらた)めてそれを痛感した。
翌58年、対抗策として設立されたのがDARPA(米国防高等研究計画局)である。本書は、かつての機密文書や豊富なインタビュー記録を用い、発足当初から今日に至る足跡をたどっている。
本書が投げかける疑問の一つは、平和研究と軍事研究の境界線だ。旧ソ連との地下核実験禁止条約を締結するため、米国は核実験と地震とを確実に識別する技術を必要とした。そのために、DARPAは大規模な予算を投入し、科学としての地震学を発展させた。軍縮のための基礎科学研究をも、軍事研究と呼ぶべきなのだろうか。
DARPAの実質的な出発点は、ベトナム戦争での60年代以降の秘密作戦だ。軍の旺盛な需要に、彼らは応えた。小型の自動小銃を開発するに止(とど)まらず、ゲリラから隔離した「戦略村」を構想し、空爆による心理的打撃の効果を上げるために社会心理学をも動員した。
もっとも、ベトナム戦争への関与は全体として大きな失敗だった。戦略村は機能せず、社会心理分析は的外れで、枯れ葉剤のように、国際的にも、国内的にも、厳しい非難を浴びた開発成果もあった。
研究戦略の観点から興味深いのは、DARPAでの研究者の裁量の大きさと、異常なまでの意思決定の速さである。後世インターネットとして結実した研究は、一人の独創的な研究者の発意を当時の局長がわずか15分で承認したことから始まった。有識者の会議で、長時間かけて意見を集約するようなやり方とは、対照的である。
とりわけ注目すべきなのは、無人攻撃機、ステルス技術、GPS(全地球測位システム)、自動走行車、音声認識、精密誘導弾、さらにコンピューター間連携による統制支援や兵器群連携システムなどを早くから手掛け、しかもいったんは失敗に終わっていたことだ。
同様のことが、今日も行われている可能性は高い。数十年後に人類が目にする技術は、いま密(ひそ)かに研究されているのかもしれない。成果の公開と自由な相互批判を基盤とする科学研究とは別個に、闇に隠れたダークマターのような技術の世界が、見えないところに広がっているのかもしれない。
近年のDARPAは、有名になった割に活動が低調であり、存在理由すら問われる状況だという。だが、「米中新冷戦」が語られる今日、技術安全保障における米国の躍進をもたらした組織の実像を知る意義は、まことに大きい。
(選・評/東京大学教授、信州大学教授 玉井克哉)