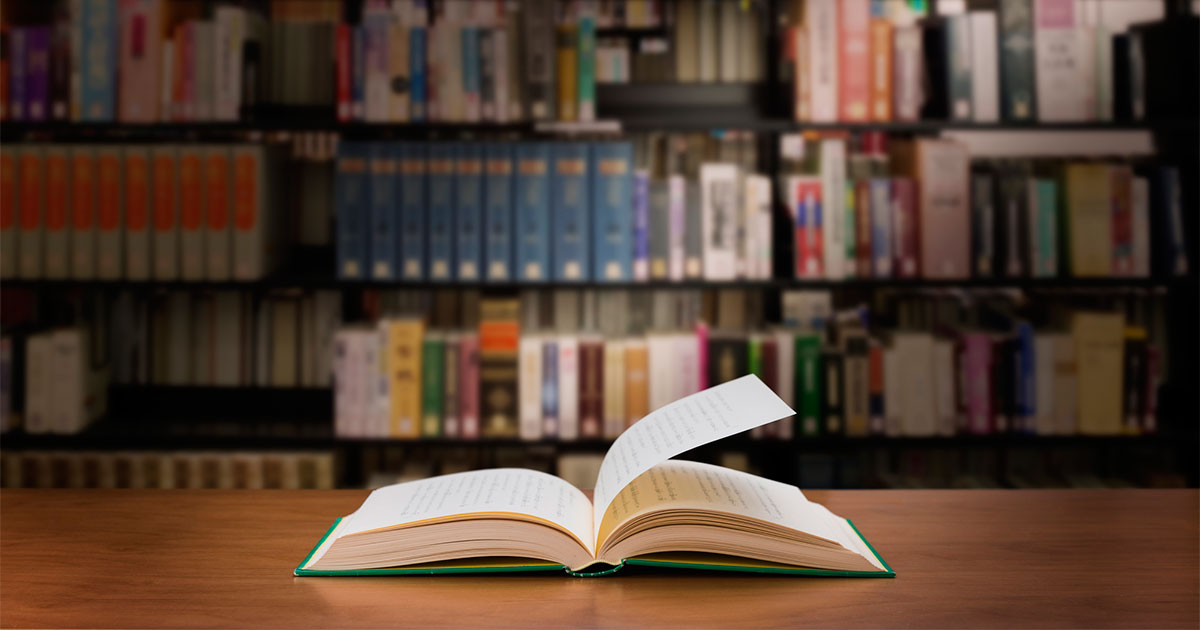
Book Reviews 私の「イチオシ収穫本」
問題の本質は少子化ではない 企業投資で経済は復活できる

元財務大臣の父が語り尽くす 世界中で歓迎された経済読本

過去に直視を避けてきた現実 欧州リベラリズムの末期症状

当代屈指の歴史家が取り組む「世界を動かした男」の前半生

トランプ支持者の今を伝える労働者の街を歩いた定点観測

リベラルと保守の断絶を越えトランプ支持者の深奥に迫る

国家と法の支配と民主主義、フクヤマが描く人類興亡史

超大国を内面から掘り下げる 洞察に満ちた波乱の米国通史

大胆な金融緩和政策をしてもなぜ、経済の回復が遅いのか?

多様な協働が求められる中で敵と手を組んで前進する方法

古今東西を縦横無尽に駆ける戦略思考の本質を伝授する書

混迷が続く世界情勢の渦中で少数民族の将来はどうなるか

ウッドワードの新作ながらも不完全燃焼を感じる政権批判

“ディストピア”は不可避か 新技術がもたらす階級社会

世界的作家をめぐる誕生秘話 本人を含む関係者の声で検証

消費増税という手段に頼らず日本は生活経済大国になれる

科学と軍事と民生技術を集約 謎のイノベーション推進組織

元米軍の技術将校が警告する“未来の戦争”での重大な懸念

日常生活でも使われる「戦略」 その本質を追求する渾身の著

他人と違っても欠点ではない 「排除しない社会」を考察する
