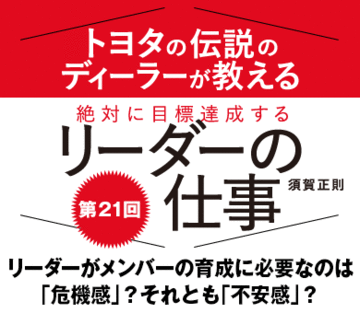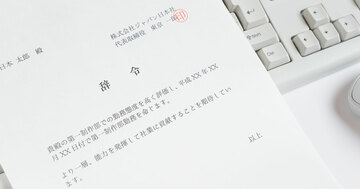社員と共有すべきなのは、危機感ではありません(写真はイメージです) Photo:PIXTA
社員と共有すべきなのは、危機感ではありません(写真はイメージです) Photo:PIXTA
経営者が社員と共有すべきは
本当に「危機感」か?
 小宮一慶
小宮一慶小宮コンサルタンツ代表
当社の社員には危機感がないと嘆き、従業員に対してむやみに危機感をあおり、危機感を共有したがる経営者がいます。しかし、経営者が従業員に語り、共有すべきなのは危機感ではありません。「現場」「理念」「夢」の3つです。
経営者は経営が順調であっても、常に最悪の事態を想定し、備えています。私は決して、その危機感を従業員と共有することを否定しているわけではありません。
例えば、受注が増えて業績が安定している。おかげで利益が順調に積み上がり、冬のボーナスは多く出せそうだ。そんなときは社内に緩みが生じがちなので、「治に居て乱を忘れず」のことわざ通り、従業員の気持ちを引き締める目的で、経営者が抱いている危機感を伝え、共有するといいでしょう。特に幹部とは、不測の事態に備えて将来のリスクを想定し、そのことを前提に危機感を共有すべきだと思います。
しかし、経営が順調なときは従業員と一緒に浮かれる一方で、経営が危機に陥るとやおら危機感をあおるような経営者の行動には賛成できません。危機に陥ったのは真面目に働いている従業員のせいでしょうか。いえ、そうではありません。原因の大半は、良い時期の経営者の危機感不足や、経営能力の低さにあるのです。
経営コンサルタントという職業柄、倒産に追い込まれた会社を何社も見てきましたが、会社の経営が悪化したときに従業員の危機感をあおると余計に社内が浮足立ち、悪いうわさがまん延しがちです。そして、多くの社員の心まで縮こまり、のびのび働けなくなり、優秀な社員から辞めていくという悪循環に陥ります。
中小企業の場合、受注が激減した、商品が売れなくなった、借金が増えて返済が難しくなったといった経営不振の原因をつくった責任は、元々はすべて経営者にあります。「商品が売れない」と従業員を責める前に、まず経営者自身が謝るべきです。返済できないほどの借金を作ったのは経営者自身であり、従業員ではないことを自覚しなければなりません。