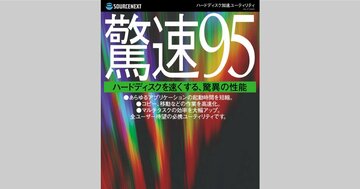1997年にソースネクストが発売したタイピングソフト「特打」は、なぜ累計600万本の大ヒットとなったのか? その開発とネーミングの秘密を聞きました。
ソースネクストの歴代ユニークな製品としてよく挙げていただくのは、1996年に出したソフト「驚速」シリーズのほか、1997年に発売したタイピングソフト「特打」です。当時、高視聴率を誇ったTBSテレビの看板番組の一つ「筑紫哲也NEWS23」のスポンサーになって、CMを流していたので、覚えている方もいらっしゃるかもしれません。
「特打」も、日本(人)に対する私の危機感から生まれた商品でした。ソフトのライセンスの買い付けにアメリカに出張に行ったとき、60代ぐらいのアメリカ人女性がパソコンのキーボードを打っているのを見たことがありました。
これが、猛烈に速いのです。というのも、アメリカにはタイプライターの文化があったので、キーボードに抵抗がありませんでした。
ところが、パソコンブームに沸いていた日本はどうだったか。
年配の人どころか、若い人ですらキーボードを打つ手つきは、たどたどしいものでした。私は創業当時からよく量販店の売り場に立っていたので、手元を見ないでタッチタイピングができる人は、ほとんどいないことがわかっていました。実はソースネクスト社内でも、ソフトウェアの会社なのにうまくキーボードを打てない人が多かったのです。
私は当時31歳でしたが、これはまずいことになる──と危機感を持っていました。これからパソコンがビジネスにも浸透し、メールのやりとりも当たり前になる。そんな中で、おぼつかない手つきでキーボードを打っていては、日本は世界に置いていかれる。コミュニケーションがまともにできなくなる、と思ったのです。だから、「特打」は日本のために作ろう、と考えました。これからの日本のために、必須のソフトだ、と。
このとき改めてわかったことは、お金儲けに関係なく、社会のためにやろう、と考えたものは、かなりの確率で売れるということです。近年ソースネクストが発売したAI通訳機「ポケトーク」でも同じです。このまま英語が使えないと日本はまずい。言語で大きく損をする。
「特打」は、今までで累計600万本以上売れるほどご好評いただいています。
この「特打」の開発にあたっては、これまでにない面白いものにしなくてはいけない、と考えていました。人は面白いものなら続けられるからです。
ゲーム感覚で楽しく続けていれば、タッチタイピングはできるようになる、と私は思っていました。だから、その習慣化して続けられる仕組みこそが大事になる。実はタイピングソフトでも、まじめなものはすでに販売されていましたので、今までにない楽しいソフトを作る必要がある、と考えました。
しかも、ターゲットをかなり絞りました。当時30~40代の男性です。というのも、この年代の人々には、一つの習性があるからです。若い人の前で打てないのは恥ずかしいので、コソコソと家で練習したい。家でやるなら、楽しくやりたい。このニーズに、まさしくマッチするものを作ろう、と思ったのでした。
実際、これはとても好評だったのですが、「特打」には他のタイピングソフトのようなキーボードの絵が出てきません。練習するためのメニューに文字もない。登場するのはイラストだけで、ユーザーにも衝撃だったようです。しかも、うまくできると「すごーい!」などとソフト上のキャラクターが褒めてくれる。これが、非常に好評でした。
ネーミングはターゲットとコンセプトに合わせる
また、ネーミングも大きなポイントだったと思っています。「驚速」をすでに出して大きくヒットしていましたから、「速い」という言葉を使ったほうがいいのではないか、という意見が、社内から続出しました。
しかし「特打」にこだわったのは、プロ野球のワードでもあったからです。ターゲット層が好きなプロ野球が、まさに全盛の時代でした。野球の世界で特打というのは、バッターが打てなかったときにやるもの。いってみれば、隠れてコソコソ練習するものでした。要するに、コンセプトにぴったりだったのです。
だから、「特打」というネーミングにすれば、どういうことを意味しているのか、ターゲットとなる年代の人々にはすぐにピンとくる、と思ったのでした。ただし、若い社員たちは、まったくピンときていないようでした。
そこで若手の説得材料になったのが、スポーツ新聞です。当時、スター選手だった松井秀喜選手らが打てなくなると、「松井、特打」などと大きく一面で報じていました。ネーミングを決めるにあたり、そうしたスポーツ新聞を見せながら「『特打』という名前にしたら、無料で広告が打てるぞ」と言って、若い社員を説得しました。
ソースネクストがミッションとして定めている「製品」というものの価値を、「特打」は改めて教えてくれた製品だった、と私は思っています。「製品」を出すことの意味や重要性です。
たとえば1997年当時、タイピングを学ぼうとすると、パソコン教室が一般的でした。5万円ほど払って通い、タイピングを覚える。教える側も、一人5万円しかもらえない。サービス業は、提供される側もする側も嬉しくないビジネスモデルです。
ところが「製品」になると、提供される側もする側もお互いにとって非常にハッピーなビジネスモデルになります。
当時、「特打」の価格は、売価で約3000円でした。自分の好きなときにいつでも練習できて、払うのはたった3000円です。そして、製品を作った当社側はというと、600万本売れたのですから、180億円も売り上げたわけです。このようにお客さまと提供側の双方に大きなWin(メリット)を生むのが、「製品」のパワーです。
人が人に教えるのであれば、払う側は一人5万円かかり、もらう側も一人5万円にしかなりません。しかし、「製品」になった瞬間に、払う側はたった3000円でよくなって、もらう側は180億円にもなり得ます。「製品」という形態は、両者にとってWinで、社会にも大きく貢献できるのです。
(つづく。詳しくはソースネクスト松田社長著書『売れる力』もご覧ください)