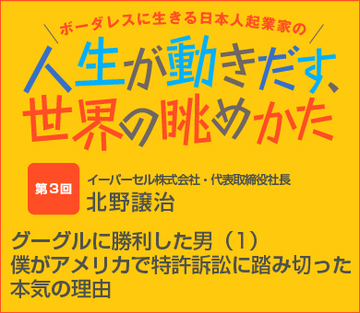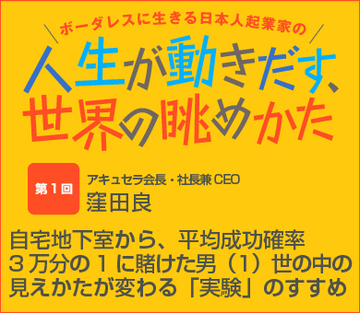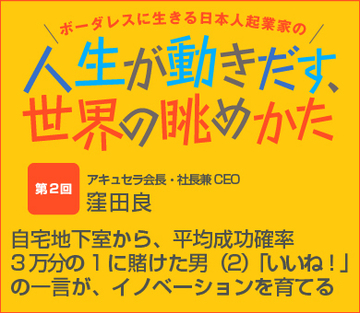六本木の路上で花を売っていた頃
「稼ぐこと」
――それがすべてだった。
一気に時計の針を30年ほど巻き戻して、学生時代にさかのぼってみたい。
大学4年間は、貧乏学生らしく勉強そっちのけでアルバイトに没頭した。とにかく早朝から深夜まで、遊ぶ時間も(当然、勉強する時間も)なく、仕事に明け暮れた。休日は4人の小・中学生の家庭教師、平日は早朝の築地魚河岸のマグロの台車押しにはじまり、授業のない日は仮眠をとって夕方から深夜2時まで、六本木・俳優座向かいにあったスーパー軒先の小さな露店で花を売っていた。
田舎者の貧乏学生が大都会の真ん中で生きていくためと言ってしまえばそれまでだが、花屋では、お金を稼ぐ「尊さ」や「工夫」、「楽しさ」と「辛さ」を店主から徹底的に叩き込まれた。若かったからだろう、そんなことをスポンジのように体が吸収した。一言でいえば、商売の本当の楽しさを教わった気がする。
これまでの人生を振り返ると、僕に起業家精神を植え付けたのは、他でもないこの六本木の花屋の主人だったんだろう。「男なら、小さくてもいいから一国一城の主(あるじ)になれ」とよく話していたことを思い出す。
今や六本木の一等地で店舗を構えるまでになった店主とは、今も親しくお付き合いしている。ちょっと歳の離れた兄貴のような存在で、どんな場面に遭遇しても、無条件に僕を支えてくれる最も頼れる応援団だ。
その花屋にはテント屋根があるだけだったので、天候は店主にとって大きな関心事だったはずだ。確かに、天気は売上に大きく影響した。しかし、店をオープンするかどうかを決めるのには、さして重要ではなかった。というのも、日曜と祝・祭日の定休日以外は、どんな事態に直面しようが例外なく、夕方の4時には必ず生花の陳列を終え、深夜2時まで開店することに決めていたから。そして、いつしか、それが商品の質や価格を圧倒的に凌駕するコア・コンピタンス(他がまねできない能力)になっていた。
嵐の日には花束が飛ばされて、街中を追っかけ回したことも一度や二度ではなかった。豪雨になれば全身ずぶ濡れになったが、それでも店は閉めなかった。真夏は汗だくになり、真冬になれば寒さに打ち震えて花束をつくることすらできないこともあった。しかし、そんな辛い記憶も今、思い起こせば、ただただ懐かしい。紛れもなく、僕の青春時代は、大学のキャンパスではなく、六本木の小さな花屋と共にあった。