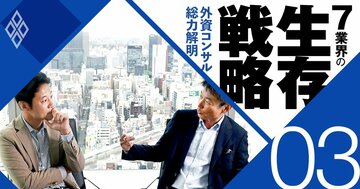どの企業も1つや2つは、「儲けは小さいが、売上高のかさ増しと従業員の雇用維持にはそれなりに役立っている」という事業を抱えているものだ。こういった事業は平時であれば、大儲けはできないが、他の事業を含めた企業全体ではなんとか帳尻が合うので、温存されたままになっている。
だが平時と異なりコロナ時代にはまず、緊急事態宣言のような直接的な感染防止策で、消費・需要が急落する。今後数年間の中期展望でも、テレワークが定着する、都市間移動が減少するといったドラスティックな変化を受けて、「伸びる市場」「衰退する市場」が大きく変わっていく。こういった中、これまで大して稼がなかった事業は、「赤字の問題事業」に容易に転落してしまうのだ。
問題事業の切り離しという消極的な動機ばかりが、事業売却続出の理由ではない。企業は足元では多少収益性が高くても、ノンコア(非中核)事業と位置づけており、長い目では経営資源を傾注できそうにない事業も、これからどんどん売却していく。
企業の経営戦略に詳しいボストン・コンサルティング・グループの杉田浩章日本共同代表は、「優れた経営者はコロナのはるか前、前回危機のリーマンショックの後に、『こういうショックがまた起こったら、うちの会社はどうなってしまうのか』を真剣に考え抜いた。そして弱い事業を整理して、中核事業に経営資源を集中すべく、事業ポートフォリオを見直している」と指摘する。そしてこういった優れた経営者はコロナ時代の今、事業の集中と選択をいっそう真剣に考えているのだという。
強い企業にとって事業売却は決して敗戦処理などではない。稼げる事業への積極的な投資戦略と表裏一体をなして進められるのだ。
ならば、日本企業は今後どんな事業、どんな市場で稼ぐことができるのか。それを予測するために、ダイヤモンド編集部は、外資コンサルティングファーム4社の力を借りた。