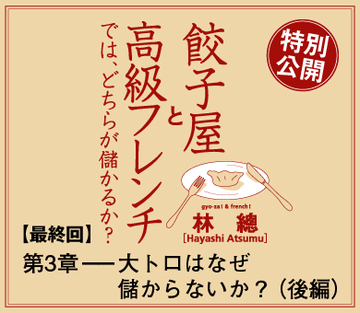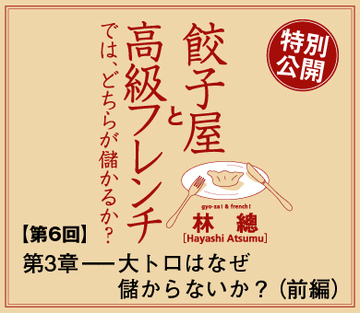「いや、遅くなって申し訳ない」
もじゃもじゃの髪の毛をかきむしりながら、安曇が個室に入ってきた。由紀は、立ち上がって深々と一礼した。
安曇は腰をおろすと、コップの水を一気に飲み干した。
「君は、お父さんから引き継いだ会社を、どのようにしたいと考えているのかな?」
「先生にお願いするまでは、会社が破産したって構わないと思っていました。しかし不思議ですね。日を重ねるごとにハンナを失いたくない、という気持ちが強くなってきました。でも、正直言って、何をすればいいのかわからないのです」
由紀は、自分の気持ちを率直に伝えた。
それまで、目を閉じてじっと耳を傾けていた安曇が口を開いた。
「会社を失いたくない、と思う気持ちはよくわかった。だが、社長である君は、誰も頼ってはいけない。社長の仕事は会社を潰さないことに尽きる」
由紀は顔から火が出る思いがした。会社を潰さないことが自分の使命だとは、思ってもいなかったからだ。単に父親から引き継いだ会社を潰したくない、と思ったに過ぎなかった。心のどこかで、安曇が助けてくれるだろう、と願っていた。
ところが、安曇は、会社の運命は社長が握っている、というのである。
「社長として最初にするべきことは何でしょうか?」
由紀は、おそるおそる聞いてみた。すると、思ってもいなかった答えが返ってきた。
「まず、会計を学ぶことだ」
(会計ですって……)
由紀は戸惑いを覚えた。
会社を経営するのに、なぜ会計が必要なのか見当もつかない――。
それに会計用語は特殊だし、仕訳や数式を見ただけで拒絶反応が起きてしまう。会計はこの世で最も魅力のない学問に違いない、と由紀はつねづね思っていた。