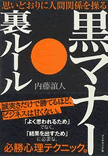「何をしていいかわからない」からスタートする方法(写真はイメージです) Photo:PIXTA
「何をしていいかわからない」からスタートする方法(写真はイメージです) Photo:PIXTA
職場や人前で自分をうまく表現することができない。成長したいと強く願いながらも、今ひとつ突き抜けた成果を出せない。そんなモヤモヤを抱えていませんか?その原因はあなたの能力が低いからではなく、自分を表現できていないだけかもしれません。Zアカデミアで次世代リーダーの育成を行い、2021年4月開校の武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の学部長に就任するほか、多くの大手企業やスタートアップ育成プログラムでメンター、アドバイザーを務める伊藤羊一さんも、かつてはそうだったといいます。『ブレイクセルフ 自分を変える思考法』(世界文化社刊)では、伊藤さんが自身の失敗談を交えながら「自分自身を突破=ブレイクセルフ」した方法を説きます。
人から学ぶしかない
何かをアウトプットをするには、その前にインプットが必要だ。素材がなければ表現はできない。そもそも、自分がどんな個性や価値を持っているのかを見つけるためにも、まずは他人について知らなければいけない。そのためにはインプットだ。まずはアウトプットの機会をつくることが大事、という話も一方でよくするが、それはある程度インプットをしている人向けのアドバイスだ。最初はやっぱりそれなりに自分の中に「ネタ」を仕入れたい。
インプットと言えば、本を読むことがまず思い浮かぶ。
かつて僕は、本を読んで学ぶということが苦手だった。それをつくづく感じたのは、銀行員だった20代のときのことだ。