
今回紹介するのは、「ダイヤモンド」1956年1月1日号に掲載された日本労働組合総評議会(総評)の太田薫(1912年1月1日~1998年9月14日)インタビューだ。総評は、労働組合の全国的結合組織で、1950年の発足当時の基本綱領には、「左右両極からの全体主義の台頭を防ぐ」とある。それに多くの組合員が共鳴し、340万人の組合員を抱える日本最大の組織になった。
というのも、総評結成前には全労連(全国労働組合連絡協議会)という450万人の労働者を擁した全国組織があった。しかし全労連の書記局は共産党に掌握され、全労連の方針に反対すると「反動」「裏切り者」「ファシスト」などと糾弾されて、締め出される始末だったという。こうした状況に不満を持ち、左右全体主義への抵抗と、組合の民主化を志向する労働者が結集し、総評が誕生した。しかし51年、結成翌年の第2回大会では、同年のサンフランシスコ講和条約および日米安全保障条約に反対する「左派社会党」の支持を打ち出し、左傾化を強めていった。
太田は、宇部窒素工業(現宇部興産)の初代労働組合長で、産業別組合の合成化学産業労働組合連合を結成して委員長を務め、総評に参加した労働運動家だ。今回の記事では総評副議長としてインタビューに応じているが、58年から66年まで総評議長を務め、春闘方式を定着させた人物。春闘では、産業別組織単位で賃上げ要求を行い、大企業の妥結状況から中小企業に広がり、人事院勧告もそれを参考に公務員の賃金を決めていく。インタビューの中にも出てくる日本経営者団体連盟(日経連、現日本経済団体連合会)の前田一専務理事とは春闘のたびに激論を交わし、春の風物詩となった。
総評は89年、日本労働組合総連合会(連合)の結成とともに解散したが、同じ労働組合の全国中央組織といっても、連合が果たす役割は70年前の総評とは随分違う。確かに、高度経済成長期を通じて日本的雇用慣行の維持と所得分配の仕組みとして、労働組合が果たした役割は大きかったが、労働組合自体の位置づけは時代を経て明らかに変化したからだ。
現在、労働者の3人に1人は、パート、アルバイト、契約、派遣などの「非正規雇用」となっており、「正規」「非正規」の分断が起きている。その背景には、正社員の権利が守られ過ぎて首を切れないため、その代償として非正規雇用が増えたという流れもある。いまや労働組合は弱者を助ける組織ではなく、正社員という“社会的強者”を守ることが目的となっているとの批判すらある。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
というのも、総評結成前には全労連(全国労働組合連絡協議会)という450万人の労働者を擁した全国組織があった。しかし全労連の書記局は共産党に掌握され、全労連の方針に反対すると「反動」「裏切り者」「ファシスト」などと糾弾されて、締め出される始末だったという。こうした状況に不満を持ち、左右全体主義への抵抗と、組合の民主化を志向する労働者が結集し、総評が誕生した。しかし51年、結成翌年の第2回大会では、同年のサンフランシスコ講和条約および日米安全保障条約に反対する「左派社会党」の支持を打ち出し、左傾化を強めていった。
太田は、宇部窒素工業(現宇部興産)の初代労働組合長で、産業別組合の合成化学産業労働組合連合を結成して委員長を務め、総評に参加した労働運動家だ。今回の記事では総評副議長としてインタビューに応じているが、58年から66年まで総評議長を務め、春闘方式を定着させた人物。春闘では、産業別組織単位で賃上げ要求を行い、大企業の妥結状況から中小企業に広がり、人事院勧告もそれを参考に公務員の賃金を決めていく。インタビューの中にも出てくる日本経営者団体連盟(日経連、現日本経済団体連合会)の前田一専務理事とは春闘のたびに激論を交わし、春の風物詩となった。
総評は89年、日本労働組合総連合会(連合)の結成とともに解散したが、同じ労働組合の全国中央組織といっても、連合が果たす役割は70年前の総評とは随分違う。確かに、高度経済成長期を通じて日本的雇用慣行の維持と所得分配の仕組みとして、労働組合が果たした役割は大きかったが、労働組合自体の位置づけは時代を経て明らかに変化したからだ。
現在、労働者の3人に1人は、パート、アルバイト、契約、派遣などの「非正規雇用」となっており、「正規」「非正規」の分断が起きている。その背景には、正社員の権利が守られ過ぎて首を切れないため、その代償として非正規雇用が増えたという流れもある。いまや労働組合は弱者を助ける組織ではなく、正社員という“社会的強者”を守ることが目的となっているとの批判すらある。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
経済同友会が進歩的といっても
中でやっていることは…
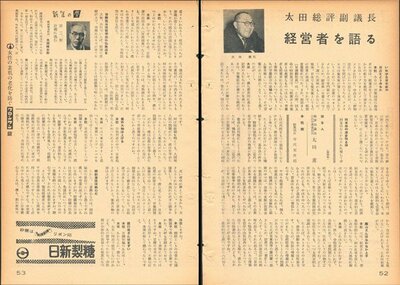 1956年1月1日号より
1956年1月1日号より
――今日は、労働陣営の指導者の方は、経営者をどう見ているか、その在り方を批判していただきたい。これはトップマネジメントで米国に行った中山伊知郎(経済学者、一橋大学初代学長)さんなんかの話なんだが、この30年間ばかりのうちに、米国では資本家が著しく後退したということだった。企業のマネジメントの上で専門家がずっと出てきたとか、顧客第一主義とかで……。違った意味かもしれないが、戦後、日本でも資本家というものが非常に後退した。それで、経営者重役になった。また、桜田武(日清紡社長)さんは、この間、同友会の特別発言で、「経営者と労働者とは異質なものではない。労働者も経営者になれるもんだ」という意味のことを言っている。ところが労働組合の立場からは、いぜん資本家と言っているが、その言葉の迫力は薄れてきていると思うのだが……。
いや、僕ら歴史的に見ると財界の人たちがパージを食らったときは、労働組合が華やかな時代であった。
ところが、パージが解けてから出てきたのは、昔の人。親分の人が出てきてから、やはり、昔の夢が捨てられないのですね。基本的に、日本の会社の取っておる労務政策はあくまでも家族主義的な低賃金政策、これが一つも改められないで、だんだん濃くなったのではないか。







