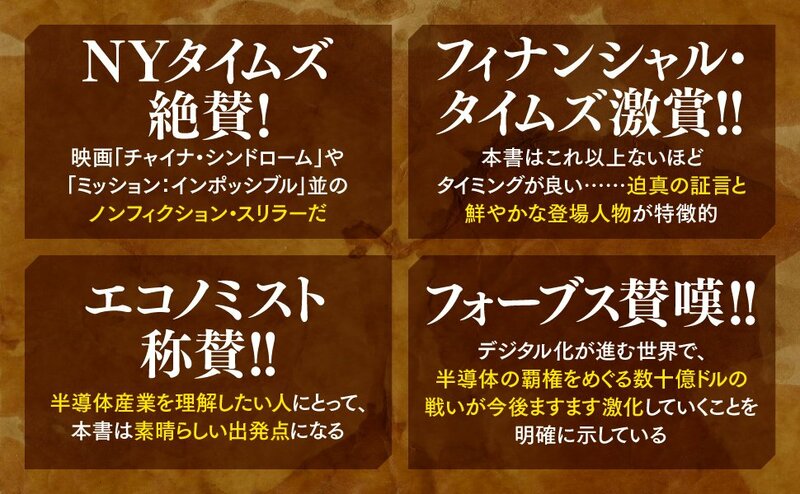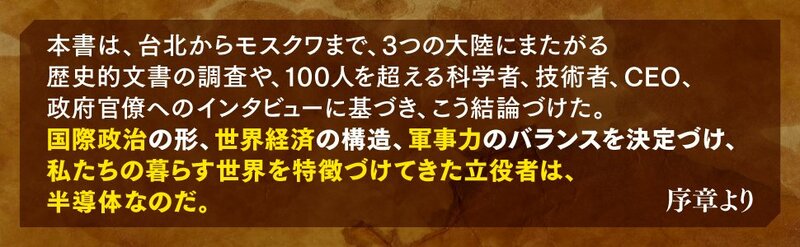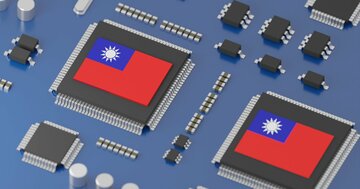NYタイムズが「映画『チャイナ・シンドローム』や『ミッション:インポッシブル』並のノンフィクション・スリラーだ」と絶賛! エコノミストが「半導体産業を理解したい人にとって本書は素晴らしい出発点になる」と激賞!! フィナンシャル・タイムズ ビジネス・ブック・オブ・ザ・イヤー2022を受賞した超話題作、Chip Warがついに日本に上陸する。
にわかに不足が叫ばれているように、半導体はもはや汎用品ではない。著者のクリス・ミラーが指摘しているように、「半導体の数は限られており、その製造過程は目が回るほど複雑で、恐ろしいほどコストがかかる」のだ。「生産はいくつかの決定的な急所にまるまるかかって」おり、たとえばiPhoneで使われているあるプロセッサは、世界中を見回しても、「たったひとつの企業のたったひとつの建物」でしか生産できない。
もはや石油を超える世界最重要資源である半導体をめぐって、世界各国はどのような思惑を持っているのか? 今回上梓される翻訳書、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』にて、半導体をめぐる地政学的力学、発展の歴史、技術の本質が明かされている。発売を記念し、本書の一部を特別に公開する。
 MichaelVi - stock.adobe.com
MichaelVi - stock.adobe.com
オランダという「中立地帯」での立地が
ASMLのひとつの強みだった
キヤノンとニコンにとっての真のライバルは、小さな企業ながら急成長を遂げていたオランダのリソグラフィ装置メーカー、ASMLだった。1984年に、オランダの電機メーカーのフィリップスが、社内のリソグラフィ(露光装置)部門をスピンオフして誕生した企業である。
GCA〔かつてのリソグラフィ世界最大手〕の事業を衰退させた半導体価格の崩壊と同時期に行なわれたそのスピンオフは、タイミングとしては最悪だったといっていい。おまけに、ベルギーとの国境に程近い町、フェルトホーフェンは、半導体産業における世界的企業に似つかわしい立地とは思えなかった。ヨーロッパはそれなりの数の半導体を生産していたが、シリコンバレーや日本に後れを取っていることは明白だった。
オランダ人技術者のフリッツ・ファン・ハウトは、物理学の修士号を取得した直後の1984年にASMLへと入社したとき、自分から入社したのか、それとも入社させられたのか、と同僚に訊かれたことがあった[1]。
当時のASMLには、フィリップスとの関係以外に、「工場もなければ資金もなかった」と彼は振り返る[2]。それでは、社内にリソグラフィ装置の本格的な製造工程を築くのは不可能だっただろう。
代わりに、ASMLは世界中の供給業者から入念に調達した部品を用いてシステムを組み立てることにした。主要な部品を他社に頼るのは、明らかにリスクがあったが、ASMLはそのリスクを抑えるすべを学んだ。
おかげで、日本の競合企業がすべてを自社でつくろうとしたのに対し、ASMLは市場から最良の部品を仕入れることができた。EUV(極端紫外線)リソグラフィ装置の開発に注力し始めるころには、さまざまな供給源から調達した部品をひとつにまとめる能力が、同社の最大の強みになっていた。
ASMLのもうひとつの強みは、想定外ではあるが、オランダという立地にあった。1980年代から1990年代にかけて、同社は日米貿易摩擦において中立的な存在とみなされ、アメリカ企業はASMLをニコンやキヤノンに代わる信頼できる取引先として扱った。
たとえば、アメリカの新興DRAMメーカーのマイクロンは、リソグラフィ装置を購入する際、日本の主要メーカー2社のいずれかに頼る代わりに、ASMLに頼った。日本の2社は、日本におけるマイクロンの競合DRAMメーカーとの関係が深かったからだ[3]。
フィリップスとの縁が
TSMCとASMLの協力体制を生んだ
フィリップスからスピンアウトしたというASMLの歴史もまた、意外な形で奏功した。台湾のTSMCと深い関係を築くのがスムーズになったからだ。フィリップスはTSMCに大規模な投資を行ない、自社の製造工程技術や知的財産をその若きファウンドリへと移転していた。TSMCの工場はフィリップスの製造工程に基づいて設計されていたので、ASMLはお抱えの市場を手にしたも同然だった。
1989年にTSMCの工場で起きた火災事故も思わぬ追い風となった。TSMCが火災保険の給付金で、19台の新型リソグラフィ装置を追加購入する形となったからだ。
ASMLとTSMCはもともと、半導体産業の片隅で小さな会社として産声を上げたが、両社はパートナーシップを築き、二人三脚で成長を遂げていった。その協力体制がなければ、今日のコンピューティング分野の進歩はぴたりと止まっていただろう[4]。
ASMLとTSMCのパートナーシップは、1990年代の第三次「リソグラフィ戦争」の到来を予感させた。産業界や政界のほとんどの人は認めようとしなかったが、それは政治的な闘争にちがいなかった。
当時のアメリカは、冷戦の終結を祝福し、平和の配当を享受している真っ最中だった。技術力、軍事力、経済力、どの基準で見ても、アメリカは同盟国も敵国も含めた世界の頂点に君臨していた。
ある有力な評論家は、1990年代のことを、アメリカの優位が確立した「一極時代」と表現した。実際、湾岸戦争はアメリカの驚異的な技術力と軍事力を証明する形となった[5]。
1992年、アンディ・グローブ[インテル元CEO]がEUVリソグラフィ研究へのインテル初の本格投資を承認しようとしていたころ、冷戦中の軍産複合体から生まれた半導体産業でさえ、もはや政治など関係ない、と結論づけたのは無理もなかった。
経営の第一人者たちは、権力ではなく利益が世界のビジネス風景を形づくる、未来の「国境なき世界」を約束した[6]。経済学者たちは加速するグローバル化について口々に語った。CEOや政治家たちもまた、こうした新たな知的流行を受け入れた。
そのころ、インテルは再び半導体事業の頂点に返り咲いていた。日本のライバルたちをはねのけ、PCを動かすチップの世界市場をほぼ独占し、1986年から毎年利益を上げ続けていた[7]。政治について心配する理由がどこにあるだろう?
アメリカ政府がEUVリソグラフィ研究から
キヤノンとニコンを締め出した理由とは
1996年、インテルはアメリカのエネルギー省が運営するいくつかの研究所とパートナーシップを結ぶ。光学をはじめ、EUVリソグラフィを機能させるのに必要な分野の専門知識を共有するためだ。
インテルはほかに数社の半導体メーカーをそのコンソーシアムに迎え入れたが、ある参加者の記憶によれば、予算の大半を拠出したインテルが、会議を「95%牛耳っていた」という[8]。
インテルは、ローレンス・リバモア国立研究所やサンディア国立研究所がEUVシステムを試作するための専門知識を持つと知っていたが、両研究所の主眼は量産ではなく科学的な側面のほうにあった。
しかし、カラザースの説明によれば、インテルの目標は「何かを測定するだけでなく、つくること」にあった。そこで、インテルはEUVリソグラフィ装置を市販化し、量産できる企業を探し始めた。アメリカにそんな企業は存在しない、というのが同社の出した結論だった。
GCAはもうない。現存するアメリカ最大のリソグラフィ装置メーカーであるシリコンバレー・グループは、技術的に後れを取っていた。しかし、1980年代の貿易戦争の苦い記憶がいまだ抜けきらないアメリカ政府は、日本のニコンやキヤノンに国立研究所と手を組ませることだけは避けたかった(ニコン自身は、EUV技術がうまくいくとは考えていなかったが)。となれば、残るリソグラフィ装置メーカーはASMLのみだった[9]。
外国の企業に、アメリカの国立研究所で行なわれている最先端の研究へのアクセスを認めるという考えに、アメリカ政府内では疑問の声が上がった。EUVリソグラフィ技術に直接の軍事的応用はなかったし、この技術がうまく機能するのかどうかもまだ定かではなかった。それでも、もし機能すれば、アメリカはあらゆる計算に不可欠な装置を、ASMLに依存することになる。
だが、国防総省(ペンタゴン)の何人かの当局者を除いて、懸念を抱く者は政府内にほとんどいなかった[10]。大半の人々はASMLやオランダ政府を信頼できるパートナーとみなしていたし、政治のリーダーたちにとって重要なのは、地政学よりも仕事への影響のほうだった[11]。
アメリカ政府は、リソグラフィ装置用の部品の製造工場をアメリカ国内に建て、アメリカの顧客に商品を供給し、アメリカ人を職員として雇用するようASMLに要求したが、ASMLの核となる研究開発活動は本国オランダで行なわれた。
商務省、国立研究所、関係企業の主な意思決定者たちの記憶によれば、この協力関係を前進させるという政府の決断において、政治的配慮は仮にあったとしてもたいして大きな役割を果たしていなかったという[12]。
長期にわたる遅れと巨大な予算超過に見舞われながらも、EUVリソグラフィ技術に関するパートナーシップはゆっくりと進展を遂げていった。アメリカの国立研究所における研究から締め出されたニコンとキヤノンは、独自のEUVリソグラフィ装置を開発しないことを決めたため、ASMLが世界で唯一のメーカーとなった。
[1] Peter Van Den Hurk, “Farewell to a ‘Big Family of Top Class People,’” ASML, April 23, 2021, https://www.asml.com/en/news/stories/2021/frits-van-hout-retires-from-asml.
[2] フリッツ・ファン・ハウトへの2021年のインタビューより。
[3] Rene Raiijmakers, “Technology Ownership Is No Birthright,” Bits & Chips, June 24, 2021.
[4] フリッツ・ファン・ハウトへの2021年のインタビューより。“Lithography Wars(Middle): How Did TSMC’s Fire Save the Lithography Giant ASML?” iNews, February 5, 2022, https://inf.news/en/news/5620365e89323be681610733c6a32d22.html.
[5] Charles Krauthammer, “The Unipolar Moment,” Foreign Affairs, September 18, 1990.
[6] Kenichi Ohmae, “Managing in a Borderless World,” Harvard Business Review(May-June 1989).
[7] ブルームバーグのデータによる。
[8] ジョン・テイラーへの2021年のインタビューより。
[9] Chuck Gwyn and Stefan Wurm, “EUV LLC: A Historical Perspective,” in Bakshi, ed., EUV Lithography(SPIE, 2008). ジョン・カラザースとジョン・テイラーへの2021年のインタビューより。
[10] ケネス・フラムとリチャード・ヴァン・アッタへの2021年のインタビューより。
[11] David Lammers, “U.S. Gives Ok to ASML on EUV,” EE Times, February 24, 1999. このメディア報告書は、ASMLが同社の装置の一部をアメリカで生産することをアメリカ政府に約束した、と報告している。私がアメリカの当局者やASMLにインタビューしたかぎりでは、そうした約束の存在は確かめられなかったが、複数の元当局者は、そういう約束があったことは十分にありえるし、あったとすれば公式ではなく非公式のものだっただろう、と述べている。現在、ASMLはEUVリソグラフィ装置の一部をコネチカット州の製造工場で生産している。よって、アメリカ政府との約束を忠実に守っているようだ(そんな約束が実際にあったとすれば、だが)。
[12] 私のインタビュー相手はひとりとして、外交政策的な考慮事項がこの決断において重要だったとは考えていなかったし、多くの者はこの話題が議論されたという記憶もなかった。
(本記事は、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』から一部を転載しています)