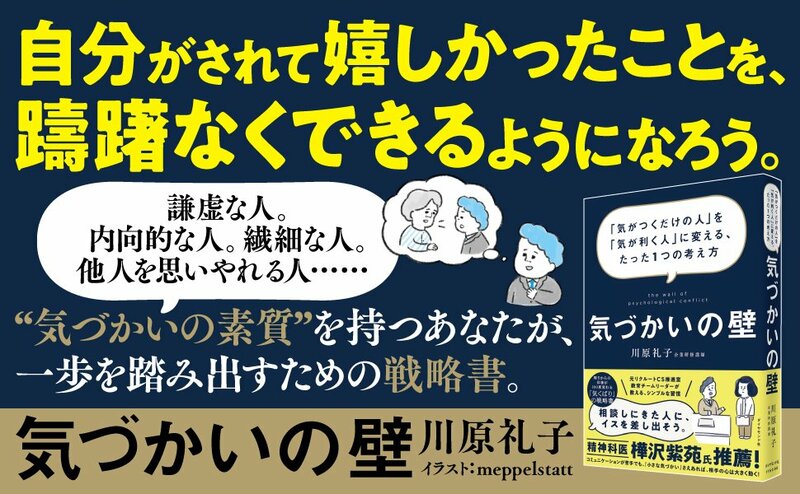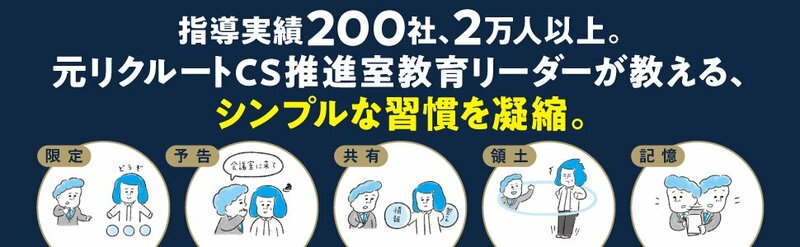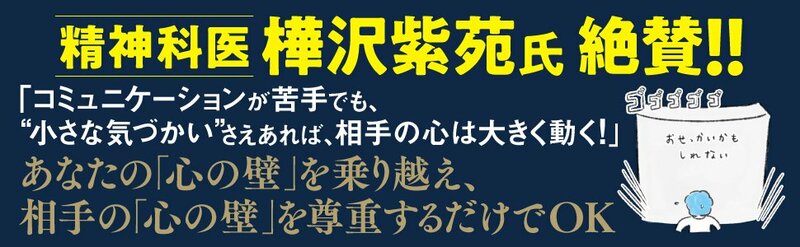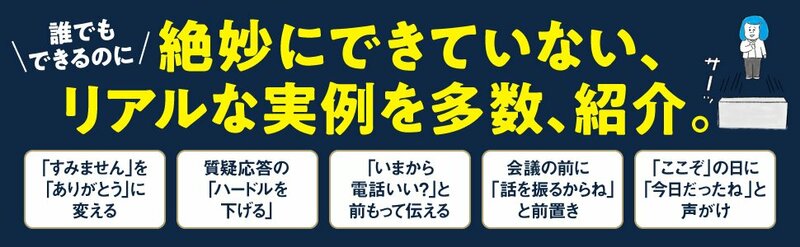職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…!」と自分に言い訳したり……。
気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか?
この連載では、「顧客ロイヤルティ(お客さまとの信頼関係づくり)」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた『気づかいの壁』の著者、川原礼子さんが、「気がつくだけの人」で終わらず、「気がきく人」に変われる、とっておきのコツをご紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
苦情のピンチは「大きなチャンス」
これまで、後輩や部下への「アドバイス」で悩む先輩や上司のみなさんをたくさん見てきました。
そんな方々に知っておいてもらいたい考え方があります。
それは、苦情対応の最前線にいた頃に知った、苦情の申し立てと再購入率の相関関係を表す「グッドマンの法則」((C)顧客ロイヤルティ協会)という考え方です。
その法則は3つあり、1番目に掲げられている法則が、次のようなものです。
「不満を持った顧客のうち、苦情を申し立て、その解決に満足した顧客の当該商品サービスの再購入決定率は、不満を持ちながら苦情を申し立てない顧客に比べて高い」
実際の例でいうと、1万円以上の商品の場合、苦情を迅速に解決してもらえたお客さまの再購入率は「82%」で、苦情を申し立てなかった人の再購入率は「9%」だったのです。
この数字を見ると、苦情は「信頼回復の機会につながるチャンス」ということを教えてくれていることがわかります。
つまり、「言ってもらえてよかった」のです。
最後は「ポジティブ」に転じる
若手が失敗すると、原因を追究し、厳しく指摘したくなるときがあると思います。
ただ、絶対にやってはいけないのは、「二度としないように」と、最後に言い残すようなことです。
また、優しい人が言いがちな「まあ、気にしないようにね」という声がけも、一見、救われるように聞こえますが、その言葉を真に受けられてしまうと逆効果です。
では、厳しいことを伝えながらも、前向きな感情を残すためには、どうすればいいのでしょうか。
アドバイスの最後に、こんな声をかけてあげてください。
「今、失敗を経験しておけば、繁忙期の対策が立てられるからよかったと思いますよ」
「早い段階で先方にお詫びに行けたからよかったよ」
「勘違いがこの機会にわかったし、よかったはずだよ」
と、たとえわずかながらでも、「失敗したからこそ得られた経験」のほうに目を向けてみて、そこに触れるようにしましょう。
「よかったね」という言葉には、失敗した過去をよい記憶として残す力があるのです。
また、「クレーム対応」も似ています。
たとえ、相手がどんなに非常識なことを言っていても、「相手は今、そう思っている」ということを受け止めて、正しいかどうかのジャッジは、いったん横に置いておきます。
どんなに大きく怒っているお客さまでも、気持ちがおさまり、許してもらえたら、お詫びをお礼に切り替えます。
誰でも、謝られ続けるより感謝されたほうが嬉しいからです。
「〇〇様、最後になりますが、本日はご連絡をくださってありがとうございました」
と、最後を感謝で締めくくると、最初は苦情だった電話が、切るときには「いいことをした」という温かい記憶に変化するのです。
株式会社シーストーリーズ 代表取締役。
元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー。
高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。
2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ(C-Stories)を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。『気づかいの壁』(ダイヤモンド社)が初の著書となる。