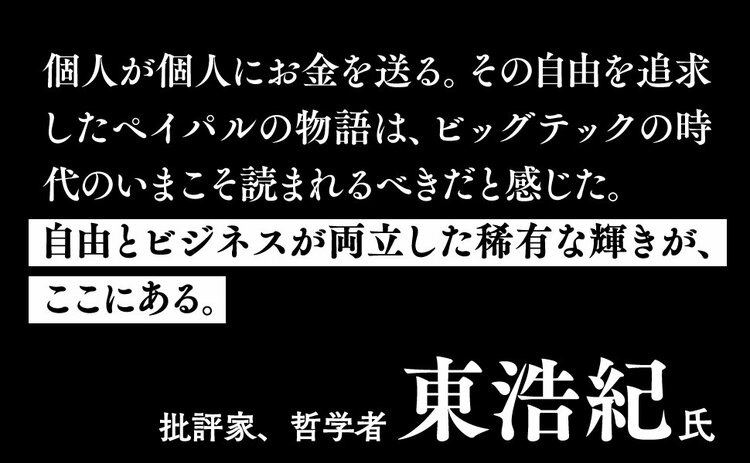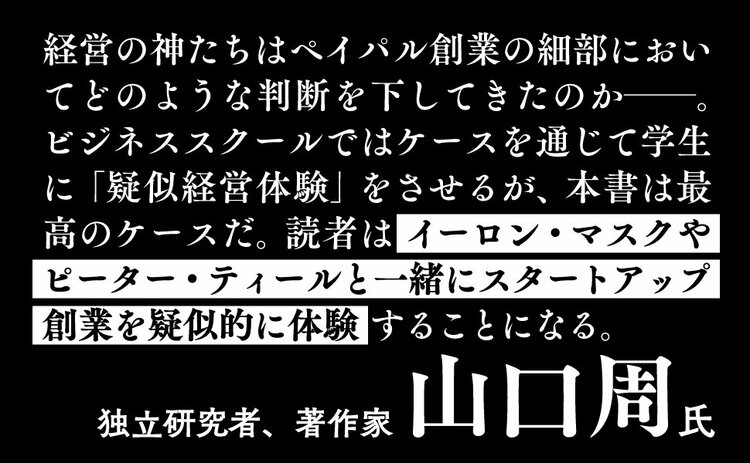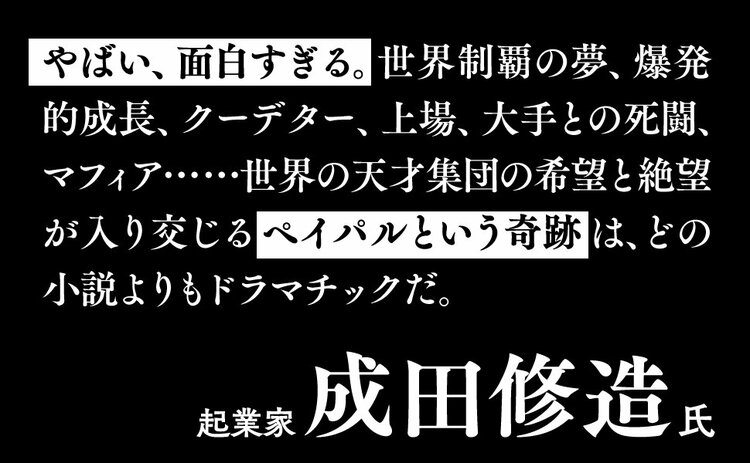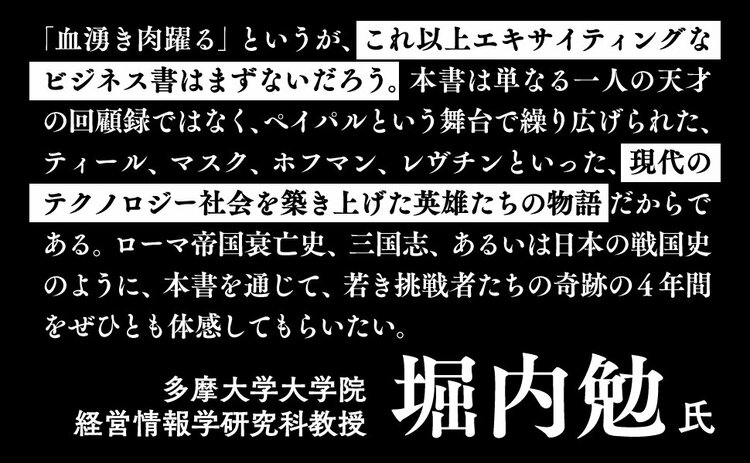1999年、若きイーロン・マスクと天才ピーター・ティールが、とある建物で偶然隣り同士に入居し、1つの「奇跡的な会社」をつくったことを知っているだろうか? 最初はわずか数人から始まったその会社ペイパルで出会った者たちはやがて、スペースXやテスラのみならず、YouTube、リンクトインを創業するなど、シリコンバレーを席巻していく。なぜそんなことが可能になったのか。
その驚くべき物語が書かれ全米ベストセラーとなったのが『創始者たち──イーロン・マスク、ピーター・ティールと世界一のリスクテイカーたちの薄氷の伝説』(ジミー・ソニ著、櫻井祐子訳、ダイヤモンド社)。東浩紀氏が「自由とビジネスが両立した稀有な輝きが、ここにある」と評するなど注目の本書より、内容の一部を特別に公開する。(初出:2023年5月10日)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「自分の存在」にどんな意味があるのか?
イーロン・マスクが物理学を正式に学び始めたのはペンシルベニア大に移ってからだが、それよりずっと前から傾倒していた。
「12、3歳のとき、実存の危機に陥った」とのちに語っている。「自分の存在にどんな意味があるのか、人間がなぜここにいるのか、すべてが無意味なのか、などと自問していた」
この危機のさなかに、希望をくれるSF小説を見つけた。ダグラス・アダムスの『銀河ヒッチハイク・ガイド』だ。
小説の主人公アーサー・デントは、地球滅亡を生き延び、伝説の星マグラシアを探して銀河を旅する。デントはこの冒険で「超知性を備えた汎次元的な生命体」の古い種族が、「ディープ・ソート」というコンピュータを設計して「生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問」に答えを出そうとしていることを知る。
マスクはこの本から、正しい問いを立てることは、答えを導き出すことと同じくらい大切だと悟り、そのことが実存的不安を和らげたと語っている。「問いは答えより難しいことが多い。そして、問いを正しく立てることさえできれば、答えを考えるほうは比較的簡単だ」
マスクの見るところ、物理学は正しい問いを投げかける学問だった。『銀河ヒッチハイク・ガイド』を読み終えると、ノーベル賞受賞学者リチャード・ファインマン博士の著書を読みふけった。
官僚主義に阻まれたらどうする?
大学でさらに物理学にのめりこみ、ペンシルベニア大学ウォートン校の経営学の授業では、ウルトラキャパシタ(電気二重層コンデンサ)と宇宙エネルギーシステムの経済的メリットに関するレポートを書いて高い評価を受けた。
マスクは授業で物理学の問いに取り組みながらも、卒業後に物理関係の道に進むべきかどうか悩んだ。「たとえば、粒子加速器の建設計画が官僚主義に阻まれたらどうする?」と彼は言う。「粒子加速器がSSC(超伝導超大型加速器)計画みたいに中止されたら最悪だと思ってね」
だがそれに代わる道は何なのか? ウォートンの同級生は銀行やコンサルティング会社に内定が決まり、多額の契約ボーナスをもらっていた。銀行はインターンとして経験済みだった。そんなありきたりの進路は、議会に邪魔されながら粒子加速器に取り組むよりさらにつまらなそうだ。
結局、迷える大学生の定番の進路を選んだ。大学院だ。マスクはスタンフォード大学の材料科学工学の博士課程に出願し、合格した。(中略)
ネットスケープのビルでうろつく
コンピュータプログラミングは、マスクにとっては目新しくもなんともなかった。子どものころからコードを書いていた。
13歳で「死の水素爆弾とステータスビーム装置を積んだ異星人の宇宙貨物船」を破壊する「ブラスター」というビデオゲームをつくり、ソースコードを販売した。
起業も経験済みだった。カナダでマスク・コンピュータ・コンサルティングという会社を設立し、コンピュータとワープロを売った。クイーンズ大学学生新聞の広告には、この会社が「最先端」であることが謳われ、「昼夜いつでもお電話ください」と書かれている。
マスクの見るところ、ヤフーやアマゾンの創業者は自分とたいして歳も変わらず、自分より賢いはずもなかった。とはいえベンチャーを始めるのは、とくにスタンフォード大学院への切符を手に入れたいまとなっては、リスクが高いように思われた。とりあえずの落としどころとして、当時の大人気IT企業、ネットスケープの求人に応募してみた。
ネットスケープからは返事がなかったが、正式に断られたわけでもなかった。マスクはネットスケープの本社に行って、ロビーをうろつくことにした。そこで誰かと話しているうちに何かにつながるかもしれない。だがこの計画も空振りに終わった。
「僕はシャイで誰とも話せなかった」と、のちに起業家のケヴィン・ローズに打ち明けている。
「だから、ただロビーに突っ立っていた。あれは恥ずかしかったね。誰かに話しかけようと思って立っていたのに、ビビって誰とも話せずに帰ってきたんだから」
自分が「世界に最も影響を与える」には?
ネットスケープの線が消えると、大学院に行くか、インターネット企業を立ち上げるかで悶々と迷った。「未来に最も影響を与えることは何だろう、僕らが解決すべき問題は何だろうと考えていた」
ペンシルベニア大学時代、彼は近未来に大きなインパクトを与える分野をリストアップした。
インターネット、宇宙開発、再生可能エネルギー。
だが未来を変える分野にこの自分が、イーロン・マスクという人間が影響をおよぼすには、いったいどうしたらいいのだろう?
マスクはピーター・ニコルソン〔注:マスクが新聞で見つけて興味を持ち、いきなり電話して知遇を得た天才的人物。本書で前出〕に相談した。トロント界隈をゆっくり散策しながら、二人で次のステップを考えた。
ニコルソンはマスクの背中を押した。「いいか、イーロン。インターネットのロケットはぐんぐん上昇している。君のアイデアに賭けてみるのに、いまほど絶好のタイミングはない。博士号なんていつでも取れるじゃないか。その機会はこの先もずっとテーブルに置かれたままだ」
自身もスタンフォードの博士号を持つニコルソンの助言には重みがあった。
それでもマスクは95年夏、ペンシルベニア大学を去り、スタンフォード大学博士課程に進もうとした。だがいざベイエリアに戻ると、ニコルソンのアドバイスが気になってきた。「インターネットのめざましい急成長を横目で見ながら何年も過ごすのはあまりに歯がゆく、いても立ってもいられなくなった」とマスクは言う。スタンフォードに、入学時期を1995年9月から翌年の1月に延期することを願い出た。
マスクはいまでこそ、ビジネス界きってのリスクテイカーとみなされているが、このときは大学院に進むかどうかを逡巡していた。当時がどれほどリスクの高い環境だったかがうかがい知れる。
「僕は生まれながらのリスクテイカーじゃない」とマスクはペン大の校友会誌ペンシルベニア・ガゼットで語っている。「奨学金と学資援助もあったから、それを失うことにもなる」。入学延期が認められたとき、スタンフォードの学部担当者にこう言われたという。
「まあ、やってみなさい。でも3ヵ月後にまたお会いすると思いますよ」
〔注:しかしその後、マスクはスタンフォードに戻らず、事業にのめりこむことになる〕
(本原稿は、ジミー・ソニ著『創始者たち──イーロン・マスク、ピーター・ティールと世界一のリスクテイカーたちの薄氷の伝説』からの抜粋です)