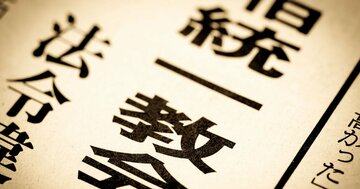モラルを崩壊させる帳尻合わせ
組織カルチャーの全否定を!
「旧日本軍発祥の働き方」は、日本企業の不正の温床になっている。その代表が「員数主義」である。簡単に言えば、「数の帳尻合わせ」である。
実際に従軍経験のある評論家の山本七平氏によれば、敗戦直後、多くの軍隊経験者が、この「員数主義」こそ日本軍の敗因だったと指摘したという。
なぜかというと、これがまん延したことで、参謀などの幹部から現場の一兵卒まで、まさしく「組織全体」のモラルが崩壊してしまったからだ。
「員数」は日本軍の中でよく使われた独特な言葉で、例えば、部隊の装備品などの検査で数が合わなかったときなど、鉄拳制裁とともにこんな感じで使われた。
「バカヤロー、員数をつけてこい」
日本軍は「員数」さえ合えば、実態が異なっていても「問題なし」という考えがまん延していた。そして、戦局が悪化すればするほど、「員数合わせ」にのめり込んでいく。大本営は、勝ち目のない戦地や、意味のない神風特攻にも「員数合わせ」で若い兵士を次々に送り込んだ。自ら血を流さない大本営からすれば、戦争は足りないところへ戦力を送り込む「数合わせゲーム」になっていたのだ。
それは「不正」も同じだ。司令官は師団長など現場に「軍紀や風紀の乱れを是正せよ」と命令を出して、悪い報告が上がってこなければ、「軍紀や風紀の乱れなし」と判断をする。ただ実際は師団長が「員数合わせ」をして、略奪や捕虜殺害などの違法行為を握りつぶしてカウントしていなかっただけというケースも多々あるのだ。
ここまで言えば、筆者が何を言わんとしたいのか、もうおわかりだろう。
データ改ざん、利益のかさ上げ、統計不正、そして保険金の不正請求など、近年、日本の組織でまん延している「不正」の本質をつきつめていけば、すべて「員数合わせ」で説明がつくのだ。
では、どうすればこの「員数主義」由来の不正を防ぐことができるのか。筆者は嫌というほど、この「員数主義」が引き起こす不正を見てきたが、今のところ、これを是正する方法は「組織の解体的出直し」しかないように思う。つまり、これまでの組織カルチャーの「否定」だ。
しかし、日本企業は「前例踏襲」を重んじるので、これが難しい。「創業精神を引き継げ」とか「苦しい時こそ原点に戻れ」みたいなストーリーが好きなので、喉元過ぎればなんとやらで、ほどなくすると、亡霊のように古いカルチャーが復活して、同じ過ちを繰り返す。
そういう意味では、大株主の兼重前社長の影響力が排除できないビッグモーターの「再生の道」は、かなりいばらの道ではないだろうか。
(ノンフィクションライター 窪田順生)