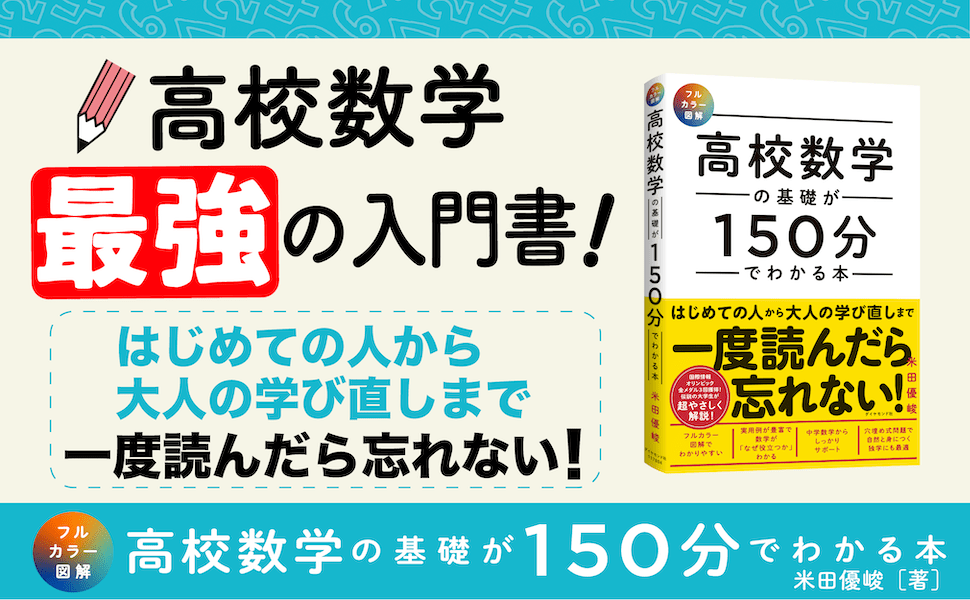子どもから大人まで数学を苦手とする人は非常に多いのではないでしょうか。ましてや高校数学ともなるとほとんどの人が挫折してしまった経験を持っているでしょう。しかし、高校数学の基礎は丁寧に学べば特別難しいものではなく、同時に得た知識は私たちの生活にも大きく役立ちます。そんな高校数学の超入門書として書かれたのが『【フルカラー図解】高校数学の基礎が150分でわかる本』です。本記事でははじめての人から大人の学び直しまで1人で高校数学が学べる本として発刊された本書より内容の一部を抜粋してお届けします。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
大人なら知っておきたい平均値と中央値の違い
平均値には、極端なデータの影響を受けやすいという問題点があります。
たとえば、年収5000万、600万、400万、300万、200万の人がいる場合、平均値は(5000+600+400+300+200)/5=1300万となり、2位の人の倍以上になってしまいます。そこで平均値に代わる指標として、中央値が使われることがあります。※
※もちろん中央値にも欠点があります。たとえば6人がテストを受けて100、100、100、99、50、40点だったとき、99点の人はどう考えても「できる側」なのに、中央値である99.5点を参考にすると「できない側」だと誤解してしまいます。ですので平均値と中央値を上手く使い分けることが重要です。
中央値とは
中央値は、データを小さい順に並べ替えたとき、ちょうど真ん中に来る値のことです。たとえばデータが5個あるときは下から3番目が中央値になります。(下図の中央値は400です)

ただし、データの数が偶数の時は真ん中が2つになるので、この2つを平均した値が中央値になります。(下図の中央値は350です)